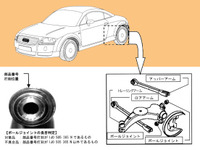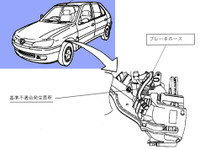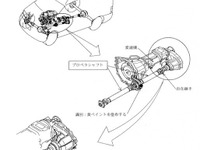日本自動車販売協会連合会が発表した1月の新車販売台数(軽を除く)によると、トラックが大幅に落ち込んだ影響で前年同月比2.6%減の24万8489台だった。好調なのは『フィット』、『モビリオ』が好調なホンダと、シボレー『クルーズ』が好調なスズキのみ。

タクシーやバスの規制緩和を促す改正道路運送法が1日、施行された。これらの事業は従来の免許制から許可制になり、新規参入や廃業が原則自由になるほか、運賃も一定範囲内で多様化が認められる。

大阪府警は31日、自動車盗難被害数が19年連続で日本一だったことを受け、駐車場管理会社や通関業者を含む自動車関連8団体に対し、盗難防止や不正輸出の防止を呼びかける緊急提言を行ったことを明らかにした。

全国軽自動車販売協会連合会が1日発表した1月の軽乗用車の販売台数は、新型車を投入したメーカーとそうでないメーカーの売れ行きの差が歴然となった。三菱が4割近い伸びを示したのに対しホンダは1割の減少となった。

自動車運転代行法(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律)の施行令が1日、閣議決定され、6月1日から施行される見通しになった。自動車運転代行業を営むには今後、公安委員会の認定が必要。

交通事故を起こしたドライバーへの処分を重くする改正道交法施行令が1日、閣議決定され、6月から施行される見通しとなった。