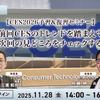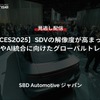毎年新年早々に米国ネバダ州ラスベガスで開催される見本市と言えば、ハイテクの展示会「CES」である。
例年自動車メーカーも発表や展示を行うが、今年(1月7日から10日に開催)の日本勢はと言えば、「ウーブンシティ」について発表を行ったトヨタ、新世代EV「ゼロシリーズ」の発表を行ったホンダ、それにCES初参加となったスズキ。それに加えて、長らく気を持たせて来た「AFEELA(アフィーラ)」の量産モデル『AFEELA 1』を発表したソニーホンダモビリティと言ったところだろう。
「ソニーが入ると違う」かはもう少し先に

さてどこから行こう。まずはアフィーラについて。アフィーラの最大の関心はその価格だったが、2種類のトリムの内、安い方の「オリジン」が8万9900ドル(約1416万円)。高い方の「シグネチャー」が10万2900ドル(約1621万円)。流石に最初のプロトタイプ発表から2年経つので、新鮮さは失われているのだが、いよいよ米国での発売開始ということで、どれだけの顧客に訴求できるかが勝負になってくる。
ソニーホンダによるアフィーラとホンダ独自のゼロシリーズは、全く別のラインで事業が動いているとのことで、CESでも、カンファレンスの時間が一部かぶることを調整もしないほどに完全に無関係。何なら他社の話くらいの関係性である。逆に言えば2つのビジネスラインが綱引きで勢力争いをすることもない。それぞれのチームが自分のベストの形でやるという気迫の表れだと受け取ることもできる。
基本的には走る機能に関してはホンダが、エンターテインメントを含むソフトウエア系をソニーが受け持つことになっている。カメラやLiDARをはじめとする40個のセンサーを装備し、自慢の高速演算能力を持つECUとAIを投入して高度なADASを実現しているとのことだが、それらが作り出す体験が期待を超えるものなのかどうか、そこは乗ってみないと何とも言えない。交通法規や規制の影響も受けるので、米国の仕様と全く同じことが日本国内仕様でできるかどうかもまだわからない。
「なるほどソニーが入ると違う」になっているかどうかは、もう少し先にわかるだろう。
新しさを追求するホンダの0シリーズ

次はホンダ繋がりで「0(ゼロ)シリーズ」。ホンダのプレミアムEVシリーズになると思われる新シリーズが「ゼロシリーズ」である。「Thin, Light, and Wise.」のアプローチで「原点に立ち返り、移動体を0から考え直す」シリーズになるとのこと。ボディタイプはランボルギーニと見紛うウェッジシェイプのサルーンと、どこかクライスラー系の「MOPAR」を彷彿とさせるSUVの2種類。
クリーンな面で構成されるデザインは斬新で個性的である。シリーズの立ち上がりとしてはこのくらい思い切って個性を打ち出さないと埋もれてしまう。とにかくEVに関してはどこの製品も何とかして他社を置き去りにするくらいの新しさを出そうと躍起になっている中で戦うのだ。
そうした状況を考えると「Thin, Light, and Wise.」というある意味古典的とも言えるデザインテーマに軸足を置きながら、面の構成で新しさを追求するのはクレバーなやり方である。基本は正統派で、変化はフィニッシュで作り出すわけだ。
ちなみに発売はSUVタイプの『Honda 0 SUV』が先で2026年。言われてみればデザインの細部の煮詰まり具合もこちらの方が少し進んでいるように思う。逆に言えば、まだ生産までに時間のある『Honda 0 SALOON(ゼロ サルーン)』の方は、イメージを引っ張るためにも現時点ではとんがったデザインが必要であり、そういう意味ではよりコンセプト性が高い。おそらく量産までにはもう少し落ち着いていくだろう。
ハードウエアとしてのエンジニアリングの基本は、長く延伸したホイールベースでバッテリー搭載量を確保している。ただしホイールベースを伸ばせば当然小回りが厳しくなる。そこで、モーター/インバーターの横幅がICEよりコンパクトである点を活かして、フロントメンバーの幅を狭めて、前輪の最大舵角を増やすことで小回り性を確保している。このメンバー幅のもうひとつの恩恵としてフロントサスアームの長さにも余裕ができ、走りの質の向上やばねレートの自由度にもメリットがあるはずである。
さらにフロントフードを低くしてカウル高さ(Aピラー起点の高さ)を低く押さえて空力を有利にするなど、現在最新のEVのトレンドをしっかり押さえたデザインとなっている。空力と言えば、おそらくはテールエンドのデザインも空力最優先となっていると思われ、引き換えに物理視界は抑制される。というよりそれをきっぱりと諦めることで新しい時代の造形を作ろうとしているように思える。どちらの車両も、後ろに箱を背負ったASIMOの様な形状のリヤデザインである。後方視界についてはカメラの画角によってカバーされるだろう。
要するにゼロシリーズのデザインでは、肉眼での直接視界をある程度諦めることで、従来になかったリヤデザインを実現してみせた。これに関しては多少の差はあれどSUVもサルーンも同じ考え方。この2台は確かにコンセプト的に双子の関係にある。

またルネサスとの協業によってECU用の高性能システム・オン・チップ(SoC)を新たに開発することで、高速演算能力と省電力の両立を図る。詳細は語られていないが、常識的に考えて、従来分散型となっていた各種ECUをまとめて一元化する方向になると思われ、それによって従来のスパゲッティ状態を卒業し、SDV時代におけるアップデートの設計・管理コストの低減を狙う。
もう一点、ソフトウエアプラットフォームもこのチップセット同様、ブランニューデザインされる。いわゆる新世代的なビークルOSである。AD /ADASやインフォテインメントなどをカバーするという意味で、このゼロシリーズの核心のひとつである。そこにいかに力を入れているかは「ASIMO OS(アシモOS)」というネーミングからも想像が付く。
OSのアップデートコストの低減には明らかにアドバンテージがあると思われるが、その先でホンダのSDVが何を見せてくれるのかはまだわからない。中国製EVが始めた昨今のブームでは超信地旋回(その場旋回)とカラオケがSDVの証のようになっているが、一発芸で煙に巻くのはそろそろ終わりにして、これぞSDVという明確なユーザーメリットのある機能をきっちりと見せてほしい。
トヨタ ウーブンシティは何をするところなのか?

さて、お次はトヨタのウーブンシティである。ウーブンシティの話を理解するためにまず一度頭を整理してほしい。「未来のモビリティのための実験都市を作る」。そう聞いたら多くの人はまるでタイムスリップでもしたように、未来のモビリティを体験できることを想像してしまう。だがウーブンシティはそういうものではない。