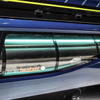物流の脱炭素化と中長期的なカーボンニュートラルに積極的に取組むトラックOEMといえば三菱ふそう。「ジャパンモビリティショー2025」では、カール・デッペン代表取締役社長・CEOがキーノート・スピーチを行い、三菱ふそうが掲げる「フューチャー・トゥギャザー」のモットーとは、顧客やドライバー、そして社会全体とのパートナーシップやコラボレーションを通じて、将来の課題に対し、ともに前進するための革新技術とソリューションであることを強調した。
その一例が、日本初のEV小型トラック『eキャンター』だ。2年前から発売されているが、今回はスマートボディとデジタルソリューションを融合した「コボディ(コネクテッド・ロード・ボディの略)」というテクノロジーが組み合わされている。

まず荷台は、荷下ろし作業をするドライバーのエルゴノミーを中心とするスマート設計となっている。加えてAIで最適な配送ルートを自動的に計画する「ワイズ・システム」と連携しており、短距離の配送ドライバーの作業時間短縮や負担軽減、配送効率の向上を図る。つまりゼロエミッションというだけでなく、配送ドライバーの仕事をもスマート化するトラックという訳だ。