パイオニアは、カロッツェリアのフラッグシップモデル「サイバーナビ」に「AR HUD ユニット」を搭載した「AVIC-VH99HUD」「AVIC-ZH99HUD」の2機種を今月下旬に発売する。
同モデルに搭載されたAR HUD(ヘッドアップディスプレイ)ユニットは、運転中の視線移動を少なくするほか、実際に運転する風景にルート表示を重ね合わせることで直感的な道案内を実現した。
今後、HUDユニット単独でカーナビとして機能するものや、スマートフォンとの連携で車載向けに最適な形で情報を提供するといった利用法も想像でき、車載ディスプレイにイノベーションを与える可能性あるデバイスだ。
AR HUD開発を担当した、パイオニアの橋田雅也氏(カー事業戦略部スマート・ビジョン事業開発室)と古賀哲郎氏(カー事業戦略部スマート・ビジョン事業開発室)に話を聞いた。
◆スマートフォン時代到来を見据えたプロジェクト
----:2011年のCEATECで公開されたAR HUDが、フラッグシップモデル「サイバーナビ」に搭載され発売を迎えようとしています。カーナビゲーションの世界に新たな価値を生み出すものとして、市場でも大きな関心をもって迎えられていますが、HUDの開発に至った背景についてまずお聞かせください。
橋田:約3年ぐらい前になりますが、市販のカーステレオやカーナビゲーション市場が成熟しコモディティ化している中で、次なる成長戦略を考えなければならないということで、新しいプロジェクトを発足しました。
その当時、スマートフォンが世界中で盛り上がる兆しを見せていましたので、スマートデバイスに対する新しい戦略を考えていくというのがまず1つ。車載ディスプレイの市場で新しくイノベーションを起こしていくというのが2つめ。そして、必ず到来するである電気自動車(EV)の市場に積極的に関わっていくというのが3つめです。
----:いずれもIT/自動車業界の次なるトレンドを予見して、商品を投入しようという戦略ですね。その3つの柱の1つが実際の商品として形となったのが、今回のAR HUDなのでしょうか。
橋田:はい。HUDで目指したのは、「地図を理解しなくても目的地に着けるカーナビを実現したい」、そして「映画に出てくるような未来の世界観を実現したい」という強い思いがありました。
----:そのパッションがAR HUDとして業界初のアイディアとして具現化した、と。
◆徹底して磨き上げてきた位置精度がなければAR HUDは実現しなかった
----:HUDに関しては、これまでも自動車メーカーが採用してきた例はいくつかありますが、市販のカーナビゲーション製品で実現するにあたって苦労したのはどのような点ですか。
橋田:前例や基準がありませんので、医学的見地からのアドバイスと開発側での検証の積み重ねという2つのアプローチを取りました。医学的見地では、大学の研究者からのアドバイスをもとに、焦点を合わせる時間や視点を動かす時間を考慮して表示を調整しました。開発側でも実走を繰り返しおこない、HUDの設置場所やドライバーからの焦点距離の最適値を設定しました。
----:投影される映像の焦点距離はどれくらいなのですか。
橋田:3mです。HUD自体は、1980年ぐらいから自動車に採用され、航空機ではもっと以前からありますが、航空機は速度も速く障害物もないので焦点距離は無限に設定できます。クルマの場合だと前方車両の向こう側に映像を映してしまう違和感を感じたり、歩行者が前を通ったりしますので、バンパー付近に映像を映し出すような今の距離がベストと考えています。
----:AR HUDを使っていると、解像度の高く発色の豊かなRGBレーザーと相まって交差点の右左折の場所に立つ旗があたかも実際にそこにあるようなリアルさを感じます。HUDを下支えしている技術的なポイントはどのような点にあるのでしょう。
橋田:自車位置の正確な検出とルート案内の精度、この2点はAR HUDに不可欠な要素です。ARナビでは見ている風景と案内表示の位置がずれると危険ですよね。私はサイバーナビ初代の時からソフトフェアで位置精度を担当していたのですが、とある媒体で位置精度を比較する企画があり最下位だったんですね。その頃カーナビの基本性能である位置精度をなんとかしないといけないということで、プロジェクトが立ち上がり、様々な取り組みの結果、ほどなくして「位置精度ならカロッツェリア」とまで言われるようになりました。
----:そうしたチューニングとノウハウの結晶がAR HUDを実現に結びつけたのですね。
橋田:位置精度もある程度までいけば“道案内に必要ないよ”と言われていたのですが、それでも精度にこだわり取り組んだことが、ようやく昨年サイバーナビで実現したARナビゲーションや、今年のAR HUDという高い位置精度が求められる機能が登場したことで花咲いたと感じています。
◆デザイン性と小型化を実現したレーザー技術
----:今回、AR HUDユニットはサンバイザーの部分に固定する方式をとりましたが、製品化にあたって、ハード面でこだわった部分は。
古賀:デザインですね。車内で圧迫感のないようなデザインを心がけました。できるだけ、薄く小さく、カラーも内装に合わせたを採用しています。特に気を配ったのはアーム部分ですね。
橋田:実はあのアーム、開発陣やデザイナーが非常に苦労してつくったパーツなんですよ。
古賀:アームが太いと車内では非常に違和感があるので、細く違和感のないように仕上げています。細くするとしても強度が必要なので、素材や構造にも非常にこだわった部分です。
----:RGBレーザーを投影するスクリーンが曲面で仕上げられているのも、デザインなのでしょうか?
橋田:ディスプレイ部に関しては、像を大きくするのと遠くに見せるためにカービングさせています。
----:光源にRGBレーザーを採用した理由は?
古賀:我々がやりたかったARの世界観を実現するために、フルカラー・高精細・高輝度・高コントラストの特徴を有するレーザーを光源として採用しました。また、レーザーを採用することで本体の小型化にも寄与し、このような圧迫感のないデザインを実現することができました。
----:RGBレーザーの技術はパイオニアで開発したものなのですか。
古賀:当社はレーザーディスクからブルーレイという、長年にわたるレーザーのモジュール化技術を持っていたので、ほかの製品に転用できないかと考えたところに、ちょうどヘッドアップディスプレイに搭載する話がでてきました。
----:AR HUDとナビ本体はBluetoothで無線通信していますが、有線あるいはWi-Fiという選択肢はなかったのでしょうか。
橋田:もちろん通信方式はさまざまに検討しました。ただHUDに映像自体を送っているものでなく、必要最低限のデータを送ってHUD内で再描画しているので、無線部分で大容量のデータ伝送を必要としなかったということです。
◆車載ディスプレイにイノベーションを
----:製品を発表してから、テレビなどでも大々的に取り上げられていましたが反響の大きさについて実感する部分はありますか?
橋田:これまで経験したことがないような、いろんな反応があって驚いています。我々も製品を発表して“危ないのではないか”といった批判がくるのかと想像しましたが、ソーシャルメディアの反応や銀座のショールームなどアンケートをみると、ポジティブな意見が多い印象ですね。
----:CEATECでの展示ではスマートフォンとの連携を提案していましたが、今回はサイバーナビとの組み合わせで製品化が実現しました。サイバーナビで展開する狙いというものがあるのでしょうか?
橋田:サイバーナビのユーザー層は本当にクルマや新しいもの好きな人が多く、HUDを普及させるうえで一番マッチすると考え、その層に向けてまずは市場を作っていきたいと思っています。AR HUDは、これまで取り組んできた位置精度の追求やルート品質、そしてレーザーモジュールなどパイオニアの技術の集大成です。ただ“凄い”だけでなく、一旦HUDに慣れてしまうとナビ画面を見なくてよいため実用面でも価値があると考えています。多くの方に体験し価値を体感していただきたいと思います。
《聞き手 北島友和》



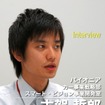







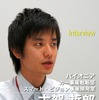














![最新機種の“魅力”を解剖! ナビ力もエンタメ力も随一、孤高のハイエンド機『サイバーナビ』![メインユニット最前線]](/imgs/sq_l1/2165105.jpg)
![サイバーナビDSP活用術 愛車アクアが劇的に変わる音作り[Pro Shop インストール・レビュー]by AUDIO.VISUAL.SECURITY FIST 後編](/imgs/sq_m_l1/2126807.jpg)












