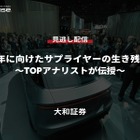11月中旬、中国・上海は珠海国際サーキットで行われた「ZF Next Generation Mobility Days(ZFネクスト・ジェネレーション・モビリティ・デイズ)」に参加し、同グループの最新テクノロジーを試乗を通じて経験することができた。
ただしこの催しはZFグループの新たな技術的成果、つまり具体的な新製品を試すだけに終わらなかった。中国はアジア・パシフィックのグループ本社というだけでなく、14か所の拠点を置いている。長期的戦略の中で将来的な世界最大の自動車市場と捉え、長年にわたって継続的なコミットメントを続けており、生産施設やサービスはもちろんR&Dの体制についても積極的に現地化を進めてきた。2019年には2億2000万ユーロ、22年には3億8000万ユーロまで投資額を伸ばし、それに伴い中国市場での売上も約1.5倍に成長しているという。よって今回のデモンストレーションで示された技術の中には、少なからず中国拠点のイニシアチブによる開発もしくは関与によって進められており、17台が用意された試乗車の中にも少なからず中国製EVが含まれていた。
かように中国のOEMが牽引するEV市場の伸長は大きなトレンドになっている中で、北アジア地域において日本のOME各社の技術開発の動向と市場は欠かすことのできない位置を占めており、ZFはOEMとの協業による開発体制を強めている局面にあることを、取材に応じた同グループの取締役、シュテファン・フォン・シュックマン氏は強調した。
◆ビークル・ダイナミクスと自動運転、需要と普及の見通しは?
「パワートレインの電動化」「SDVと動的制御」そして「自動運転」が今、ZFのとくに注力する3つの領域といえる。前二者についてはセンシングのためのデバイスからシステム統合化、機能ソフトウェアの開発やデータマネージメントまで、包括的に手がけられるところが強みで、SDVについては室内エンターテイメントのみならず、「Xバイ・ワイヤ」技術と総合ソフトウェアによってビークル・ダイナミクス制御そのものを包括している。その先の自動運転については、乗用車でいう現在のレベル2+以上から先へ、商用車についてはレベル4に向けて開発を進めているという。
ただし全体の基調講演の中で、フォン・シュックマン取締役は自動運転テクノロジーが製品化されていく見通しが、当初よりやや遅れていることも明らかにしている。それがどういった理由に起因するものか尋ねてみたところ、ZFジャパンの代表取締役、多田直純氏は現状を次のように見立てている。
「自動運転に対する成熟度がまだ上がっていないというところです。今はそれ以上に、中国市場が自動車自体の価値を自動運転以外のところに求めています。とはいえ、それは電動化と矛盾するところではなく、SDVの価値が伸びていることと軌を同じくする点でもあり、そちらが先行して自動運転は後に来るのではないか、ということです。自動運転というとSDVの完成形のように捉えられますが、そうでもないんです。我々のCubiX(キュービックス)のような、ソフトウェアでビークル・ダイナミクスを操るプロダクト群は、電動化の早い段階から求められてきました。今は機械だけを売るということではなくて、そうしたソフトウェアによって付加価値の高い車を中国OEMが作ることにシフトしているんですね。その中でビークル・ダイナミクスに対する理解度を深めつつ、我々もそうですが高い収益率を確保しているのが現状、と見ております」
自動運転の成熟度とは、技術面のみならず法制や市場の受け入れ体制についてもいえることであり、フォン・シュックマン取締役が付け加えて、次のような見通しを述べた。
「我々は現状、乗用車の自動運転もそうですが、商用車の自動運転にも注力しております。開発スローガンとして乗用車の方はアフォーダビリティ、つまり手の届くものにすることを心がけていますが、商用車のビジネス・ケースは異なると考えています。商業的な領域で自動化というソリューションを購入することですから、用途として足りること、すぐに実装できることが大事で、いざ普及していく際のスピードも商用車の方が速いと思われます」

同じく、日本の多田代表取締役の自動運転に対するスタンスも次のようなものだ。
「日本の直近でいえば、物流の2024年問題が懸念されている通り、物流の効率化を考える局面ですよね。ですから商用車の方がハブ・トゥ・ハブのような範囲だけでも、自動運転化テクノロジーが早く投入されるべき、優先的な課題であろうという認識です」
いわばZFのようなティア1がにとって電動化からSDV、自動運転といったテクノロジーの将来的な需要は変わらず高いものの、運転の乗り味やエンターテイメント性を嗜好的価値として付加すべきハイエンドな乗用車と、実需をベースとする効率化の要請から拡大するであろう商用車では、コアとなるテクノロジーは同じでも用途やアウトプットとして求められるものが異なるのが現状というのだ。それらの点を踏まえた上で今回、「Xバイ・ワイヤ」技術を搭載したものを中心とする試乗用のデモカーに乗った印象をふり返ると、SDVがもたらす革新や変革の輪郭がおぼろげに見えてくる。
◆統合制御ソフトウェア「キュービックス」の実力を試す
まず最初に乗り込んだのは、日本でも2024年半ばにデリバリーが始まるであろうロータス『エレトレ』。これはソフトウェアによるビークル・ダイナミクスの統合制御ソフトウェアである「CubiX」を搭載した車両で、インテリジェント化されたシャシーを構成するメカニズムとしては、IBC(インテグレーテッド・ブレーキ・コントロール)、ベルトドライブ式のEPS(電動パワーステアリング)、CDC(コンティニュアス・ダンピング・コントロール)、そして前後車軸に800VのPSMモーターを組み込んだ4WDにして4WSだ。

そもそも5.1mを超える全長に2.5トンもの巨体が、ドライバーの頭をヘッドレストに押しつけるほどに軽々と加速していくフィールに、驚く。試乗はフルコースでこそなかったが、珠海サーキットの特徴的なレイアウト、「上」の字の1画目にあたる第1コーナーは、奥に行くほど右巻きのRが小さくなっていき、周り込んでから左へ切り返すという、難しい複合コーナーだ。にもかかわらず、低重心で安定したロール姿勢が持続する粘り強い接地感覚が保たれ、切り増しから切り返しまで回頭性が軽い。ロータスらしいハンドリングの自在さが見事に再現されていることに舌を巻いた。助手席に乗り込んだエンジニア氏は32歳という若さで、パラメーター設定を今度は弱US(アンダーステア)からOS(オーバーステア)寄りに変更した。続くコーナーで、左右に急激に車体を揺すってみろ、という。すると第1コーナーで見せたスタビリティとは対照的に、リアが緩やかにブレークして、一瞬テールスライドするが、車の方が瞬時に駆動力を抜いて安定姿勢に戻る。
「ZFのアドバンテージは、ビークル・モーション・コントロールにおける蓄積ノウハウが多大にあるから、ソフトウェア制御の上で、前もって予測シナリオを立てられること。予測の幅広さも精度も高い、ということです」と、キャリア当初からビークル・ダイナミクスを専門にしてきたという若い中国人エンジニア氏は、目を輝かせる。エレトレは中国のジーリー(吉利汽車)主導で開発されたとされるスポーツSUVだが、キュービックスのフレームワークは、駆動やパワートレインのみならず、サスペンションの制御システムやロール制御、クラウド・インターフェイスといったシャシー側の要件や構成要素に応じて、モジュラー設計が可能だ。もちろんそこには安全性デバイスも含まれれば、OEMごとに機能要件を入れ込むことも可能という。安全性の例としては、70km/hぐらいで走行時に片側2輪だけスキッドプレートに載せてフルブレーキしても、4輪それぞれに制動力を独立制御することで、車両を直進状態の姿勢に保とうとする。また50~60km/hでのダブルレーンチェンジのために、ステアリングを急激に右左、次は左右、といった風に切り返しても、リアの挙動が追従方向に保たれ、元のレーンに安定して復帰することができた。Uターンのような低速走行の局面なら、後輪側の操舵を前輪側と逆位相にして小回りを利かせるのがセオリーだが、低速とも高速ともいえない中速域で、同位相か逆位相かギクシャクせずに判断するのが、成熟度の高さを示す好例と感じられた。
◆シャシー制御の幅広さ、懐の深さを実感
以上はパッシブもしくはセミアクティブ、つまりドライバーの操作という入力を受けてからコントロールする制御だが、キュービックスのアクティブ制御サンプルを、続く試乗車で体験することになった。それが東風モータースの『Mengshi(猛士)917』だ。リアル軍用車というよりはラグジュアリーなフルサイズSUVのEVで、各輪を268psの各モーターで駆動し、東風モータースによれば、出力総計は1084psを謳っている。バッテリーは147kWhにも及ぶ巨大容量ゆえ、3トンを超える車重で、最大航続距離は505kmと公称されている。