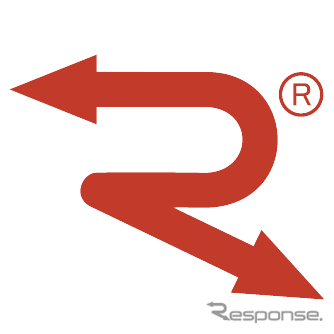中国の自動車メーカー、BYDの日本法人ビーワイディージャパン(略称BYDジャパン)は、子会社のBYD Auto Japanを通じて乗用車を日本に導入すると発表。そこでBYD Auto Japan代表にその意図や展開について話を聞いた。
◆3年前とは比較にならない完成度
----:これまでBYDは商用系、例えば日本でシェア7割を誇るEVバスを導入するなどの活動を行ってきましたが、今回なぜ、フルEVの乗用車を2023年1月から日本導入することを決定したのでしょうか。
 BYD Auto Japan代表取締役社長の東福寺厚樹氏
BYD Auto Japan代表取締役社長の東福寺厚樹氏BYD Auto Japan代表取締役社長の東福寺厚樹氏(以下敬称略):参入発表そのものは5月から6月で出来ないかと検討してきた結果としていまになってしまいましたが、当初から23年1月から販売開始したいと考えていました。そこから逆算して考えると、どう考えても5月ぐらいには発表して、そこから一気に販売体制を作っていかないと間に合わないということです。日本ではブランドとして全く認知されていませんので、お客様に買っていただくレベルにまで認知度を上げるというと、それなりに時間がかかるのです。ただ、クルマの準備の問題や、6月に『シール』を発表するなどがあり少し遅れてこのタイミングになりました。
 BYD シール
BYD シール
当初導入予定は2モデルで、『ドルフィン』と『アット3』を23年に順次投入していく計画でした。順番はドルフィンが実は先だったんです。今回の車種は全てeプラットフォーム3.0を採用していますので、ブレードバッテリーも当然搭載された、いわゆるグローバル戦略車ですので、日本でもこの選択になりました。スペック的にも、各国の認証を取得する上でも十分なクルマに仕上がっていますので、どこの国にでも出せる準備が出来た結果といっていいでしょう。
 BYD ドルフィン
BYD ドルフィン BYD アット3
BYD アット3----:実際に見せていただきましたけど、品質感は非常に高いですね。
東福寺:実は走りに関してもそうなんです。ブレードバッテリーしかりなんですが、あれだけの性能のものをバッテリーパックごと車体にちゃんと組み込んだ結果、ものすごく剛性感が高いんです。私は前職で、あるインポーターにいたのですが、そのメーカーもすごく車体剛性にこだわって作っていました。そこと比較しても全く同じレベルか、もしかしたらちょっと低重心な分だけ乗り味の面で、高級感が1枚上の雰囲気が出てると感じています。走らせてみると足回りがあまりバタつかないんですね。そういったチューニングも元メルセデスベンツでチューニングスペシャリストだった方が、全部のクルマのチューニングをやっている結果でしょう。
因みにインテリアデザイナーは元メルセデスベンツで『Sクラス』や『マイバッハ』を担当したデザイナーです。そして、デザインのトップは元アウディのチーフデザイナーだったヴォルフガング・エッガー氏なんですね。このように欧州ブランドの超一流どころがみんなで寄ってたかってやっています。それはデザインだけではなくて、先程申し上げたようにクルマとして完成させる上でのNVHの部分や車体剛性、路面の追従性をはじめとしたあらゆるところに“一番すごい技術者”が関わっていることから、クルマとしての基本性能がものすごく上がったのではないかと思います。
 BYD アット3
BYD アット3私もこの会社に入る前(東福寺氏は昨年8月に入社)にBYDのことをどれだけ知っていたかというと、ほとんど知らなかったんですが、劉社長(ビーワイディージャパン代表取締役社長の劉学亮氏)がいうには、3年前のBYDのクルマと今日のクルマを比べると全然違っているというぐらいに激しく良くなっているみたいです。
このReady to goというモードになった1番大きなきっかけは、多分ブレードバッテリーの非常に高い性能が担保出来たことでしょう。そこからさらに量産も出来るようになったことから新型車がどんどん開発され、それらが全部ブレードバッテリーに置き換わっていっている。その生産体制や、研究開発も含めてメーカーとしての実力が上がった結果、商品そのものに対して自信をもってお勧め出来る状態になったのが1つ大きな理由として挙げられます。
 BYD eプラットフォーム3.0
BYD eプラットフォーム3.0それと、日本は2035年を目指して新車の販売を電動化するという目標が大きなトリガーになっているとは思います。そこにプラスして劉社長がプレゼンテーションでもお話したとおり、“コロナ禍前にいろいろな人が(本社に)来て、これだけのものをどうして日本に持ってこないんだ”というような話を多く聞いていたのです。そこでリサーチを掛けたり、『E6』を日本でも実験的にタクシー会社で使っていただいたり、大手のエネルギー産業の会社で業務車として使っていただいたりしてきました。もちろん右ハンドルで、ウィンカーレバーも右側に付けた車両としてです。そこからのフィードバックや、日本での使用環境もだいぶデータとしては取れましたので、それを最新のプラットフォームの量産車で日本仕様化していけばうまくいくのではないかと決断した。そこで今回は型式認定を取得して、並行車両ではない初めての中国ブランドとして参入が出来る体制が整ったのです。
◆EVオンリーでの導入は2つの理由で
----:本国などでのBYDのラインナップを見ると、プラグインハイブリッドモデルもありますが、あえて日本市場においては3モデルともフルEVとなりました。この意図は何でしょう。
東福寺:確かにその議論はありましたが、フルEVにした大きな理由は2つあります。まず1つは、中国ほどプラグインハイブリッドが日本のマーケットで浸透していないことがあります。これはトヨタのハイブリッドが世の中に行きわたっていますので、あえてプラグインというところにメリットを感じるお客様があまりいらっしゃらない。それであればEV1本に絞った方が潔いということです。
そしてもう1つはディーラーさんで売っていただく上で、プラグインハイブリッドを入れると、結局既存のガソリン車を扱ってるのと同じ設備や機器類が必要になってくるんですね。補用部品もそうなんですけど、油脂類もやりながら、そこに加えてバッテリー関係もやらなければいけない。本当に二股になってしまいます。
いままでの既存ビジネスであれば、徐々にEVに変化していくという切り替えをやっていけるんですが、いきなりゼロスタートでEVとガソリンの両方やってくださいといったら、それこそいままでやっているのとほぼ同じ規模感が最初に必要です。さらにしばらくはアフターサービスの収入(車検整備など)が見込めないわけですから、これはやる方としても相当辛いです。しかしEVのみにすれば排ガスが出ませんので、例えば床さえしっかりしてればショッピングセンターの中にちょっとしたお店を作っていただいて、その中で動かす分にも全く汚染物質は出ませんよね。そういうお店側の事情も考えました。いずれは全部EVに切り替わるでしょうし、バッテリー性能も上がっていけばプラグインでカバーしてる1000kmという航続も十分可能になるでしょう。因みにいま、バッテリーだけで1000kmは技術的には可能な段階に来ています。ですから5年10年経った時に、やはり(プラグインハイブリッドは)入れないで良かったねという話になるでしょう。そこで最初からやめようという話になりました。