今やDSPを使ったサウンドチューニングはカーオーディオでは必須となっている。さまざまなノウハウが蓄積される中、プロショップのMST代表である小川さんが、DSPのパフォーマンスをフルに発揮させるプロの調整テクニックについて開示してくれたので、話を聞いた。
◆MSTの最新設備と“プロ視点”で見るDSP調整の要点
広大なピットスペースや塗装ブース、木工スペースなど、充実した作業環境を整えるMST。東京都にあるこのオーディオプロショップは3Dプリンターや3Dスキャナーを活用したインストールや加工など、最新機器を用いたオーディオインストールにも長けている。
そんなMSTの代表である小川さんから最新のDSP調整の勘所について、プロのインストーラーが普段調整していて感じているポイントについて紹介してもらうべく、取材に出かけた。
ここからの話はあくまでもプロのインストーラーがDSPを用いてサウンドチューニングをする際の話であり、一般ユーザーがDIYで調整する際のハウツーではないので、承知の上で読んでほしい。テーマは大きく分けて3つ、(1)DSPの処理能力について、(2)DSPの処理能力・リソースには限りがあること、(3)あらためてアナログ面(取り付け)が重視される、について話が及んだ。
◆高性能DSPの“音の完成度”と作業効率
まず(1)のDSPの処理能力についてから話はスタートした。「カーオーディオの世界にDSPが登場した頃には、DSPで処理したサウンドは“デジタルっぽい”などと言われていました。しかし近年の高品質なDSPは、それを感じさせない音の完成度になっています」。
「年々進化を続けるDSPは、安価なモデルから高価なハイスペックモデルまでさまざまなグレードがあります。実際に調整して音を出していると、その違いは歴然です。細かな音のニュアンスを表現できるのがハイスペックなDSPです。レベルの高いサウンドを求めるなら、処理能力の高いDSPを用いることが求められます」
さらに、インストーラーが調整作業をする際の手順でもDSPの能力差が出るという。「設定をして音が鳴るまでにわずかなタイムラグがあります。DSPの内部で入力した数値を設定する時間が必要だからです」。
「これがモデルによって、コンマ数秒違います。比較して聴き比べる作業も含め、インストーラーにとってはタイムラグが少ないほうが調整の精度が上がります。その点でも、最新かつハイスペックなDSPは完成した音が良い傾向になります」
◆リソースを食うのは“やりすぎ調整”優先はタイムアライメント
次の(2)のDSPの処理能力・リソースの話も、日常的に数多くのDSP調整を行っているプロらしい興味深いものとなった。
「DSPはデジタル音声信号を内部で処理していますが、多くの処理を重ねると処理能力が限界に近づきます。例えば、タイムアライメントやイコライザーを使う際に、大きく調整(調整箇所や調整幅)するとDSPの処理能力を消費します。音声データの読み込み→DSP処理→出力の過程で負荷が高すぎると、処理能力が不足するケースが出てきます。その結果、タイムアライメントの設定が不安定になることもあります」
「そこで私は、タイムアライメントを優先し、なるべくイコライザーを大きく調整しないことで負荷を低減させ、全体の処理をスムーズに進めるよう心がけています。先に紹介した処理能力の高いDSPを使えば、その許容範囲は高くなります。古いDSPを使うと、音の揺らぎが出ることもありますが、これも負荷に対する処理能力の不足だと感じています」
◆アナログ面を仕上げて“DSPの仕事”を軽くする
ここまでの処理能力の話を受けて、小川さんが近年特に力を入れているのが(3)のアナログ面の充実だという。「なるべくDSPに負担をかけないで、狙ったサウンドを引き出すために、取り付けがあらためてクローズアップされています。バッフル、背圧の処理、スピーカーロケーション、ケーブルなど、取り付けの精度を上げてDSP調整を減らし、負荷を下げます」。
「DSPでさまざまな調整を実施していると、“本来は物理的に対処すべき”ポイントが見えてきます。そこを逆算してあらかじめ取り付け時に処理しておくことで、DSPの調整を最小限にできます。そうすれば、その分の処理能力を、DSPでしかできない処理に割り振ることが可能です」
このようにDSPは何でもデジタルで調整できる魔法の機器ではなく、インストーラーがうまく使いこなすことが大切だ。プロのインストーラーが現場で日々感じていることでもあるので、そのリアルさが伝わってくる。これらの情報を知った上でDSP選びやインストールの計画を進めれば、より高音質な愛車を完成させることができるだろう。
土田康弘|ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。















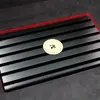

![動画を観たい場合の“裏ワザ”公開! 特にトヨタ車オーナーは要チェック[クルマで音楽は何で聴く?]](/imgs/sq_l1/2185876.jpg)
![プロは、スピーカーの“仕事の仕方”も制御する![イン・カー・リスニング学…プロショップ編]](/imgs/sq_m_l1/2185542.jpg)
![10数年ぶり復帰! アバルト695Cが“もう一度”火をつけた[car audio newcomer]by サウンドステーション クァンタム 前編](/imgs/sq_m_l1/2185368.jpg)


