タイヤはホイールに組み合わせて使うものだが、このタイヤの幅とホイールのリム幅の組み合わせにはさまざまなセッティングがある。ホイールのリム幅に対してタイヤの幅はひとつだけではなく、使えるサイズには一定の許容範囲がある。
その中でどのような組み合わせにすると良いのだろうか。実はタイヤ幅とホイールのリム幅の組み合わせは奥が深いのだ。
◆リム幅「J」とインチ換算の基礎
ホイールはその直径が17インチや18インチで示されるが、リム幅は7.0J、8.5Jのような数値で示される。Jというのはホイールのフランジ形状の規格のことで、その前の数字はインチでの幅を示す。1インチは25.4ミリなので、7.0Jのホイールはリム幅が177.8ミリであり、8.5Jのホイールは215.9ミリとなる。
タイヤメーカーはこのタイヤの幅に対応する適正なリム幅を示している。例えばADVAN「NEOVA」(アドバン・ネオバ)の265/35R18サイズの場合、標準リム幅は9.5Jだが、許容リム幅は9.0~10.5Jまでとなっている。つまり、9.5Jのホイールと組み合わせて使うのが標準であるが、9.0Jから10.5Jのホイールまで組み合わせて使っても良いということである。
◆「引っ張りタイヤ」とは何か
ここで出てくるワードが「引っ張りタイヤ」というもの。これはタイヤ幅に対して広いリム幅のホイールを組み合わせることでタイヤを左右に引っ張って使うことからそう呼ばれている。
引っ張りタイヤはタイヤのサイドウォールが垂直ではなく斜めになる。それによってサイドウォールが潰れにくくなり、ステアリング操作に対する剛性が高まる。具体的にはステアリング操作に対してクルマがクイックに反応しやすくなる。
そういった利点から、80年代から90年代にかけてはスポーツタイヤでサーキットを走るのであれば、引っ張りタイヤにするのが常識だった。広めのリム幅にやや細めのタイヤを履かせて、サイドウォールを引っ張ることで剛性を上げる狙いだったのだ。しかし、今のトレンドは変化している。近年のスポーツタイヤは極めてサイドウォールの剛性が高いため、必要十分な剛性があっても、引っ張りタイヤにするとサイドウォールの剛性が高すぎてタイヤをうまく使えなくなる。
また、タイヤが設計通りに潰れてくれないため、本来のグリップを発揮できなくなる。以前はサーキットでのタイムアタックでも引っ張りタイヤを使っているユーザーが多く見られた時期もあったが、現在はほぼいないといって良い。タイヤ本来のパフォーマンスを発揮するのであれば、標準リム幅のホイールを組み合わせるのが最もバランスが良い。
◆スタイルと実用の狭間で、許容リム幅内の応用例
とはいえ、許容範囲の中であれば使っても問題はなく、あえて引っ張りタイヤにするという手もある。
特にスタイル重視でタイヤとホイールをツライチにしている場合、タイヤのサイドウォールがフェンダーに当たりやすいことがある。そういった場合はタイヤを引っ張ることでサイドウォールが斜めになり、フェンダーとの干渉を避けやすくなる。ギリギリのサイズ設定のタイヤとホイールを装着することができるのだ。
FF車では前後同じタイヤ幅だが、フロントのホイールは0.5J広いものを使うことで、ややステアリング操作に対するレスポンスを高め、リアタイヤは標準幅で使うことで乗り心地を向上させ、リアのストローク感を出すセッティングもある。そういう意味で許容リム幅内で、あえてホイールサイズを変えて、同じサイズのタイヤを履くというセッティングもある。タイヤはゴムで動きやすいだけに、どのように動かすかで乗り心地もハンドリングも見た目にも変わってくるパーツなのだ。

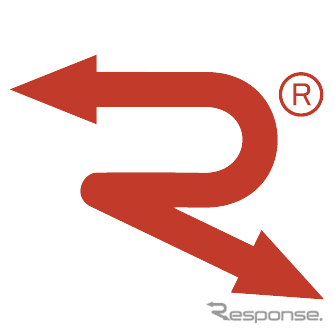






![裏ワザ! スマホをプレーヤーとするときの接続法[クルマで音楽は何で聴く?]](/imgs/sq_m_l1/2182234.jpg)