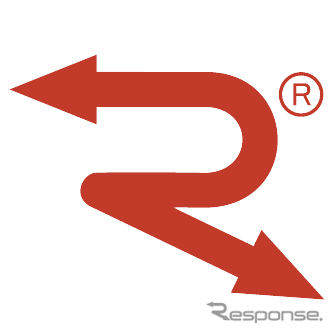軽自動車のラインナップ刷新に取り組んでいるホンダ。「普通乗用車からのダウンサイジングユーザーの受け皿となれるクルマ作りを目指した」(開発責任者・浅木泰昭氏)というが新世代モデルとして昨年11月に発売した軽セダンの『N-ONE(エヌワン)』。を330kmほどテストドライブする機会があったので、レポートをお届けする。
試乗車はN-ONEのなかでは中間的な立ち位置の「ツアラー Lパッケージ」FWD(前輪駆動)。トルクに余裕のあるターボエンジンを搭載し、足回りも性能が高められている一方、内外装は上級グレードのプレミアムに比べると比較的簡素な仕立てのもの。試乗コースは東京都葛飾区をスタートし、千葉県の犬吠埼、南房総の勝浦を巡って帰着するというもので、行程は331.6kmだった。
まずは乗り心地、安定性、静粛性などの動的な質感について。基本的に足回りのセッティングは固めで、速度域の低い市街地では道路の細かい荒れを拾う。衝撃は角の立ったものではなく、ダンピングの効いた緩衝材を通したようなもので、不快感を覚えるほどではないが、低速での振動吸収性自体はトップランナーというほどではない。
交通の流れがやや速い郊外の一般道はN-ONEの得意とするステージ。低速ではやや固かった乗り心地は、速度レンジが上がるにつれて滑らかさになっていき、印象が劇的に好転する。特筆すべきは、急カーブなどに設置されているゼブラ型の滑り止め舗装を乗り越えるときや舗装が荒れ気味の部分を走行するときのフィーリングで、ブルブルというゴムの振動感が残らない。
最近は軽自動車やコンパクトカーの商品力が全般的に上がり、一発の入力なら上手くいなすモデルも増えた。が、連続する入力をうまく減衰させるセッティングは、サスペンションのストロークが限られていたり、コストの制約が厳しかったりといった要因もあってなかなかうまくいかない傾向がある。
N-ONEの高速側のサスセッティングはそれら軽自動車やコンパクトカーのなかでは白眉とも言えるレベルで、同じく高速寄りのチューニングがなされているフォルクスワーゲン『ポロ』やアウディ『A1』などと比べても遜色ないように思われた。ミニマム・プレミアムを名乗るのに十分な資質を持っているといえる。
軽自動車にとっては苦手科目である高速巡航時も、郊外道路で見せた乗り心地や操縦安定性の良さは失われない。振動やロードノイズの遮断も非常にうまくいっており、軽自動車とは思えないスムーズなクルージングが可能である。ただし、大きめのうねりが連続する箇所では軽自動車サイズという物理的制約が影響してか、前後方向のピッチングが普通車に比べて少し大きめに出る。
ロングドライブ中、印象に残ったのがシート設計の良さ。フロントシートの座面は普通車に比べて短めだが、体圧分散が優れているためか腰のすわりが非常に良く、320km程度のツーリングでは臀部のうっ血感や腰の疲労などはほとんどなかった。また、N-ONEの外観上の特色である丸目ランプ上のフェンダーの盛り上がりは運転席からも見える。ボンネットが視界に入ることから、直進時の方向感の定まりが良く、これも疲労軽減に一役買っているものと推測される。
車体剛性は非常に高く、路面の大きなギャップを乗り越えるといった大入力にも余裕で耐える。設計を改善したほうがいいと思われたのはヘッドランプのたてつけ。夜間、ヘッドランプを点けて走行しているときに不整路やギャップを通過したさいに、衝撃で光軸が微妙に振動するのが容易に視認できた。根本的な問題ではないが、質感を重視するなら直しておきたいポイントだ。
また、燃料タンクを前席下に置くセンタータンクレイアウトを採用したためか、前席のスライド幅がやや小さい。座面を上げて眺め良く運転したい場合、身長約170cmの筆者が座る場合でも最後端まで下げる必要があった。身長の高いドライバーの場合、着座位置を低くして運転する必要があろう。もっともそれは、ホンダが本来想定している着座姿勢なのであろうが。
トータルでみて、N-ONEは市街地を低速で走り回るさいは普通だが、ロングツーリングになると一転、操縦性や快適性の高さ、疲労の少なさなどが際立つ、グランドツーリング型の軽自動車と評することができる。
ただし、これはターボモデルや上位グレードのプレミアムなど、フロントサスペンションにスタビライザーを装備するモデルに限った話で、デビュー直後に試乗したスタビライザーなしのベースモデルはクオリティ感が一段落ちる。ロール剛性を高めるために、スタビライザーありのモデルより固いスプリングが使われているのが原因とみられる。これは先行デビューした『N BOX』も同様である。
新世代シャーシの優れた性能を生かして、ある程度ロールを許してでも柔らかくセッティングするか、さもなくば全グレードともスタビライザー装備のサスペンションに統一したほうが、よりミニマム・プレミアムらしさが出るのにと思われた。