「多目的e-Cargo」は、低重心で積載能力の高い電動3輪自転車だ。作ったのは、世界シェアNo.1のチェーンメーカーである椿本チエイン。
ただし、椿本チエインは祖業である自転車用チェーンからは撤退していたという。なぜ、椿本チエインは自転車チェーンに戻るだけでなく、自転車本体まで作ったのか。
◆安定感と積載量の大きさが魅力
「Bicycle-E・Mobility City-Expo 2023(自転車- 電動モビリティまちづくり博)」で大きなスペースをとって展示された「多目的e-Cargo」は、自動車エンジン用タイミングチェーンで世界シェアNo.1の椿本チエイン社が試作中の3輪電動アシスト自転車だ。
運転席の後ろ、2つの後輪の間に自転車としては大きめの積載スペースがあり、大きな荷物でも安定して運搬できる。サドルポストの後部に大きめの枠があって、そこに斜めに寄りかからせる形でかなり長尺の荷物も運べる。絶妙のデザインだが、実はタタメルバイクを設計・製作したICOMA社の生駒社長によるデザインなのだ。
 斜め上から見ると、サドルポストに付けられた枠がよくわかる。長尺モノを自転車で運べたら便利だ。
斜め上から見ると、サドルポストに付けられた枠がよくわかる。長尺モノを自転車で運べたら便利だ。椿本チエインは1917年に自転車チェーンのメーカーとして大阪で操業した。しかし、近年は自転車チェーンは作っていなかった。それがなぜ、自転車チェーンのみならず、電動自転車そのものまで作るに至ったのだろうか?
◆中国メーカーに対していかに特色を出すか
取締役の宮地正樹氏によると、きっかけは自転車メーカーから、自転車チェーン製造の依頼があったことだという。
以下、宮地氏の談話。
実際にやってみると、自転車チェーンの性能を上げるのは非常にハードルが高かったのです。そこで、「これだけのチェーンを開発するのだったら、もうちょっと思い切ったことをやれないか」ということから、椿本チエインの駆動系の技術を世の中に出していきたいとなりました。
現在は中国製の自転車も沢山販売されている。その中で、それに対抗できる特色を出していきたい。ICOMA社といろいろ協力しながら自転車本体の開発に踏み切りました。3輪車にしたのは、(後輪の間の)後ろの空間が多目的に使えていろんな可能性があるんじゃないかということです。
 真横から見た「e-Cargo」コンセプトモデル。デザインはタタメルバイクの生駒氏。
真横から見た「e-Cargo」コンセプトモデル。デザインはタタメルバイクの生駒氏。
しかし、自転車本体開発のノウハウがまったくなかったので、さまざまな外部の知見を取り入れながら、現在も開発を進めています。技術面では、チェーンはもう世の中に出せるレベルですが、チェーンだけでは面白みがない。また3輪車に特有の技術的なハードルがかなりある。安心・安全でかつ乗りやすいものを目指しています。
また、ビジネスモデルもこれから。レンタルや自治体などの市場からスタートさせるのか、あるいはモニタリングという形にして、この自転車をバージョンアップしていくのか。一気に世の中に出すというよりは、段階的に反響を見ながらモデルチェンジして、最終的にはビジネスにしていきたいです。
3輪自転車なので、ナンバープレートも免許も要らないので購入はしやすいと思います。しかも積載量が大きくクーラーボックスなども詰める。家庭なら子供を乗せたいというのもあるでしょう。しかし、それも安全性をきちんと見ていかないと、全てご破算になってしまう。まずは、自社の工場内で使うなどして、改善していきたいです。
◆メイドインジャパンをモットーに
以下は、e-Cargoの開発推進課長の濱口秀史氏に聞いた技術面の課題などについて。
 「e-Cargo」のシンプルな塗装バージョン。ブルーが基調だが、サドルポスト部の白線がアクセントになっている。
「e-Cargo」のシンプルな塗装バージョン。ブルーが基調だが、サドルポスト部の白線がアクセントになっている。e-Cargoの開発を始めて1年くらいです。自転車そのものが判っていなかったので、いろいろ勉強しながら進めてきました。
フレームはアルミフレームを採用し、電動ドライブユニットは日本製のものです。メイドインジャパンということを我々のモットーにしています。このドライブユニットの中には、弊社の部品である「ワンウェイ・クラッチカム」が使われています。自転車のペダルは後ろに回すと空転し、前に漕ぐときだけ機能する。これがワンウェイ・クラッチカムです。
チェーンも今回独自に開発したものです。チェーンは伸びて外れてしまうことが問題ですが、現在のところ従来の3倍以上の耐久性を持たせていて、もっと高みを狙っていこうとしています。
 「e-Cargo」コンセプトモデルの駆動部。チェーンは椿本チエイン自慢の3倍強いオリジナル品。
「e-Cargo」コンセプトモデルの駆動部。チェーンは椿本チエイン自慢の3倍強いオリジナル品。重量は30kgを目指しています。人が持てる限界がそれくらいなので。今後、1、2年をかけて軽量化していきます。
◆安心・安全を旗印に
今回のBicycle-E・Mobility City-Expo 202では、さまざまな分野からeモビリティへの参入が見られた。その中でよく聞く言葉が「安心・安全」だった。パーソナルなeモビリティにおいては、特に安心安全が非常に重要で、椿本チエインがかなり慎重に開発を進めているのも、そこを重視しているからだろう。
 来場者向け記念品の「e-Cargo」のプラモデル(非売品)。
来場者向け記念品の「e-Cargo」のプラモデル(非売品)。 「e-Cargo」コンセプトのパネル表示。
「e-Cargo」コンセプトのパネル表示。









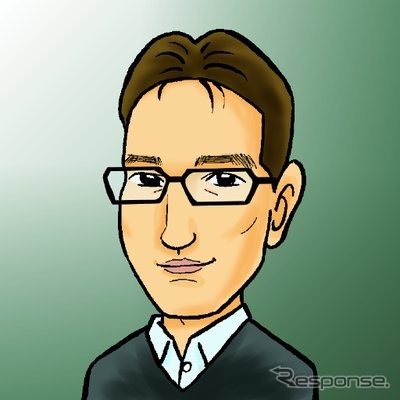




![【収納アイテム特集】「スペースが足りない!」と嘆く『ジムニー』オーナーに朗報! 専用便利品[特選カーアクセサリー名鑑]](/imgs/sq_l1/2183048.jpg)




