環境自動車税、2012年度創設へ
自動車税制に関し、新しい動きがあった。総務省は15日、「自動車関係税制に関する研究会」の報告書を公開。その中で、軽自動車税を廃止して普通乗用車と同じ税体系に組み入れた「環境自動車税」を創設する考えを示したのだ。報告書はpdfファイルとして総務省のホームページに上げられており、誰でも見ることができる。
総務省は来年度にも自動車税制を改正し、2012年度から実施したいという意向を示している。そのスケジュールは非常にタイトであり、今回の報告書はすでに最終案に近いものと言っていいだろう。
この報告書の要点を簡単にまとめると、
1.環境自動車税は現在の自動車税と自動車重量税を一本化した地方税。現在、暫定措置として割増税率が適用されている税額程度を本則税率とする。
2.軽自動車は機能面、安全面、環境負荷など多くの点で普通乗用車とほとんど同じであることから、環境自動車税へ移行する時には同一の税体系とする。
3.現在、営業用自動車と自家用車の税額には大きな差がある(営業用は軽自動車とほとんど同じ税額)が、差をつける合理性はないのでこれも一本化が望ましい。
4.税額はCO2排出量、排気量の両方を勘案したものとし、環境損傷負担金と財産税の両方の性格を持たせる。
といったところだ。
こうした大きな改革を行う大義名分として掲げられているのは、CO2排出量の削減である。与党民主党は「2020年に日本のCO2排出量を90年時点から25%削減(05年比で約32%とされる)」という目標を国際公約として掲げている。クルマにCO2課税を導入すれば、CO2排出量の抑制に役立つという論法だ。この研究会自体、もともと鳩山内閣と第一次菅内閣で総務大臣を務めた原口一博衆議院議員の指示によって組織、開催されたもので、民主党の意向が強く反映されている。
◆“聖域”軽自動車と営業用自動車の増税
CO2課税導入を目指す理由はそれだけではない。CO2削減を大義名分に、自動車部門からの税収アップを目指しているのだ。民主党政権は今、財源不足に悩まされ、予算を組むこともままならない状況である。巨額の税収が得られる自動車関連諸税を、税収増を当て込める数少ない部門とみているのだ。
その目玉が、軽自動車と営業用自動車の増税である。軽自動車についてはこれまでも散々、増税の槍玉に上がってきたが、かつては産業保護の観点から“聖域”とされてきた営業車についても大幅増税を示唆しているあたりに本気度がうかがえる。
CO2排出量削減はグローバルなトレンドであり、環境自動車税はそれにマッチした税制だというのが研究会の結論だ。
CO2削減という部分のみを見れば、研究会の主張には合理性がある。軽自動車や営業用自動車の税制を大幅に上げれば軽自動車の販売台数は激減するが、軽自動車がコンパクトカー並みの税額となれば税収は台あたり約3倍となる。その税収増は台数の激減分をカバーして余りあるという計算はとりあえず成り立つ。
一方で、クルマの保有台数が減ることによるCO2排出量の抑制効果もある程度は期待できるだろう。明確なシミュレーションは行われていないが、クルマの保有台数は、公共交通機関がほとんど存在せず、軽自動車を中心にクルマが“一人に一台”というレベルで普及している地方部をはじめ、各地で減少することは想像に難くない。クルマ1台あたりの走行距離は多少延びるであろうが、全体の走行距離は抑制されるだろう。
このように、CO2排出量削減を社会の最大目標とし、その達成のためなら社会の枠組みをいかように変えても構わないという視点に立つ限り、自動車税、とりわけ軽自動車や営業車など、税額の低いクルマの課税を大幅に強化することは一定の意義を持つと言える。
が、日本のモビリティや国土の有効活用、とりわけ地方の活性化を考えたとき、本当にこのシステムでいいかというと、この政策はなはだ疑問である。
◆増税が地方の「足」を奪う
今日、過疎地域の公共交通網は全国的に軒並み崩壊している。筆者は昨年7月、皆既日食を見ようと悪天候を押して種子島に行ったのだが、バスは島を南北に縦貫する国道58号線こそ1日に11本バスが走っているものの、それ以外は朝に上り1本、夕に下り1本といった状況で、生活路線としてはほとんど役に立たない状況であった。
この様子は種子島に限ったことではない。九州・沖縄から北海道まで、山間部などに少し入り込んだ瞬間、公共交通機関での移動は事実上不可能という状況を目の当たりにできる。もちろんこうしたエリアにも住人はちゃんといて、その数は意外に多い。
近年、過疎地で経営を大成功させ、ビジネス番組などでも注目された「A-Z (エーゼット)」というショッピングモールが鹿児島にある。その店舗のひとつが薩摩半島南部の川辺というところにあるのだが、周辺を見回すと山ばかりで、こんな過疎地に店舗を構えて商売になるのかと思ってしまうほどだ。が、果てを見るのが嫌になるほど広い駐車場は普段から、来店客のクルマで一面埋め尽くされている。過疎地ではすでにクルマ社会が浸透しており、半径数十kmという広大なエリアから客が集まっているのだ。
研究会が打ち出した、軽自動車と乗用車の税制を一本化するという構想は、CO2抑制という観点では正義性を持つ一方で、こうした地方の生活を徹底破壊してしまう可能性がある。その代替案として研究会は、増えた税収の一部を公共交通機関の整備に回すという案を出している。が、過疎地で公共交通機関を走らせてもたちまち赤字となり、すぐに廃止論議や補助金問題が発生することは明白であり、愚策である。
軽自動車はもともと、日本版国民車構想から出てきたもので、クルマの普及と自動車産業の振興の一挙両得を狙って税額が低く抑えられた。が、その後、地方の過疎化が進むにしたがって、公共交通機関なき後の「移動の自由」の保障へと役割を変えて温存されてきたという経緯がある。
地方の足となった軽自動車の税額を単純に引き上げることは、移動の自由を阻害し、ひいてはその土地に住み続ける権利を事実上奪ってしまいかねないような、重大な方針転換と言える。当事者にとっては、CO2などよりよほど深刻な生活の危機とも言えよう。
◆モビリティの視点に立った議論を
ホンダの前社長、福井威夫氏は「日本は国土が狭く、しかも山がち。その大切な土地をあまねく有効活用できないようなら日本は滅びますよ。公共交通機関を置けないような地方で人やモノの流れを絶やさないため、低価格なパーソナルモビリティの道具を作り続けることはホンダの使命」と語っていた。が、クルマのコストは購入費用であるイニシャルコストだけではない。維持費であるランニングコストが上がっては、安さは失われてしまうのだ。
日本が全国にあまねく公共交通機関を敷設し、移動のサービスを国民に提供できない以上、軽自動車と普通車の税制を統合するというだけではモビリティの維持を図ることはできない。スズキの鈴木修社長はこの軽自動車税制について、「軽の税金を上げるだけでなく、リッターカーの税金を下げるという話ならいくらでも協力するのに」と語るが、研究会の意見はあくまで現状維持プラスアルファだ。
軽自動車の税額を引き上げるならば、それに代わって地方のモビリティを維持する新しいシステムを作るべきだ。たとえば過去、スズキが作った『ツイン』やダイムラーの『スマート・フォーツー』のような、現在の軽自動車よりも小型の2人乗り自動車を、今の軽自動車より安い税額で乗れるようにするといった制度である。そうすれば、一家のメインのクルマとして普通車を1台保有しても、後のクルマの維持費は大きく抑制でき、トータルでの支出を増やさずにすむ。また、2人乗りに限定することで、普通車との差別化を図ることもできるであろう。
こうしたモビリティの視点に立った議論ができていない最大の理由は、自動車関係税制に関する研究会のメンバーが税金や財政学、法律の専門家、税を取る地方公共団体、そしてなぜか広告メディアである宣伝会議の編集室長など、モビリティのド素人ばかりで構成されていることにある。
原口総務大臣自身、道路交通に関しては素人であるため、致し方のない部分もあろう。情けないのは道路交通のプロフェッショナルである自動車メーカー、建設会社、IT企業、エネルギー会社などである。行政の言いなりなのか興味がないのかはわからないが、有効な提言を何らできていない。が、今のタイミングで声を上げなければ、日本のモビリティは大きな打撃を受けることは間違いない。
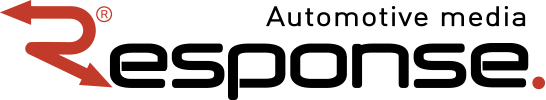


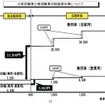




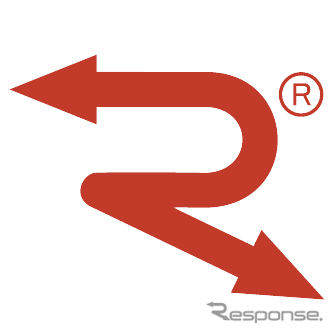

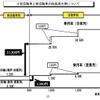








![車購入時の“2重課税”見直し、「環境性能割」2年間限定で停止検討へ[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_l1/2164061.jpg)





![プロは、ドアを物理的にチューニングできる![イン・カー・リスニング学…プロショップ編]](/imgs/sq_l1/2181931.jpg)

