11月19日から21日までの3日間、パシフィコ横浜で「オートモーティブ ソフトウエア エキスポ 2025」が開催される。SDVやCASEといった次世代モビリティの核となる自動車ソフトウエアに特化したイベントで、今回が3回目の開催となる。
組込み/エッジテクノロジーの総合展である「EdgeTech+(エッジテックプラス)」の中から生まれた同展は、開催当初より自動車業界内外から注目を集めた。自動車の開発や組込みテクノロジー、IoT関連のプログラミングやサービスなど最新のソフトウエア技術にフォーカスを当てた技術、製品、情報が一堂に介す場となる。
開催を前に、同展の事務局長大嶋康彰氏(ナノオプト・メディア 代表取締役社長)と、レスポンス編集長の三浦和也が対談。現在の自動車業界が抱える課題、そして同展注目のポイントについて語り合った。
◆自動車は巨大な動くIoT
 レスポンス編集長 三浦和也(左)とナノオプト・メディア 代表取締役社長 大嶋康彰氏(右)
レスポンス編集長 三浦和也(左)とナノオプト・メディア 代表取締役社長 大嶋康彰氏(右)三浦和也(以下、三浦):ずばり今年の「オートモーティブ ソフトウエア エキスポ2025」。大嶋さんとしてテーマは何に掲げてますか。
大嶋康彰社長(以下、大嶋):今回のテーマはいくつかあると思いますが、本格的にSDV時代が到来する最終準備の局面にAI支援開発のトレンドが合流しました。それに対してどう業界内外でタック組んで体制を作っていくかというのがひとつ。また、SDVで先行する中国をはじめ、海外でのトレンドも見逃せないポイントだと思います。
あとはやっぱりサイバーセキュリティです。OTA(Over-the-Air)でどんどんクルマがアップデートされるようになると、サイバーセキュリティのリスクが隣り合わせになる。そして人材です。これらのトピックでは、これまでの自動車業界に求められてきたものとは異なるスキルセットがエンジニアに求められることになります。こうしたことを踏まえて、業界として今どんな課題があって、どういう風に取り組んでいかなきゃいけないかということを感じて頂けるかと思います。
三浦:今回はオートモーティブ ソフトウエア エキスポとしては3回目。元々、組込み/エッジテクノロジーの総合展である「EdgeTech+」という母体があって、そこから生まれたオートモーティブですが、これが生まれた意義というのを教えていただけますか。
大嶋:自動車に関連する展示会は、すでにいくつか開催されていますが、やはりハードウエア中心のイベントが多いですね。EdgeTech+の場合は、ソフトウエア開発側からのアプローチになります。もともと組み込みのシステム業界というのは自動車業界とも非常に近い距離にありましたし、家電業界を含めて、日本のものづくり業界の重要な役割を果たしてきていました。今後は自動車がソフトウエア化していくという文脈の中では、ソフトウエアこそが中心的な役割を担っていくことになります。
三浦:SDVによってクルマのつくり方が、ハードウエアからソフトウエア中心にシフトしていく、つまりハードウエアとソフトウエアの主従が逆転していく中で、自動車業界にとっては主従の新しい側から見た関係を体現してるのがこのイベントであると。ハードウエアを見せるコンシューマーイベントの要素もあるモビリティショーとは逆の視点が得られるとのがポイントになりそうですね。
大嶋:これまではソフトウエア業界の方や、自動車業界の中でもソフトウエアに近い業種の方の来場がメインでした。ただ、これからは自動車がソフトウエア化する、コンピューター化するという中で、自動車づくりに関わる方々全員がその潮流を捉える必要あると思います。自動車は巨大な動くIoTです。ですから、ソフトウエアに関わる方はもちろんですが、ハードウエアの開発に携わるエンジニアの方々にもぜひお越し頂きたいと思っています。
 ナノオプト・メディア 代表取締役社長 大嶋康彰氏
ナノオプト・メディア 代表取締役社長 大嶋康彰氏
三浦:ハードウエア開発の人が、自らの足でソフトウエアの最先端に触れることができる場所に飛び込む。行動するハードウエア技術者というのが、これから日本の自動車業界にとっては重要になってくるかもしれないですね。
今回の出展社名簿を見せていただきましたが、異業種からの参加が目につきました。
大嶋:そうですね、CRIさんとかエピックゲームズさんのようなゲーム業界の企業も自動車ソフトウエアに参入し初めています。開発環境はもちろん、コックピットまわりのユーザー体験のデザインにもゲームで培った技術が活かされはじめています。
三浦:HMI(ヒューマンマシンインターフェース)の部分、人間の操作に対してどうハードが対応するか、どう見せるかというところのリアルタイムな感覚なんかは、ゲーム業界の人はシビアに見ていると思います。そしてエンターテイメント性ですよね。クルマがワクワクする、楽しいものであるというのが大前提なので、日本はゲーム業界も非常に裾野が広いですし、SDVになってくると日本の強みがより発揮できそうですね。
◆「サイバーセキュリティ」と「AI」が2大テーマに
 オートモーティブ ソフトウエア エキスポ 2024の会場風景
オートモーティブ ソフトウエア エキスポ 2024の会場風景三浦:今回、展示だけじゃなくてカンファレンスも多く開催されます。特に注目のカンファレンスはありますか?
大嶋:話題のソニー・ホンダモビリティさんからはまさに「モビリティにおける新たな価値の創造」としてクラウドとソフトウエアが果たす役割について語っていただきますし、海外の動向を知る、というところでは昨年も出ていただいた日産自動車さんから中国の日産出行服務有限公司に総経理として赴任されている山内進一郎氏が、中国での事例をもとにAIとSDV、さらにAIが進化を主導するAI-DVについて講演されます。なかなか日本には入ってこない情報も聞けると思いますので、注目していただきたいですね。
あとはサイバーセキュリティ。今回はJ-Auto ISACさんとタイアップして、自動車サイバーセキュリティ専門のセッションを3日間通しておこないます。これに関連した展示もありますので、併せて見ていただきたいと思います。
三浦:丸3日間も自動車のサイバーセキュリティに特化したセッションをおこなうのですか?
大嶋:それだけ取り組まなきゃいけない中身があるということですよ。以前はサイバーセキュリティというと、「お金がかかるし…」というような厄介者扱いでしたが、今は事業継続性の観点からも無視することはできません。AIを活用しながら、“攻め”と“守り”の両面をやっていかないといけません。クルマが動かなくなる、というのも大きな問題ですし、最悪の場合は工場が止まる、ということにも繋がりかねません。
三浦:自動車関連企業から安心安全のイメージが損なわれてしまうのは絶対に避けなければなりませんね。
大嶋:はい。ですからもう必須要件ですね。生成AIについては、EdgeTech+と一緒のコーナーになりますので、必ずしも自動車向けというわけでもありませんが、ものづくりに関連したソリューションが中心になりますので、自動車業界の方にも参考になるものが結構あるんじゃないかなと思います。
三浦:自動車以外のものづくりでは、どのような業界、ジャンルが注目でしょうか?
 レスポンス編集長 三浦和也(左)とナノオプト・メディア 代表取締役社長 大嶋康彰氏(右)
レスポンス編集長 三浦和也(左)とナノオプト・メディア 代表取締役社長 大嶋康彰氏(右)大嶋:これからはやはりロボットやフィジカルAIと呼ばれる分野でしょう。大きなくくりの中では自動運転もフィジカルAIの1つだと思います。
三浦:サイバーセキュリティとAI、これは2大テーマとして自動車分野以外の展示でも抑えていると。自動車業界の人は他の業界のブースやカンファレンスも見た方がいいですね。
大嶋:SDV時代の人材教育も業界全体の課題だと感じています。20日に三浦さんにモデレートしていただくセッションでは、トヨタ自動車さん、日産自動車さん、本田技研工業さんから、それぞれ人材教育に携わる方々をお招きして、組込みシステム技術協会の副会長も交えて、SDVの本格化にあたり求められる人材とは、というテーマでお話しいただきます。
三浦:例えばアメリカではSDVやAIの動きに対して、従来スキルの人材をばっさり切って、新たな人材を雇い入れる、というような人材の入れ替えをするのですが、日本企業は解雇を避けてリスキリング教育を中心に開発体制を変えてゆきます。日本は人手不足だと言われる中で、これまで開発に携わってきたエンジニアたちの発想の転換とかスキルチェンジをいかに上手くおこなっていくかというのは、企業競争力の非常に重要なポイントになるところです。
◆SDV化が進む自動車業界の課題
三浦:SDV化が進む中での自動車ソフトウエア現場の課題というのは、わかりやすく言うとどんな所にあるんでしょうか。
大嶋:これは自動車業界だけの話ではないと思いますが、古い体質が残ってしまってるというか。ハードウエア中心の開発体制や開発プロセスとか、人材の揃え方とか、そういうところの刷新が追いついていないなというのはあります。クルマは当然、人の命が関わるものですから変更に慎重になるのも仕方ありませんが、そのあたりをどうバランスを取って、ソフトウエア化を睨んだ人材確保や体制作り、周りの企業さんとのタッグというものを業界全体で考えていくのが急務だと思います。
 ナノオプト・メディア 代表取締役社長 大嶋康彰氏
ナノオプト・メディア 代表取締役社長 大嶋康彰氏三浦:作り手の側はAIひとつを取ってみても、AIを活用しなければいけないというのはもう自明になっています。ほんの1年前は、「AIって嘘つくけど、本当に使っていいの?」とか「本当に安全なの?」という迷いもありましたが、今、これを否定する人はもういませんね。このわずか1年でも、環境だけでなく意識も大きく変わりましたよね。
つぎは消費者に対して、つまり多くの「今のままでいいと思ってる人」たちに対して、新たな価値に同意してもらわなければならないという課題ですよね。
大嶋:確かにそれは大きな課題の1つですね。やっぱり、瞬間的にわかりやすいっていうのはすごい大切だと思います。最近のスマートフォンでは、SNSやカメラの性能が買い替えの原動力になっている。
三浦:ハードとソフトの組み合わせで自分でびっくりするほどよい写真が撮れる。友達に写真を自慢したい。だから20万円のスマホに買い換えようという発想になる。
大嶋:モチベーションとしてはわかりやすいですよね。
三浦:多分そういうものがSDVにとっても必要なんですよ。僕はそれが市街地でのハンズオフ走行や自動運転だと思います。運転手責任の自動運転であっても、市街地でハンズフリーができて目的地まで行けるということは、運転が苦手な人も、お年寄りであってもドライブに不安を覚えることなく行ける。日本の今の交通課題とか高齢者ドライバーの課題を直接解決する技術として期待しています。
大嶋:それがSDVの価値としてシンクロできれば夢が広がりますね。
 オートモーティブ ソフトウエア エキスポ 2024の会場風景
オートモーティブ ソフトウエア エキスポ 2024の会場風景三浦:今回「オートモーティブ ソフトウエア エキスポ2025」は3回目を迎えるわけですが、改めて来場者には何を持ち帰ってほしいですか? また、4回目、5回目へ向けた展望などがあれば教えてください。
大嶋:イベントそのものはソフトウエア業界のイベントで、かなりフォーカスされた催しではありますが、やはり自動車開発に関わる全ての方が変革の中心となって、これからどういう風に取り組んでいくべきか、どう変えていくかというのを考えていただく機会になると思います。ジャパンモビリティショーには多くの業界の方も行かれたでしょうから、そこで見た「未来のコンセプト」を実現するためのソフトウエア技術を「オートモーティブ ソフトウエア エキスポ2025」で組み立てていただく。そんな流れになると、美しいなと思います。
三浦:発注者の先にいる、最終利用者に響く技術だったりサービスから逆算する、モビリティショーと組み合わせて視野を広げる機会にしたいですね。
大嶋:そうですね。自動車は日本の製造業の主力産業ですから、海外に遅れをとらないようにぜひ頑張ってほしいと思いますし、それを支えるイベントにできればと考えています。
オートモーティブ ソフトウエア エキスポ 2025の詳細はこちら
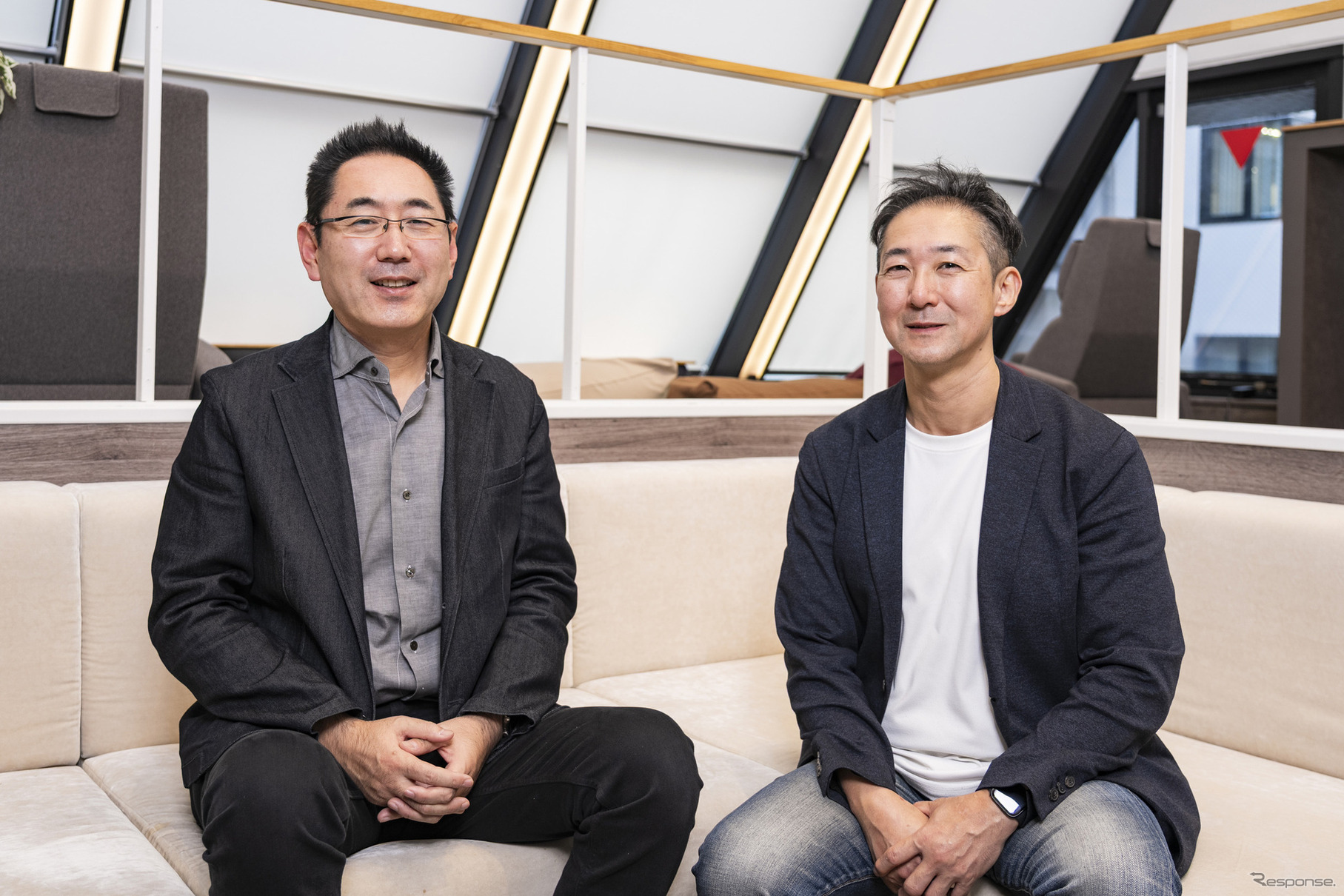







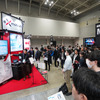




![商用車SDVの勝ち筋を読み解く…KPMGコンサルティング プリンシパル 轟木光氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2183972.png)


![外付けの“アンプ”は本来不要!?[カー用音響機材・チョイスの極意…外部パワーアンプ編]](/imgs/sq_m_l1/2185059.jpg)

