深々とした色合いの冬の蒼空にカラフルな熱気球が次々に離陸していく――12月17日から19日までの3日間にわたって開催された「熱気球ホンダグランプリ2021」の最終戦、渡良瀬バルーンレースの初日のフライト。一見、ごくありふれた熱気球競技の光景のようだが、実は滅多に見ることのできないビューだ。
通常、離陸許可を示すグリーンフラッグが揚がったのは午前10時45分。実はこの時間に熱気球がリフトオフすることは珍しく、そうなったのは天候と大会本部の決断ゆえのことだった。通常、熱気球は早朝と夕方に飛ぶのだが、この日は明け方に雨。天候は午前中に急回復するものの、午後には強い地表風が吹くと予想されていた。
熱気球は地表風が強いと飛ぶことができない。一旦上空に上がってしまえば問題はないのだが、地表で風に煽られると離陸準備のために熱気球を立てることができないからだ。2日目は冬型の気圧配置で1日中北西の季節風が吹き荒れる予報となっていたことから、午後に飛べなければ最終日の午前中まで飛ぶチャンスがなくなってしまう。そこでレースの競技本部が案じた一計は雨と風の合間、昼下がりにレースをしてみるということだった。
「40年以上熱気球競技に関わってきましたが、昼前に競技をやってみるというのは初めてのこと」
町田耕造・熱気球運営機構会長は会場でこう語っていた。
真昼の蒼い空に打ち上がった熱気球
 緑旗が揚がると一斉に気球を膨らませ始める。最初は送風機で空気を送り込み、ある程度たまるったところでバーナーで熱を入れる。
緑旗が揚がると一斉に気球を膨らませ始める。最初は送風機で空気を送り込み、ある程度たまるったところでバーナーで熱を入れる。実際、この日の判断はかなり異例。熱気球は地表風には弱いものの、いったん飛んでしまえば横風には一般的なイメージよりずっと強い。アドベンチャーフライトでは時速150kmの風にだって乗れるほどだ。それに対して上昇気流、下降気流、縦渦など縦方向の風は熱気球の大敵で、飛行は不安定になるし、着陸は往々にしてハードランディングになる。ゆえに朝凪と夕凪の2回が飛行のチャンスとされているのだ。
この日、ピンポイント予想では逆転層(地表より上空のほうが気温が高い現象。対流風が弱くなる傾向にある)がブレークするのが12時半頃となっていた。気温が上がっても上昇気流がそれほど強くならなければ何とかレースを行うことができるのではないかというギリギリの読みによって生まれたのが、昼下がりのレースだった。
グリーンフラッグが揚がった後、昼間のフライトということで各機、いつもより慎重に風を見極めながら1機、また1機と離陸を開始した。機上取材が中止となり、ローンチ(打ち上げ)サイトから上昇していく気球を眺めることになったのだが、その時にふと気づいたのが普段とまったく異なる、やや黒味を帯びた真昼の冬晴れの蒼い空。エンベロープ(熱気球の球皮)のカラフルな装いがその蒼空に実に美しく映えた。
 渡良瀬バルーンレース2021
渡良瀬バルーンレース2021
大会関係者も空の美しさ、遅い時間に飛ぶことによる集客など、異例な時間帯に飛んだことが示したいくつかの効果についてポジティブに評価していた。が、今後、ある程度積極的にこの時間帯を選んで競技をすることがあるかどうかについては「面白かったけど、たまたまうまく行っただけのようにも思う。今後この時間帯を狙ってやるかと言われれば、まあ難しいでしょうね」(町田氏)。まさにこの日だけのプレミアムビューだったのだ。
今年の渡良瀬バルーンレースは若年層に人気のゲーム「あんさんぶるスターズ」とコラボレーションを組んでおり、会場にはその歌を目当てにやってきた人も多々見られた。偶然だが、遅い時間に競技が行われたことでその来場者たちの多くが熱気球が飛び立つ様をライブで目にすることになり、あちこちから歓声が沸き起こった。
「ヘジテーションワルツ」のみの短時間決戦
 地上に設けられた巨大な✕印のゴール。熱気球パイロットは風を読みながらこのゴールに近づき、マーカーを落とす。
地上に設けられた巨大な✕印のゴール。熱気球パイロットは風を読みながらこのゴールに近づき、マーカーを落とす。さて、熱気球競技の中身である。この昼下がりのフライトでパイロットに与えられたタスクは「ヘジテーションワルツ」の1種目のみ。熱気球競技は数十種類の種目があり、条件が良い時は5~6種目を組み合わせて妙技を競わせるのだが、昼間に飛ぶリスクを考慮して“短時間決戦”とされた。ヘジテーションワルツとは複数のゴールが地上に設定され、パイロットは機上で任意のゴールを選び、マーカーを落とす。投下ポイントとゴール中心の距離が近いほど順位が高いというゲームである。
「ヘジテーション(迷い、ためらい)という言葉が示すように、実際にやってみると『この風だとあのターゲットがいいかな』『あ、でもやっぱりあっちのほうが…』と迷うものなんですよ」(町田氏)
グリーンフラッグが揚がると、普段はローンチサイトから青空に向けて一斉離陸する。それはいつ見ても壮観なものだ…・が、この日は多くの選手が様子を見てなかなか飛び立たない。「天候回復に伴って風が入れ替わるのを待っていたのかな。いつもは真っ先に飛ぶタイプの強豪選手が長く地上にとどまっていたのもそれが理由でしょう」(町田氏)。
本来、ヘジテーションワルツは迷いの競技なのだが、今日は風向の変化自体は非常に小さく、3つのうち1つのゴールにエントリーした32機のほぼすべてが殺到することになった。ゴールに最も近かったのはヤクルトマンをあしらった気球を操る機番11の山下太一朗選手。グリーンフラッグが掲げられてから40分以内という離陸リミットの最後までローンチサイトに留まっていた数機のうちのひとりだった。
コロナのうっぷんを晴らす重厚なフライトに
 ヤクルトマン号の山下太一朗選手がヘジテーションワルツで最もゴールに近いところにマーカーを落とした。
ヤクルトマン号の山下太一朗選手がヘジテーションワルツで最もゴールに近いところにマーカーを落とした。18日は強風で午前、午後ともフライトはキャンセル。だが今シーズンの最終フライトである19日朝は前日、また今年も散々振り回されたコロナ禍のうっぷんを晴らすかのような重厚なものとなった。与えられたタスクは5種目。
・フライ・イン(ゴールから一定以上離れた任意の場所から飛び立ち、ゴールにマーカーを落とす)
・ミニマムディスタンス・ダブルドロップ(離れた2つの空域にマーカーを1つずつ落とし、その距離の短さを競う)
・パイロット・デクレアド・ゴール(飛ぶ前にパイロットが競技空域の任意の地点をゴールに設定し、そこにマーカーを落とす)
・ジャッジ・デクレアド・ゴール(競技本部が指定したゴールにマーカーを落とす)
・フライ・オン(パイロットが飛行中に決めたゴールにマーカーを落とす。その場所は前の種目のマーカーに記入して伝える)
初日の1タスク、最終日の5タスクの計6タスクで競われた渡良瀬バルーンレースを制したのは富澤三世選手が操る機番#3、木村情報技術バルーンチーム。中止となった鈴鹿を除く年間4戦のグランプリで総合優勝を果たしたのは世界選手権優勝経験者の藤田雄大選手がパイロットを務める機番#1、やずやバルーンチームだった。
ホンダ屈指の歴史を誇るイベント
 渡良瀬バルーンレース2021
渡良瀬バルーンレース2021航空機業界への参入を決めるなど、空に愛着を持っていたことで知られる久米是志・元ホンダ社長の肝煎りでホンダが冠スポンサーを務めるようになった熱気球ホンダグランプリ。最初にスポンサーとなった1995年からすでに27年が経過し、継続して取り組んできた活動としては、同社屈指の歴史の長さを誇るイベントにもなっている。
順当であれば2022年も渡良瀬(栃木)、佐久(長野)、一関平泉(岩手)、佐賀、鈴鹿(三重)の5戦が組まれる。コロナ禍が収まれば、レースと併催される各種の祭りも復活することだろう。ちなみにレースを見るのはタダである。ドライブがてら観戦にお出かけしてみては!?










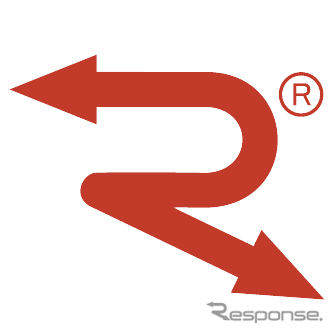











![2026年春闘スタート、自動車総連「月1万2000円以上」の賃上げ要求[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2180893.jpg)



