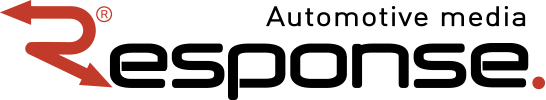東京モーターショー2017に出展したグッドイヤーは、AI搭載球形タイヤ『Eagle 360 Urban』を日本初公開した。“球体”は完全自動運転時代を想定したコンセプトタイヤだが、従来のタイヤにはない斬新な発想だ。開発担当者にコンセプトについて話を聞いた。
インタビューに応じてくれたのは、プレスカンファレンスにも登壇したグッドイヤーのアジアパシフィック消費財タイヤ部門 副社長 ライオネル・ラミレス氏と、同アジアパシフィック 製品開発部門 副社長 デビッド・ザンジグ氏の二人。タイヤと言えばドーナツ型の形状しか思い浮かばないが、それを“球体”としたのはどんな理由からなのか。
「完全自動運転時代を迎えるとクルマが意思を持つようになり、従来の発想ではタイヤは対応できなくなることが開発のスタートだった」と、開発のきっかけからザンジグ氏は話してくれた。「(自動運転では)モビリティを極限まで活用する必要が出てくる。そこでクルマの方向を変える方法に工夫を加える必要があった」という。
クルマが方向を変えようとするとき、自動運転ではドライバーが操作するのではない。そこにはステアリングさえもない。つまり、そんな状況下で方向を変えるには球体が最適という考え方だ。
Eagle 360 Urbanにはもう一つ大きな特徴がある。それはタイヤ自身が検知した路面の状況に応じて表面を無段階で変化させる能力を備えているということ。路面が乾いたり濡れたりしたとき、最適な状態にタイヤ自身が変化するのだ。これは雪道でも同じ対応をする。これについてザンジグ氏は「表面が変化するのはバイオロジー的な要素が大きい。周囲の環境に合わせて素材を変化させる技術で、これは2016年発表のEagle 360にも共通するものだ。これを“スマートマテリアル”と呼んでいる」と説明する。
この発想はまさに、グッドイヤーのオールシーズンタイヤ『ベクター4シーズンズ』にも共通する。今でこそ珍しくはなくなったオールシーズンタイヤだが、それを最初に開発したのはグッドイヤーであり、それは1977年のこと。今から40年も前にこれを具体化していたのだ。
ここでEagle 360 Urbanについて、一つ疑問が湧く。球体が自在に転がるためにはどうやって車両にタイヤを装着するのかということ。「それは磁気浮揚の技術を使う」(ザンジグ氏)という。要は、クルマはタイヤの上で浮いているのだ。もちろん、リニアモーターカーではないけれど、その実現にはそれなりの電力が必要になると思われるが、「それが今後の技術開発で解決していく問題」とザンジグ氏。しかし、こんな発想はそう簡単に出てくるものではない。
これについてラミレス氏が答えてくれた。「グッドイヤーはゴム素材をタイヤに使う発想でこの業界に参入した100年以上も前の創業以来、ずっと革新の歴史を繰り返して“初”ということにこだわってきた。全天候タイヤなども1977年に世界で初めて開発した。革新という伝統を受け継いでいるのがグッドイヤー」と、Eagle 360 Urbanが生まれた背景を説明してくれた。しかし、そうした姿勢はともすると技術志向に走りがちで、ユーザーの要求とかけ離れることもあるではないか?
ラミレス氏は続ける。「ユーザーのニーズをきちんと把握して製品開発を行うのもグッドイヤーの基本姿勢だ。ユーザーの声をしっかりと受け止め、試乗ごとに対応も万全だ。日本市場向けに作られたスタッドレスタイヤ『ICE NAVI7』はその成果だ」と力を込める。確かに、タイヤは国情で使い方は微妙に異なる。グッドイヤーはそうした市場の要望に応え、信頼を獲得してきたというわけだ。
一方、Eagle 360 Urbanは、昨年発表したEagle 360がベースとなっている。どこが違っているのか。それは、単にセンシングするだけではなく、獲得したデータをAIが判断する能力を身につけ、タイヤ自ら路面の変化に対応する。しかも、そのデータはクラウドにアップされ、より多くのクルマ同士が共有できるようになる。さらに「あらゆる端末に接続するIoTによるコネクティッドワールドの一部にもなる」(ザンジグ氏)。
ドライバーがまったく関与しない「レベル5」の自動運転は、現時点でこそ夢物語の領域ではあるが、それを実現していくためにはこうした技術の積み上げこそが重要だ。グッドイヤーの今後の新たな展開に注目したい。