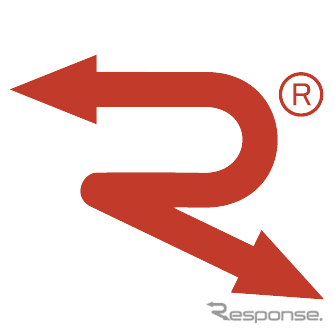エンジンオイルは最も交換頻度が高い消耗品であり、リーズナブルにチューニングできるパーツである。とりあえず高いオイルを入れておけば何か良くなりそうだと思い、なんとなく高級オイルを選ぶ方もいるが、それが必ずしも正解とは限らない。
ではどのようにチューニングとしてエンジンオイルを選び使えばよいのだろうか。
◆エンジンオイルの粘度と規格の基本(0W-20や5W-30の選び方)
まず、エンジンオイルは自動車メーカーによって使用できる粘度と規格が定められている。粘度はオイルの硬さや流動性を示す指標で、最初の数値がオイルが冷えているときの粘度、後半の数値はオイルが温まったときの粘度を示す。
最近では純正指定の粘度はどんどんやわらかいものに変わってきている。これはオイル抵抗による燃費悪化を防ぐためで、できるだけ低粘度にして抵抗を減らし燃費を稼ぐという設計意図だ。そのため、純正指定で0W-20などが指定されることが多い。
◆「サーキットだから硬い」は昔話? 粘度を上げる前に知るべきリスク
サーキット走行や峠の走行が多い人や高速道路の長距離走行が多い人は、昔から粘度を上げるべきと言われてきた。エンジンが熱を持ちやすく、シャバシャバな純正指定の粘度では油膜が切れるため、粘度を高めようと考えるが、それは必ずしも正解ではない。
エンジンは指定粘度を前提に設計されており、低粘度前提のエンジンに硬いオイルを入れると循環が遅くなる。具体的には、ヘッドに圧送したオイルがなかなかオイルパンに戻らず、オイルパン内の量が不足して圧送できず、エンジン内部にダメージを与え、エンジンブローに至ることもある。
これはサーキットでは特に起きやすい。前後左右に大きなGが発生し、オイルパン内のオイルが偏ってオイルポンプで吸い上げにくくなる条件下で、硬いオイルにするとさらにオイルが下がりにくくなり、オイルポンプがオイルを吸い上げられない事態を招き、結果としてダメージを与えることがある。
そのためサーキットやワインディングを走るから硬いオイルを入れておけばOKというのは昔の話だと認識したい。現在であれば純正指定の粘度に従うのが基本。純正指定も、メーカーによっては例えば0W-20と5W-30のどちらでも使えるなど、幅を持たせている場合がある。この場合、サーキット走行時は高い方の粘度を使用し、普段乗りが続く時や真冬は低い粘度に切り替えるといった、季節や用途に合わせたオイルチューニングが有効だ。
◆API/ILSACの最新規格とLSPI対策(API SP・ILSAC GF-6)
また、オイルにはさまざまな規格が存在する。有名どころはAPIとILSACで、これらの定められたグレードに合致したオイルを使うよう指定されている。
例えば、APIでは時代に合わせて規格が更新され、SM→SN→SN+→SPへと変わってきた。SN指定のエンジンであれば、その後発のSN+やSPは使用可能だが、SMは不可となる。近年は、小排気量にターボを組み合わせたダウンサイジングターボが増え、このタイプは低回転からの過給でノッキングが起きやすい。
現在のクルマはノックセンサーで検知し、点火時期や燃料噴射を補正してノッキングを抑えるが、それはパワーダウンを意味する。ここで問題となったのは、オイル中のカルシウム成分で、ダウンサイジングターボ特有のLSPI(低速早期着火/低速異常燃焼)を誘発しやすいとされた点だ。最新のオイルでは、清浄分散剤の設計を見直し、カルシウムを低減して別成分へシフトする動きが一般化している。したがって、LSPI対策油が指定されるエンジンに旧規格のオイルを入れると、カルシウム由来のノッキングが起きやすくなることもある。
結局のところ、それは価格の問題ではない。高価なオイルなら何でも良いわけではなく、規格に従ったオイル選びが大前提である。そのうえで、目的や好みに合うブランドのPRポイントや添加剤設計を比較し、最適な銘柄を選んでほしい。エンジンオイルの粘度の選び方や、API SP/ILSAC GF-6といったキーワードを押さえ、0W-20や5W-30の使い分けを理解すれば、燃費と保護性能の両立に近づける。