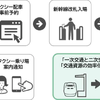「せまい日本 そんなに急いで どこへ行く」という交通安全スローガンが登場して42年。首都圏の列車には、速達列車に何度も抜かれる“カメ電”がある。東京と蘇我の間(43km)を結ぶ京葉線の各駅停車もそのひとつ。この列車にあえて乗るユーザーにその理由を聞いた。
特急や快速といった速達列車が複数設定されている平日17時台の東京駅京葉線ホーム。この時間帯に走る各駅停車のなかには、東京から蘇我まで走る間に、特急、快速、通勤快速と3種の列車に追い越されるものもある。
この“3回抜かれる各停”に乗ってみると、乗客のほとんどが各駅停車しか停車しない駅で降りていくが、終点の蘇我まで乗りとおす客の姿も見られた。
こうした“ゆっくり派”からは、「スマホのゲームに没頭できる。歩きながらだとゲームもできないから」「ドアが頻繁に開くし外気が入ってくるしで、冷房が効かないけど、快速より空いているのがいい」「英会話のリスニングがちょうど1時間」という声。なかには「腹が弱くてすぐにトイレに駆け込めるように」という男性もいた。
3回抜かれる各停は、東京と蘇我の間を1時間3分(表定速度40.95km/h)で走る。それを追い越す快速は、同区間43分(同60km/h)で、その差は20分。新習志野と海浜幕張の2駅連続で追い越される“カメ電”もある。
こうした現状について 鉄道書籍などを編集する小関秀彦さんは「“カメ電”は、急行や快速などの速達列車と比べると目的地への到達時間が多くかかるが、座れる確率が高くなったり、混雑していないなどから、自分の時間を確保しやすいという利用イメージがある。パソコンを広げたり、新聞やマンガを広げたりもでき、ちょっとした“デスクがわり”として活用する人も多いのでは」という。
いっぽうで、こうした“列車待ち合わせ”や“通過待ち”の多い各駅停車は、「減少傾向にある」と小関さん。「近年、都市部の鉄道では複々線区間を延伸したり、列車種別を単一化し、平行ダイヤを組むようなケースが増えている。そんな背景からか、都市部などでは列車追い越しシーンは減少傾向。ただ、線路容量いっぱいで列車を設定している路線も多いので、“カメ電”が消滅することはないだろう」とも話していた。




















![新幹線も走る「エンタメ空間」を演出へ、JR東日本と松竹が提携[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2059473.jpg)
![トヨタ時価総額48兆7981億円---バブル期のNTT超え日本企業で過去最大、世界では28位[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/1973566.jpg)