<講師>
茨城大学 カーボンリサイクルエネルギー研究センター 教授 古關 惠一 氏
<モデレーター>
KPMGコンサルティング株式会社 プリンシパル 轟木 光 氏
自動車の電動化と内燃機関の再評価が進む中、エネルギーの未来はどうなっていくのでしょうか。
このセミナーでは、エネルギー分野の最新動向を探り、今後のエネルギー社会について考えていきます。
たとえば、電気自動車(BEV)は近年、充電インフラの整備やバッテリー性能の向上など大きな進展を見せています。しかし、性能やコスト、充電設備の整備など解決すべき課題は依然として存在しています。それに対し、内燃機関を活用したハイブリッド車(HEV)やバイオ燃料・合成燃料を使った技術は、環境負荷を減らしつつ、再評価されています。これらの動きは自動車とエネルギーの関係に大きな変革をもたらす可能性があります。
エネルギー分野では、経済産業省が進める「S+3E(S:安全性、3E:安定供給・経済効率性・環境適合性)」を基に、企業や政府、研究機関による産官学の連携が進んでいます。再生可能エネルギーの導入や災害復旧力(レジリエンス)の強化を目的としたさまざまな成果があがっています。一方で環境分野では、グリーン経済(Greening Economy)の用語で、成長と経済性の両立という概念に切り込んできています。
しかし、自動車産業における産官学連携はまだ始まったばかりであり、電動化やカーボンニュートラルを実現するためにどのような協力体制を作り上げるか、いかに深い議論をするかが今後の課題です。
このセミナーでは、「これからのエネルギー社会をどう描くか、どのような戦略が必要か」といった問いに向けて、重要な視点となる内容をお話します。
1.環境と経済成長のWin-Win志向
環境保護と経済成長を両立させるカギは何か?2019年からのファクトを振り返り、環境と経済成長の両立解のポイントを探ります。
2.S+3Eとは-産業界・経済関係省庁による取り組みと産官学連携の重要性
どのようにして「安全性」「安定供給」「経済効率」「環境適合性」を一体的に実現するか、そのための協力の枠組みについて探ります。
3.消費者と供給者の視点の違いの考察
消費者と供給者、つまり使う側とつくる側の視点にはどのような違いがあり、どのようにそれぞれが抱える課題があるのか。たとえば、使う側とは自動車産業でありその車のユーザーのことであり、つくる側とはエネルギー生産・供給者側となります。その両者がどのようにこれまで異なった見え方となっているのか、相いれない両者の関係とその課題についても深堀りを行います。
4.社会実装を見据えた実例と課題
既に進行中の社会実装例を通して、環境と経済成長の両立について、そしてその課題について考えていきます。
カーボンニュートラルをはじめとする環境と経済成長の実現は、使う側の自動車産業やつくる側のエネルギー産業がそれぞれ独立した活動を通して実現されるものではなく、両者の異なる課題の捉え方や考え方を両者が歩み寄りながら理解し、解いていくことが重要になります。本セミナーを通して、エネルギーの未来を考えるとともにどのように解決していくべきかを一緒に考えていきましょう。


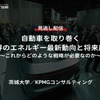



![電動化の変革を勝ち抜くアイシンの狙いとは…アイシン PTシステム製品企画部 部長 須山大樹氏[インタビュー]](/imgs/sq_l1/2174817.jpg)




