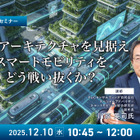MaaSは複数の多様な移動サービスを組み合わせて、検索・予約・決済等を一括で行えるようにすることで、シームレスな移動を提供するサービスのことである。
となると対象になるのは鉄道やバスなどの公共交通、自転車や電動キックボードなどのシェアリングがメインになると、多くの人が思うだろう。そんな中、ここに電動車いすを入れていこうと考えているのが、スタイリッシュな電動車いすを相次いで送り出しているWHILL(ウィル)だ。
車いすのシェアリングサービス
WHILLのプロジェクトがスタートしたのは2009年。2年後の東京モーターショーに試作機を展示し、翌年法人化を果たすと、2013年には米国拠点を開設。次の年に最初の市販型『モデルA』を発表する。モデルAは、筆者も審査委員を務めていた2015年度のグッドデザイン賞で、最高の栄誉となるグッドデザイン大賞を受賞した。多くのデザイナーや建築家、研究者などから高い評価を受けたことになる。
2017年には軽量化と分解可能な構造と低価格を両立した『モデルC』を発売。現在は進化形の『モデルC2』に加えて、折り畳み可能な『モデルF』、ハンドルタイプでスクーターのように乗れる『モデルS』の3タイプを販売している。

一方で同社は創業当初から、身体の状態や障害の有無にかかわらず誰でも乗りたいと思えるパーソナルモビリティを目指しており、空港や駅、遊園地などでシェアリングとして提供し、好きな時に自由に使えて楽しくスマートに移動できるモビリティサービスを思い描いていた。
車いすのシェアリングは、海外では以前から実例がある。代表例としては英国の「ショップモビリティ」が挙げられる。中心市街地に車いすやシニアカーなどを備えたオフィスを置き、常時または一時的に移動が困難な人に貸し出すもので、日本ではタウンモビリティという名前で展開している場所がある。欧州では、繁華街などを歩行者専用とした場所を多く見かけるが、駐車場から店舗まで相応の距離があることも多く、高齢者や移動障害者にとっては不便に感じる。そこで駐車場の近くなどで、移動を補助するパーソナルモビリティを貸し出しているのである。
目的地の中心市街地に車いすが用意されていれば、自動車で移動する際は自宅用の車いすを携行せずにすむので外出が楽になる。健常者ではあるが長い距離を歩くのは辛いという人も、ショップモビリティがあれば快適にショッピングを楽しむことができる。さらにユーザーにとっては外出機会が増え、社会との関わりが生まれ、店舗にとっても売り上げが増加し、市街地そのものが活性化するなどのメリットもある。ゆえに英国では年々導入都市が増えているという。なお日本では新型コロナウイルス感染拡大以降、移動型店舗サービスのことをショップモビリティと呼ぶことがあるが、英国のショップモビリティのほうが以前から存在していたことに留意していただきたい。
WHILLに話を戻すと、同社では2015年からシェアリングサービスの導入を始めている。対象となっているのは商業施設、ホテル、テーマパーク、美術館などで、今年3月に開業したプロ野球北海道日本ハムファイターズの本拠地、北海道ボールパークFビレッジとエスコンフィールド北海道にも配備された。
2017年に発表したモデルCは、こうした動きを踏まえ、国内で販売している電動車いすでは初めて通信機能を搭載しており、スマートフォンのアプリを使って遠隔操作を可能としたほか、トラブルの際はメーカー側で状況を確認し、その場で対処方法を受け取ることができるようになった。