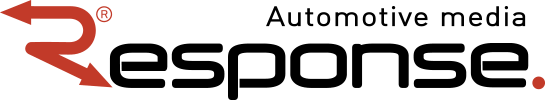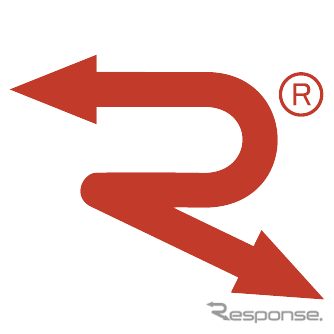ついに来るべき時がやってきたようだ。シトロエンは1955年に投入した独特な窒素ガスと油圧によるハイドロニューマチック(その後ハイドラクティブと名前変更)サスペンションの生産を止めるらしい。しかし独特な乗り味はこの『C4ピカソ』に受け継がれている。
シトロエンファンにとっては相当にショッキングなニュースだと思う。現在ラインナップでハイドラクティブが使われているのは、『C5』のみ。この現行C5の生産が終了した時、ハイドラクティブの生産も終わりになるという。ハイドロは非常に高価なシステムだし、金属バネでも十分に快適な乗り味が出せると判断した結果だと考えられる。
そして、ハイドラクティブに代わる、金属バネの快適さを体感させてくれたのが、新しいC4ピカソである。そもそも、C4ピカソに2列5人乗りのモデルが日本で販売されるのは、これが初めてのこと。従来単にC4ピカソと呼ばれていたモデルは、実は本国で『C4グランドピカソ』と呼ばれていたモデルで、今回は正式にグランドピカソとして3列7人乗りが登場、あわせて2列5人乗りのC4ピカソが日本正式デビューを果たしたというわけである。
この2台、単に室内空間の違いだけと思ってもらっては困る。実は外観もまるで異なっていて、その違いはフロントの顔付からサイドビュー、それにリアはテールゲートのデザインからコンビランプのデザインまで及んでいるのだ。だから、完璧なまでに差別化が図られている。少なくとも外観は。一方で室内はさすがに大きな違いはない。特にドライバーズシートに座るとそれを感じる。良くも悪くも個人主義を大切にするフランスのクルマらしく、シートはすべてインディビデュアル、即ち5人乗りは5脚、7人乗りは7脚のシートを備える。例によってルーフにまで回り込む広大なフロントウィンドーは、『C3』のようにゼニスウィンドーとは呼ばず、スーパーパノラミック・フロントウィンドーと呼ぶ。強い日差しを避けるためにルーフを前後に動かせるのもC3同様で、これはシトロエンの大きな個性と言えよう。
ダッシュ中央上部にメーターパネルを持ち、ドライバーの眼前には何もないレイアウトのダッシュボード。そのメーターはディスプレイタイプで、通常の丸型タコメーターとスピードメーター表示の他に、『GS』や『CX』に乗っていた人には懐かしい、ボビン式のタコメーター表示も可能になっている。こうして徐々にではあるが、シトロエンらしさというか、シトロエンの古き良き伝統を復活されてくれているのも、ファンにとってはたまらない。
車体のプラットフォームはプジョー『308』と共通である。すなわち、新プラットフォームEMP2を採用し、70kgの軽量化を実現した。一方エンジンはBMWとの共同開発による1.6リットル直4ターボユニット。アイドリングストップ機能を加え、従来より9psパワーアップしている。そしてこのエンジンと組み合わされるのは、第3世代となった6速AT。我が国のアイシンがサプライするものである。
乗り出し直後に感じたのは、「おぉ~! この乗り心地は!?」であった。路面のアンジュレーションはすべて体感させてくれるが、それによる突き上げ感やガツンと当たるショックはほぼ皆無。これはハイドロに匹敵すると思ったものである。後日C5を借りて、ハイドロを試してみたが、やはりハイドラクティブには叶わなかった。だから、これが無くなるのは返す返すも惜しいのである。とはいえ、C4ピカソの乗り心地が極上であることに変わりはない。リアにはトーションビームが採用されて4輪独立懸架ではないにもかかわらず、この乗り味なのだからチューニングが如何に大切かを痛感させられる。
1.6リットル直4ユニットは、165ps/240Nmとパワーはあるものの、プジョー308が搭載した直列3気筒ターボのような活気あふれる印象はない。より大人びた雰囲気を漂わせ、車格に合っていると感じる。何より、アイシン製の新しい6ATのその滑るようなシフト感覚をはじめとしたドライバビリティーの高さに感心した。先代から続く、か細いステックでDを選択した後はパドル操作。勿論それはマニュアル操作の時だが、Dレンジに入れて走っても、絶妙のクルーザーという印象で、ドライブトレーンに関する不満は全くない。サイズ的にはプジョー『308 SW』級。 しかし、天地が高い分MPVとしての使い勝手はこちらが上だ。因みに全高は1630mm。
■5つ星評価
パッケージング :★★★★
インテリア居住性:★★★★★
パワーソース:★★★★
フットワーク:★★★★
おすすめ度 :★★★★
中村孝仁|AJAJ会員
1952年生まれ、4歳にしてモーターマガジンの誌面を飾るクルマ好き。その後スーパーカーショップのバイトに始まり、ノバエンジニアリングの丁稚メカを経験し、その後ドイツでクルマ修行。1977年にジャーナリズム業界に入り、以来36年間、フリージャーナリストとして活動を続けている。