◆ガイアツを利用する勢力に要警戒
なるほど、そう来たかー、という感じだ。米国の自動車メーカー3社で組織する米自動車政策会議(AAPC)が、TPP(環太平洋経済連携協定)交渉への日本参加をめぐり、軽自動車規格が日本市場への参入障壁となっていると、USTR(米通商代表部)へ申し立てた。
米ビッグ3のクルマが日本で売れないのは、依然として魅力的な小型車が存在しないからであり、販売を着実に伸ばしている欧州勢に比べても努力不足は否めない。ただ、こうしたガイアツ(外圧)を利用し、軽規格と表裏一体となっている軽の税金を負担増へと誘導する勢力にも警戒すべきだ。生活の足としての軽を守るためにも、自動車業界は新たな税体系の理論武装など、万全の準備が求められる。
自動車の貿易障壁を関税で捉えると、日本は1978年の時点で完成車や主要部品の関税を撤廃している。これに対し、米国は乗用車や部品が2.5%、トラックは25%(一部のキャブシャシーは4%)となっている。
日本は世界で自動車市場が最も開かれた国のひとつではあるものの、1980年代から90年代にかけて、自動車とその部品は日米通商交渉で、常にビッグイシューとなった。小型車が主体の日本市場で米国車は苦戦し、貿易の不均衡は、政府介入なくして如何ともし難かったからだ。
◆登録車の市場が狭まっているという事実も
日本自動車工業会のまとめによると、日本市場での米国車のシェアはピークだった96年の1.6%から2011年は0.3%まで後退した。一方で、同じ期間に欧州車は3.0%から4.6%となり、昨年は過去最高に達している。日本への投入モデルを比較すると排気量2.0リットル以下のクルマでは米国メーカーが1モデルなのに対し、欧州メーカーは75モデル(いずれも10年時点)に及ぶ。
米国車の不振は市場障壁というより、米欧の「経営方針の相違」と見るのが妥当だ。もっとも、日本市場を軽自動車対登録車という構図で見れば、3台に1台強となった軽によって登録車の市場が狭まっているという事実もある。
昨年36%だった軽比率は近いうちに4割に達するとの見方が有力だ。毎年5月に徴収される自動車税(軽は軽自動車税)だけを見ても1.3リットルの登録車は軽の5倍近い負担となっており、こうした税負担の格差が、軽シフトにつながっている。
◆次世代車の時代に即した税体系を
一方、公共交通機関が貧弱な地方部で、軽は国民の移動手段の支えとなっている。日本の新車市場を考えても、軽規格を撤廃すれば、たちどころに総需要はしぼんで行くことになろう。日本の自動車各社とも、そうした見方に異論はないはずだ。
軽はエンジン排気量に660ccという制約があるため、燃費性能に課題があったものの、メーカー各社の努力で小型ハイブリッド車並みに改善されつつある。車体が小さいことによる使用資源の少なさも日本に適している。万が一、廃止を含めて軽規格を見直すとしても、現行レベルの税負担にとどめ、日本のミニカー育成を維持することが国策に叶う。
そのためには、登録車の税体系を現状の軽のレベルにさや寄せすることだ。それで欧米諸国に比べて負担の重い車体課税の問題も解消される。また、その際、排気量を課税額の基本としている自動車税は、エコカー減税のように燃費や環境性能も加味することが望ましい。多様な次世代環境車の時代に即した税体系は、早晩必要なのだから。














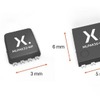




![「ツイーター」だけを追加 or 交換するのもアリ! さらには…?[お金をかけずにサウンドアップ]](/imgs/sq_m_l1/2168658.jpg)
