日昇自動車販売が1987年に「新車低金利販売」を導入した翌年、フランチャイズブランド「ONIX」(オニキス)を立ち上げた。このフランチャイズ部門が独立、ONIXの運営を手がけるのがオートコミュニケーションズだ。
同社は、この夏から秋にかけて、ONIXフランチャイズ店舗にスキャンツール(OBD2端子を用いた車内コンピュータ診断ツール)を一斉導入する。今回の取り組みについて、オートコミュニケーションズの鄭敏社長に狙いなどを聞いた。
---:新車、中古車の販売、買い取りを行う全国約300店舗のフランチャイズにスキャンツールを一斉導入します。その狙いは何ですか。
鄭社長:重視すべきは、ユーザーに自動車を買ってもらう前と、買ってもらった後をいかに大事にしていくか、ということです。自動車販売事業者は、どうしても自動車を「売る」ことが中心になってしまいます。相対的に販売の前後を大切にしていないのです。そこで、当社では販売前後のユーザーへの対応が大事だと言い続けています。特に販売後、アフターサービスは重要です。
鄭社長:日本国内の自動車販売のパイは大きくならないことが分かっています。であれば、「売る」という瞬間だけでなく、当社で自動車を買ってもらったユーザーとどのようにして関係を構築し、継続していくかということが大切な要素になります。ユーザーと関係を維持するためのツールとしてスキャンツールに着目しました。スキャンツールを用いてユーザーの車両データをストックし続けると、ユーザーの車両を深く知ることになります。結果としてユーザーとの関係も深くなるはずです。データでユーザーとつながることが、成熟した日本の自動車業界で必要になると感じました。
---:スキャンツールで取得したデータでユーザーとつながり続けるということで、顧客の囲い込みができると。
鄭社長:囲い込みを目的としてスキャンツールを導入するのではありません。ユーザーに安全・安心して自動車を使っていただきたいと考えたところ、素早く故障診断が出来るスキャンツールの導入に至ったのは自然発生的な考えです。スキャンツールはフランチャイズ全店舗に入れることを目指していますが、まだまだ一定数のフランチャイズ店舗は、導入を見送っています。スキャンツールを用いないと不具合が分からない場合もあります。自動車の不具合を確認すれば、そのままにはできませんから、しっかり直して、安心して自動車を使っていただく。安全な自動車の利用のため、当社からユーザーに点検を呼びかけることもあるでしょう。
---:スキャンツールを使用するには機材導入のコストや、サービス実施前の人材教育も必要です。コストに見合った成果は期待できるのでしょうか。
鄭社長:導入するスキャンツールは、エムログ社の「イーグルキャッチ」というスキャンツールですが、この製品は簡単に使用できることが大きな特徴です。スキャンツールの導入に時間やお金をかけず、基本的なデータを収集することが可能です。また、この商品がサーバーアップロード型であることも導入にあたってのポイントになりました。ユーザーの車両から得た情報をサーバーに残すことで、情報を追跡できるようになるからです。ユーザー情報の正確な保管、アップデートが速やかに行えるという点は魅力です。
鄭社長:スキャンツールを導入することで、販売店とのコミュニケーションを活性化することも狙いの一つです。スキャンツールで得たデータをきっかけに本部とフランチャイズ店舗がコミュニケーションをとることが出来ます。フランチャイズの店舗各社では、ユーザー第一という基本スタンスを改めて確認してもらいます。
---:スキャンツールを用いた点検が普及するとユーザーの考え方も変わりそうですか。
鄭社長:これまでの点検内容に加えて、デジタル情報も含め、ユーザーにとって良い形の点検が作られて行けばよいと考えています。
---:日本国内の自動車市場について見通しをお聞かせください。
鄭社長:販売流通のパイは小さくなります。自動車販売に関しては、さまざまなプレイヤーがいますが、それぞれの力でユーザーに安心できることを訴求していくことが大事です。自動車の文化の進化はいろいろな曲面から見ないといけません。産業全体がハードからソフトへと軸足を移したのと同じことが自動車に関しても起こるでしょう。自動車は他の工業製品に比べてソフトが足りず、メカに頼りすぎたということも言えるのではないでしょうか。
---:自動車の使い方も変わっています。ビジネスチャンスになりそうでしょうか。
鄭社長:これからは「このクルマじゃなきゃ購入しない」といった自動車そのもの、ハードに対するという要求より、「クルマを買って○○をやってみたい」という、ユーザーの経験欲求、ソフト面への要求が拡大するでしょう。当社では、残価ローンや、低金利ローンなどのサービスを実施してきましたが、これらはすべて「売り」の時に活用されるものなのです。この「売り」以外の場面で需要を創出することが成熟した日本の自動車市場では重要になってゆくと思います。一方、例えば中国市場では、ユーザーはとにかく自動車を持ちたい、と考えていますね。ユーザーの特徴を捉えるマーケティングを行うことが大切ではないでしょうか。
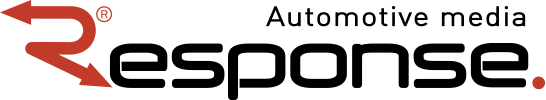






![変化するクルマの価値軸に日本メーカーはどう向き合うか…スズキマンジ事務所 代表 鈴木万治氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2158796.jpg)


