電気自動車(EV)元年といわれた2010年が過ぎた。EVを含む環境対応車を巡り、激しい競争の幕が開けた。
こうしたなか、CO2削減の観点からコンバージョンEV(中古の市販車両のエンジンを燃料タンクとモーターや電池に置き換えた車両)普及の必要性を説いているのが東京大学総長室アドバイザーの村沢義久氏だ。村沢氏は、地方の整備工場やEVパーツメーカーらとともにコンバージョンEVの普及をめざす『スモール・ハンドレッド活動』を推進している。コンバージョンEV普及のロードマップやビジネスの可能性について、村沢氏に聞いた。
◆コンバージョンEVの価値を裏付けるCO2削減
---村沢さんがコンバージョンEV事業を提唱しはじめたきっかけを教えてください。
村沢:サスティナビリティが專門である私がコンバージョンEV事業を推奨している目的は、CO2削減です。 国内市場には四輪のみでも車両が7500万台ほどあります。新車市場でEVが販売されても、CO2を排出する既存車両の数の方が圧倒的に多い。この既存車両の存在は無視できません。いかに街中を走る車両をEV化し、CO2排出量を減らすか。これは大きな問題です。
---コンバージョンEVビジネスは拡大すると思われますか。
村沢:新規事業を立ち上げるときに一般に確認すべきことはまず、その事業に「価値があるのか」。そして製品、サービスの「供給能力はあるのか」。最後に「ニーズがあるのか」という3点を把握しなければなりません。このなかで、本来一番大事なのは「ニーズがあるのか」です。しかし、コンバージョンEVに関しては、「価値があるのか」というところからスタートしています。この「価値」こそが先に述べたCO2削減ですが、世界的な合意として2009年のG8ラクイラサミットで、「2050年までに2005年比で温室効果ガスを80%削減する」という目標が設定されました。2050年までに80%削減を達成するには、車齢を考慮して逆算すると、2035年ころまでに新車はすべてゼロエミッション車でなければならない。これを実現するのは大変なことですが、併せて既存車両のEV化を進めなければこの目標はますます遠くなります。
◆コンバージョンEV年産100万台までは10年以上
---「供給能力」についてはいかがでしょうか。
村沢:供給能力に関しては、コンバージョンの拠点となり得るのは主にガソリンスタンド、自動車整備業者、自動車部品事業者などです。これらの事業者を合計すると、ざっと見積もっても10~20万店舗に上ります。供給拠点の予備軍がそれだけあるということです。このうち、1万店舗が拠点になるとしましょう。ひとつの自動車整備工場で車両1台をEVにするために2~3日かかるとすれば年間100台。年間100台のコンバージョンEVを生産できる拠点が1万存在すれば、コンバージョンEVは、年間で合計100万台生産できる計算です。この規模までは10年以上かかると考えています。
---一方でここ数年のコンバージョンEV市場はどのように成長すると予測していますか。
村沢: 2009年までに車検を通過したコンバージョンEVは約100台です。2010年に新たに約100台の生産が行われ、国内には現在、累計200台ほどのコンバージョンEVが存在します。2011年にはここから1000台積み上げることが目標です。幸い、拠点になるための初期投資はほとんどかかりません。整備業者などが「その気になった」時点で拠点は出来上がります。拠点数がどの程度のスピードで増えるかは、啓蒙活動や自治体レベルの働きかけによって変わります。
---コンバージョンEV事業着手への啓蒙活動に取り組んでおられますが、手応えはいかがですか。
村沢:コンバージョンEVに取り組もうと考える事業者は加速度的に増えています。私自身、地域で講演や、現場の整備工場の方とのコミュニケーションを通じて、コンバージョンEV事業の価値や可能性を伝える取り組みを続けています。このインタビューの直前にも、コンバージョンEV関連で整備事業車の方と連絡をとっていました。コンバージョンEVに取り組んでいる事業者に対しての問い合わせは急激に増えています。私の実感ですが、1年前ころは、コンバージョンEVに関して講演を行うと、参加者の皆さんは「考えてみよう」という感じに留まっていました。これが2010年の夏ころから変わってきました。講演後「コンバージョンEV事業をやります」という事業者が1回の講演につき2事業者くらいは現れるようになりましたね。今は1講演につき、5~6事業者が具体的な行動を起こすようになっています。地域によって、コンバージョンEV事業への取り組み強度は違いがありますが、愛媛県、静岡県が積極的な動きを見せています。こうした『スモール・ハンドレッド活動』は継続的に行っていきます。
◆「暖簾分け効果」「改造キット」…新しいかたち
---コンバージョンEV事業への着手を決めた事業者は、どのような方法でビジネスを立ち上げていくのでしょうか。
村沢:コンバージョンEVをつくるには、まずは技術を習得しなければなりません。これに関してはいま「暖簾分け効果」というような現象が起きています。例えば技術を持つ事業者が仲間に声をかけて、公開のもと1台の中古車をEVに改造します。そうすると、自動車整備業者が20社ほど集まる。そこでコンバージョン技術の伝達が行われます。お互いに議論し教え合い、各社は技術を持ち帰って熟成させる、という形で浸透しています。コンバージョンEVは、ベースとなる車両はさまざまな状況にあり、地域特性や使用目的によってゴールは違います。技術の囲い込みよりも共有がお互いの利益になるのです。
---自動車整備工場などが、より簡単にコンバージョンEVを作れるような「改造キット」を販売するようなビジネスが育ってゆくのでしょうか。
まず、改造には電池やモーター、インバーターといった部品が必要になる。国産品だけでなく海外からもまとめて輸入して単価を下げるような商社的ビジネスは成り立つでしょう。そのうえで、これらの部品をパッケージ化した「改造キット」を量産し、販売するという新しい事業も成立すると思います。実際にそれを目指す企業はすでに存在します。現状ではキットを販売する企業が技術も伝播させているようです。しかし、技術を得た企業はキットの購入だけでなく自社の技術や使用目的に合わせた独自のキットを用意するところもあります。中古車の車種や状態が千差万別であるかぎり、あくまで改造キットは半完成品でこれを買ってマニュアル通り改造するとEVができあがるというインスタントなものではありません。
◆コンバージョンEVは21世紀型のモノづくり
---たとえば自動車整備工場にとって、コンバージョンEV事業が新たなビジネスの柱に成り得ますか。
コンバージョンEVを生産するには、平均して1台につき100万円くらいかかるのではないでしょうか。そのうち部品代は約半分程度です。一方で地方の経済、地方の雇用は年々厳しさを増しています。いま、ガソリンスタンドが次々に閉鎖しています。ハイブリッドカーやEVが増えるにつれ自動車整備工場も厳しい競争にさらされます。数人が働く工場でひとり、またひとりと辞めていってもらわねばならないような地方で、コンバージョンEV事業はカロリーたっぷりのごちそうではないかもしれませんが、雇用をつなぎとめる美味しい「麦めし」に成り得ます。
---コンバージョンにかかる金額などがニーズを左右する要素になりそうです。
村沢:コンバージョンEVにかかるコストが平均100万円程度とはいえ、実際は一物一価です。良いものを作り込んで完成品として提供するのが20世紀のモノづくりだとすれば、21世紀のモノづくりは、ニーズを満たすことがすべてです。一物一価のコンバージョンEV事業は、既存の技術、部品、汎用の電池やモーターで成り立ちます。ニーズにあった車体で、ニーズにあった性能のEVを作ることができるコンバージョンEVは地域や用途にあったEVを提供できます。こなれた事業資源を組み合わせ、ニーズを吸収できる価格で製品を作る。これこそが21世紀の工業の形といえるのではないでしょうか。
(インタビュアー:三浦 和也、文責:土屋 篤司)
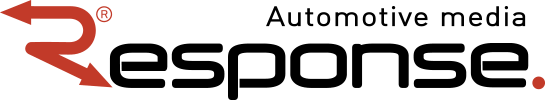












![全国へ広がる自動運転バス事業、100万台市場へ向けた新ビジネスモデルとファンド構想…BOLDLY 佐治友基CEO[インタビュー]](/imgs/sq_l1/2109198.jpg)


