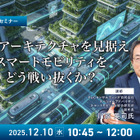日本は世界的に見ても、観光資源が豊富な国だと思っている。四方を海に囲まれ、山がちな島国ということで多様な風景を持っているし、四季の移ろいでその風景が何通りにも変化していく。加えて国としての歴史が長いので、いにしえの建造物も多い。
人口減少が続き、目立った産業にも恵まれない地方にとっては、観光は地域活性化の点でも重要である。ゆえに昔から旅行会社などがさまざまなパッケージツアーを用意してきたが、デジタル化が進む今、それがMaaSに進化している事例もいくつかある。ここでは首都圏周辺の観光地として有名な静岡県伊豆、神奈川県箱根、栃木県日光の3ヶ所について、交通事業者が主体となって展開したMaaSの実例を紹介していきたい。
同業他社が手を組む伊豆
まずは伊豆から話を進めていく。ここはいまや全国各地で見ることができる「観光型MaaS」を最初に導入した地域でもある。日本初であることはもちろん、世界初の観光型MaaSでもある。日本の公共交通は、多くの民間事業者が競合する状況が一般的で、ゆえに昔から、交通事業者が観光事業を積極的に手掛ける理由のひとつになってきた。こうした流れを考えれば、観光型MaaSが日本から出たのは当然と言えるかもしれない。
伊豆の場合は東京急行電鉄(現東急)とJR東日本(東日本旅客鉄道)が共同でプロジェクトを進めたもので、地域によってはライバル関係にもなる2社が手を組んだ点も特筆すべきものだった。名称は「Izuko」で、2018年に発表後、翌年から3期にわたり実証実験を重ねた。観光型MaaS誕生の発端は、東急とJR東日本、楽天3社の会長の会談だったという。地方の二次交通は弱体化しており、地方活性化のためにも、MaaSを考えなければならないという内容だったそうだ。
東急では未来を見据えた新規事業を手掛ける部署としてプロジェクト推進部を新設し、MaaSの開発を始めた。MaaS誕生の地であるフィンランドの関係者に接触し、現地視察を行ったところ、デンマークのコペンハーゲンで行われた第25回ITS世界会議で発表の機会を与えられ、多くのモビリティ関係者から注目されたという。伊豆を選んだ理由について東急では、この地で鉄道を走らせている伊豆急ホールディングスがグループ会社であり、東急ホテルズも宿泊などの事業を手掛けていることを挙げた。一方のJR東日本も伊東線を走らせているうえに、東伊豆は東京からの観光客が90%以上とのことで、アクセスルートとしても重視していた。