「交通事故に抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会」の速度規制等ワーキンググループ(WG長=東京大学・太田勝敏名誉教授)第1回会合(8月30日)で、警察庁が規制管理の必要性を強調した。
2012年の交通事故件数についてシミュレーションを行い、規制速度超過の事故は、規制速度内の事故の約12倍の死亡事故率であり、規制超過がなければ、死亡事故全体の約30%(1181件)が死亡事故にいたらかなったとした。
警察庁は09年10月に新たな速度規制基準を導入。通行機能を重視した構造の道路では70・80km/hが可能とする一方、生活道路は原則30km/hのメリハリある規制速度に改めた。
新しい基準で見直しをした1911区間の前後1年間の交通事故の増減の比較も明らかにした。
これによると、規制速度を引き上げた1793区間中、事故が減少した区間498(27.8%)、増加した区間は519(28.9%)だった。反対に規制速度を引き下げた117区間中、事故が減少した区間は33(28.2%)、増加した区間は34(29.1%)。見直しによる規制速度の変化は、事故増減効果は明確には示してはくれなかった。
今後、速度規制の見直しを進めるためには、標識や表示の設置や撤去に予算が必要なことなどから、警察庁交通局は優先順位をつけた計画的な取り組みが必要であるとした。
また、取り締まりのしにくい生活道路では、速度を下げさせるための道路の凹凸(ハンプ)などの設置や、カーナビ、ITS活用も考えられるとした。
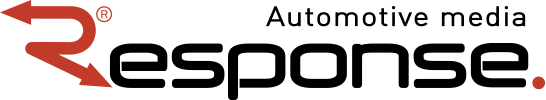


![「ながらスマホ」は即、反則金…警察庁、自転車の「青切符」導入前に「ルールブック」作成[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2140313.jpg)
