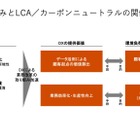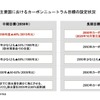現在、自動車・モビリティ産業において、Connected(コネクティッド)、Autonomous/Automated(自動化)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化)といった「CASE」と呼ばれる新しい領域で技術やビジネスモデルの変革が進んでいる。
さらに、サステナビリティの観点からLife Cycle Assessment(以下「LCA」)への関心も高まっている。「LCAが変える自動車の未来」を取り上げる本連載では、重要性が高まるLCAに業界としてどのように対応していくべきか、バリューチェーンやそれを支えるインフラにおける論点を考察したい。
第1回は、先行するEUにおけるLCA導入までの背景や現在の対応を事例に、各バリューチェーンにおける課題や対応について概観する。
LCAの潮流
現在、120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標に合意するなど、気候変動問題は地球規模の課題となっており、世界でカーボンニュートラルに向けた取り組みが加速していることで、LCAに対する注目はますます高まっている。自動車業界でも、環境負荷低減の観点からLCAの重要性が認識され、自動車のライフサイクル全般において責任ある対応が求められると同時に、ビジネス機会の探求が課題となっている。
そのような中、EUでは、電動車両の主要な要素であり、製造段階におけるCO2排出量の多くを占める電池を対象としたLCAの制度化が先行している。2020年12月に欧州委員会が公表した「欧州電池規則案」では、2024年7月1日よりEUで市販される特定の産業用・電気自動車用二次電池について、「カーボンフットプリント宣言」が義務付けられるなど、その動きは加速している。
では、なぜEUは電動車用電池などの自動車製品LCAの制度化に先行して取り組む必要があったのか。背景には、エネルギーセキュリティも含む国家安全保障上の必要性があったと考えられる。現在でもEUの化石燃料への依存は7割以上となっており、そのほとんどを輸入に依存していることで、EU各国は、自動車の利用が拡大するほどに、域外産油国への利益流出や域外依存リスクを高めてしまうジレンマを抱えてきた。
厳しい環境規制や自動車の燃費規制を敷くことで、EU各国は燃費の改善に取り組んできたが、その背景には化石燃料の消費量を減らすことで域外の産油国への依存を軽減するといった目的があった。しかし、自動車業界にとっての大きな負荷である厳しい燃費規制を以てしても、化石燃料消費をゼロにすることはできない。そこで、気候変動問題への対応という喫緊の政策課題への取り組みと歩調をあわせることで、EUは自動車の電動化・BEV(Battery Electric Vehicle)化を一気に推進してきた。
自動車の電動化・BEV化により、化石燃料の域外依存からの脱却というエネルギーセキュリティの課題解決への道筋が見えた一方、今度は電動化車両の価値の多くを占める電池を域外依存する可能性が生じた。こういった懸念が、自動車の電動化の加速とともに高まり、電池サプライチェーンの確保や輸送に伴うコスト増加への対応、品質管理の脆弱性や商品デザインの限定、域外依存の地政学的リスクを踏まえたEU域内における独自の電池供給体制確立の必要性を喚起することになる。
そこでEUでは、環境政策と産業政策をバンドリングすることで、製造工程におけるエネルギー消費量の大きな電池に、気候変動問題への対応を呼応させ、再エネ比率の高い欧州域内での製造を促進するとともに、リサイクルを通じた資源の域内循環・都市鉱山化を加速することで資源国への依存を低減するという、サプライチェーンの域内化を図る欧州電池規則の策定に取り組んだのである。
この改正法により、産業政策、環境政策、エネルギー政策を統合し、域外依存リスクを低減しながら産業の発展を図るシナリオが描かれ、産油国依存からの脱却後も、EV(Electric Vehicle:電気自動車)の付加価値の域外依存回避を実現させることができると期待されている。エネルギーや資源の安全保障に関して、類似の課題を抱える日本においてもEUの戦略は大きな示唆となる。




![中国EVメーカー、驚異の“マイナスCCC”経営…矢野経済研究所 西村玄 氏[インタビュー]](/imgs/sq_l1/2161533.jpg)


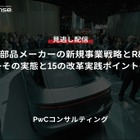
![改革に近道なし、だからこそ必要な部品メーカーのイノベーションと付加価値創出のポイント[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2144605.jpg)