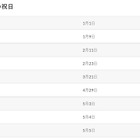2014年1月17日、国立天文台は大阪大学と茨城大学の研究者を中心とする研究チームがアルマ望遠鏡の観測により、親星から遥か遠く離れた場所で惑星が誕生しつつある強い証拠を初めてとらえたと発表した。
研究チームが南米・チリの国際天文施設、アルマ望遠鏡(ALMA:アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計)によりおおかみ座の方向にある「HD 142527」と呼ばれる若い星を観測したところ、惑星の材料となる固体微粒子(直径0.1マイクロメートルほどの微粒子。星間塵やダストとも呼ばれる)が星の周囲で非対称なリング状に分布している様子が確認された。固体微粒子が最も濃く集まった領域の密度を測定した結果、この場所で惑星が生成しつつある可能性が高いことが分かった。中心の親星からこの高密度領域まで、太陽から海王星までのおよそ5倍にも相当する距離があり、これほどの遠方で惑星が形成しつつある証拠が見つかったのは、初めてだという。
研究チームは、すばる望遠鏡を使ってHD 142527をとり囲む円盤には星の近くと外側をへだてる溝(すきま)が存在することや、外側の円盤が奇妙な形をしていることを発見していた。そこでアルマ望遠鏡を向ける天体としてこの星を選定。固体微粒子から放射されるサブミリ波の分布を確認したところ、明るい北側と暗い南側とでは約30倍もの違いがあったという。
研究チームを率いる大阪大学の深川美里助教によれば「サブミリ波で最も明るい領域は中心の親星から遠い場所にあり、その距離は海王星と太陽との距離のおよそ5倍にもなります。親星からこれほど離れた場所で、こんなにも明るく光る円盤は見たことがありません。明るいということは、サブミリ波を出す大量の物質がそこに集まっている、ということを意味します。十分な量の物質が寄り集まれば、惑星や彗星など、新たな天体が誕生する可能性があります。そこで私たちは、実際にどれほどの量の物質が存在するのかを調べました」という。
研究チームが高密度領域での固体微粒子の量を推定したところ、ふたつの可能性があることがわかった。ひとつは、固体微粒子が自分自身の重力(自己重力)で急激に周りの物質をかき集めて、木星の数倍もある巨大なガス惑星を作れるほど非常に重い可能性。また、固体微粒子が局所的に濃集し、岩石惑星や彗星などの小天体、さらにはガス惑星の中心核の形成が促進されている可能性だ。どちらの場合でも、新しい惑星の形成が進行していると考えられる。
今後、研究チームはアルマ望遠鏡での詳細な観測を続けてガスの量の測定などを行う。深川助教は「私たちの非常に限られた知識に照らせば、HD142527は特異な天体です。しかしアルマ望遠鏡が稼働してすぐに、この天体以外にも強い非対称性を示す円盤が見つかり始めました。最終的に知りたいのは、惑星誕生をコントロールする主要な物理過程が何であるか、です。そのためには、アルマ望遠鏡で多数の原始惑星系円盤を観測し、全体像を得ることも重要です。私たちもそれに加担していければと考えています」としている。