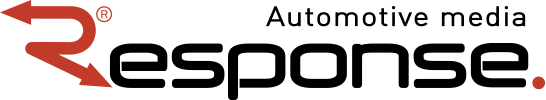実在しないアメリカの自動車団体名義とする偽造の国際免許証を発行し、国内で販売していたとして有印私文書偽造罪に問われた男に対して東京高裁は9日、一審の東京地裁が判断した無罪判決を支持し、検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。
発端となる事件は2001年5月に起きている。東京都内で交通事故を起こし、警察に逮捕された男が偽の国際運転免許証を持っていることが発覚した。アメリカの架空の自動車団体名義で発行された同じ書式の偽造免許証が1999年秋ごろから東京都や埼玉県内で数多く出回っていたことから、当初はこの男が偽造免許証を購入して使用していたものと思われていた。ところが後の調べでこの男が免許証の偽造と販売そのものに関わっていたことが明らかになった。
アメリカに在住するこの男の弟が現地で偽造したものを日本 国内で販売する仕組みだったが、この弟は兄以外の人物にも偽造免許証を卸していたことが発覚。2000年秋ごろから週刊誌やインターネット上に「簡単に国際免許証が取得できます」と広告を出していた当時56歳の男が別ルートでの販売に関与していることもわかり、2001年6月に有印私文書偽造、偽造有印私文書行使などの疑いで逮捕していた。
しかし、別の販売ルートを指揮しているとして逮捕された男は「免許証はアメリカのカリフォルニア州で現地の発行団体に勤務する人物から買い付けたが、それが偽造免許証だとは知らなかった」と一貫して主張。販売の事実は認めたものの、有印私文書偽造については断固否定した。
男は有印私文書偽造の罪で起訴されたが、公判の際にも「偽造とは知らなかった」という主張を繰り返した。検察側は男が偽造の事実を知りながら販売していたという筋書きで訴訟を進行させたが、一審の東京地裁判決は意外なものだった。
実は男が雑誌広告に載せていたアメリカの国際免許証は根本の部分で書式が間違っていたことが後に判明。「本物の免許証を知っていて、それを元に偽造しているというのなら、書式が明らかに違う杜撰なものを広告には掲載しないだろう」と裁判官は判断。根本的な間違いに気づかなかったということは、被告が一貫して主張してきた「偽造とは知らなかった」という発言を裏付けるということにもなる。
また、本物とは書式が明らかに違うものであれば、本物そっくりの偽造物を作り出したとは見なされず、したがって有印私文書偽造の罪には問えないとして無罪を言い渡した。これに対して検察側は不服を表明、東京高裁に控訴を申し立てていた。
9日の判決で東京高裁の原田国男裁判長は「被告は雑誌の宣伝広告も実名で掲載させている。犯罪の要素があると自覚していたのであればそのような行動は取らないものと考えるのが自然であり、販売物の免許証が偽造だということを知っていたなら、通常ではありえない行動をしたということになる。この点からも被告は販売物が偽造されたものではないと確信していた証拠になり、犯意は無かったという結論に達する」として一審の東京地裁判決を支持。検察側の控訴を棄却した。