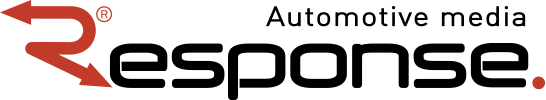前回北関東の2つの県庁所在地、栃木県宇都宮市と群馬県前橋市を取り上げた際に、北関東は日本の中でも自動車の普及率が高いことを紹介した。今回紹介する北陸地方も似た環境にある。
自動車検査登録情報協会が発表した、都道府県別の自家用乗用車の普及状況 (軽自動車を含む・平成29年3月現在)で1世帯あたりの台数を見ると、1人あたりのそれとは順位が異なり、1位が福井県、2位が富山県、3位が山形県で、北関東3県は4~6位となっている。福井県と富山県は、ともに持ち家率が高い。総務省統計局の平成30年住宅・土地統計調査では、富山県が2位、福井県が4位に入っている。これも世帯あたりの自動車台数の多さにつながっているのかもしれない。
北陸地方の公共交通改革
しかしながら北陸地方は、公共交通改革の先進地域でもある。たとえば富山市は2006年、JR西日本(西日本旅客鉄道)富山港線を、我が国初の本格的LRTに生まれ変わらせた都市として知られている。
2002年に市長に就任した森雅志氏が、次の年に「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を打ち出し、公共交通の活性化、公共交通沿線地区への居住推進、そして中心市街地の活性化という3本柱を掲げた。コンパクトシティを目指した理由のひとつに行政サービスがあった。冬季の積雪が多い中で住居が拡散していくと、税収は減るのに除雪費用は変わらないということになる。ゆえに地域拠点に人を集め、拠点間を質の高い公共交通で結ぶという指針を示した。その象徴がLRTだった。
LRT化を選択した理由として、それ以前から駅の反対側を走っていた富山地方鉄道富山軌道線(通称市内電車)との接続もあった。こちらでは中心市街地の活性化のために、一度は廃止された市内電車環状線の復活を実現し、2020年に南北直通運転が実現している。

別の理由で公共交通改革に乗り出したのが、福井市を中心とする福井県嶺北地方だ。この地域には以前からJR西日本以外に、京福電気鉄道と福井鉄道が鉄軌道を運行していたが、京福電鉄が2000年、2001年と2年連続で正面衝突事故を起こしたことを受け、国土交通省から運行停止や事業改善が命じられた。