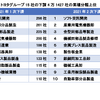自動車産業が現在直面している技術革新は、確かに自動車産業が成立してからの「100年に一度の変革」をもたらすが、同時に近代資本主義社会を支える産業技術体系変革の一局面と捉える必要がある。
◆自動車産業における技術革新と産業構造の変化
近代資本主義の動力基盤は過熱、気化による体積膨張圧力を動力に使う熱機関にあるが、その利用形態により時代は区分される。第一段階となる19世紀には、蒸気エンジンを利用した船舶や鉄道、工場生産が成立した。第二段階は20世紀、蒸気エンジンと発電機を組み合わせ、送電による中央発電所方式が確立し、トランスファーマシンとベルトコンベアによる工場生産や内燃機関と電気機器による自動車の発明と家庭での電力消費は拡大していった。
第三段階である21世紀は、熱機関の時代から直接発電の時代への過渡期にあると考えられる。燃料電池や核融合、再生可能エネルギー、電池の開発、動力用モーターの開発、これらの全体を制御する各種制御システムの開発、動力と制御のあらゆる分野での新体系創出への試みが行われる過渡期だ。重要なのは、この変化は単に産業技術の転換だけでなく、生産における労働の役割、社会における交通形態にも求めており、それは近代社会の次に来る新しい社会の在り方に関わっている。
この変化の一端を端的に表しているのは、自動車に搭載される車載用ソフトウェアの巨大化である。一昔前には1000万行というレベルだった車載用ソフトウェアは、今やベンツのモデルで6700万行、新規開発のモデルでは1億行に達しており、最終的な車載用ソフトウェアは6億行に達すると考えられている。
自動運転システムでは、車載用ソフトウェアを搭載した車両同士が5Gなどの高速通信を通じてお互いに情報を交換し合い、相互に安全な交通を行う様に判断することが想定されている。この様なソフトウェアを搭載する場合には、安定性と信頼性が現在のシステムとは比較にならないほど高める必要があり、さらに、仮にシステムダウンした場合には即座に代替回路でバックアップできることが社会システムにおいても確保されていなければならない。
いずれにせよ、F-104戦闘機で2400万行、Microsoft Officeで4800万行と言われるソフトウェアの規模に対して、自動運転システムの巨大さは目をみはるものがある。果たしてこれほど巨大なシステムの搭載が本当に必要なのか、議論すべきであることは言うまでもない。