JR西日本は2月3日、大糸線南小谷(みなみおたり)~糸魚川間について、3月から「持続可能な路線としての方策について幅広い議論」を行なうことを明らかにした。
同区間は、日本海へ注ぐ姫川に沿って長野県と新潟県の境を越える山岳線区で、2010年までは国鉄型一般型気動車キハ52形が運用されていたことで、マニアの間では人気を呼んでいた。
しかし、元来、人口が希薄だった沿線は近年、急激に過疎化が進んでおり、南小谷~糸魚川間の輸送密度はJR西日本が発足した1987年度が987人であったのに対して、2020年度は50人にまで落ち込んでいる。
これはピークだった1992年度と比べて9割以上も減少した数字で、JR西日本では芸備線東城(とうじょう)~備後落合間の9人、木次線出雲横田~備後落合間の18人に次いで3番目に悪い数字。年間の旅客運輸収入はJR西日本でワースト1となる1000万円となっている。
ちなみに輸送密度50人は、廃止容認報道が流れているJR北海道の根室本線富良野~新得間(57人)や、2021年4月に廃止された日高本線鵡川~様似間(95人)よりも少ない。この2線区は旅客運輸収入でも南小谷~糸魚川間を上回っている。
この状況を受けてJR西日本では「地域の現状、公共交通の概況、ご利用状況、移動特性、沿線住民ニーズ等を共有し、地域の振興や未来に資する持続可能な路線としての方策」を地元と幅広く議論していくとしているが、一部報道では廃止を視野に入れたものであると言われている。
 姫川沿いを北上する下り列車。2007年6月23日。
姫川沿いを北上する下り列車。2007年6月23日。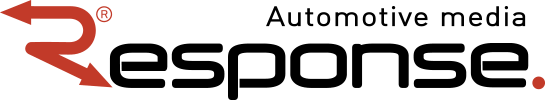







![新幹線も走る「エンタメ空間」を演出へ、JR東日本と松竹が提携[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_l1/2059473.jpg)
![トヨタ時価総額48兆7981億円---バブル期のNTT超え日本企業で過去最大、世界では28位[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/1973566.jpg)



