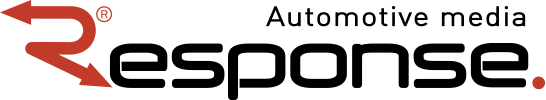徳島県警は5日、今月末を目標に1800人の全職員を対象としたアルコール体質検査を行うことを決めた。アルコールの分解能力を測定するバッチテストを実施し、酒に強いと自覚しやすい職員をピックアップする狙いがあるという。
これは警察官による飲酒運転絡みの事故が相次ぐ徳島県警が綱紀粛正の一環として決めたもの。腕にエタノールを垂らし、赤く変色するまでの時間でアルコール耐性を判定するバッチテストを1800人の全職員を対象に実施。アルコールに強い職員をピックアップし、飲酒運転防止に向けた指導を徹底させていく。
飲酒運転を行いやすい人というのは、体質的にアルコールに強く(分解しやすく)、そのために「酔った」という感覚を得られにくい人(酩酊感の弱い人)が行う可能性が高い。こうした人は酔ったという感じがしないため、血中アルコール濃度がピークを迎える時間に運転を行い、事故に至るケースも多い。
徳島県警では、2002年4月に徳島東署の巡査部長が飲酒運転の末に人身事故を起こしている。この際には呼気1リットルあたり0.15ミリグラムのアルコール濃度が検出されている。現行の道路交通法では酒気帯び運転とみなされる量だが、この際には飲酒運転とはみなされず、県警も事故を起こした警官の実名報道を見送るという決定を行った。この措置に県民が猛反発して、後に停職1カ月の懲戒処分が実施されたという経緯もある。また、飲酒運転ではないが、2002年10月には県警本部所属の警察官が泥酔状態でタクシー運転手を暴行するという事件を起こし、辞職するという騒ぎも起こっている。
県警では「体質的に酔ったことがわからない人には、自分がそういうタイプであるということをしっかりと告知し、本人の理性で抑えてもらうしかない」としている。ただ、こうした検査を全職員に対して行ったという例は全国的にも珍しく、体質によって左右するものを強制検査でピックアップするという行為が人権侵害につながるのではないかと危惧する見方もある。