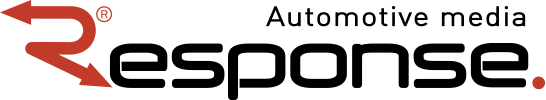過去の違反歴から免許証更新時に有効期間を3年間とされた千葉県在住の男性が、千葉県公安委員会を相手に行政処分の取り消しと、それによる免許証の有効期間変更を求めた行政訴訟の控訴審判決公判が26日、東京高裁で開かれた。裁判所は男性の請求を認めた一審の千葉地裁判決を破棄。請求を棄却している。
判決によると、この男性は1998年11月28日夜、千葉県四街道市内の市道交差点で出会い頭の衝突事故を起こし、相手側の男性に全治約2週間の軽傷を負わせて道路交通法違反(安全運転義務違反)での処分を受けた。これが累積4点の事故歴として記録され、男性は2000年の運転免許更新時に違反者講習を受けた。
その後、2002年6月の法改正によって免許区分が細分化され、優良運転者として有効期間5年の免許(いわゆるゴールド免許)の交付を受けるためには「免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前を基準日として、その前5年間を無事故無違反であること」という条件が課せられた。男性が2003年に免許を更新を申請した際には、1998年に起こした事故が「誕生日の40日前基準」に該当。違反歴があるとみなされ、男性は違反者講習の受講が要求されるとともに、違反者区分として免許証の有効期間も3年となった。
1回の事故で2度の違反者講習を受けることを強いられ、免許証の有効期間も短縮されたことを不服とした男性は「運転免許証の有効期間は原則5年であり、それは運転する権利として法律上保護されている」と主張するとともに、「2000年の更新時に違反者として扱われており、同じ事故で2度の同等処分を受けるのは憲法で定められた一事不再理の原則に反する」として行政訴訟を提訴した。
一審の千葉地裁は今年4月、「5年間の有効期間は法によって保護された利益であり、不利益を被った場合は取消訴訟によって利益の回復を求めることができる」と認定。その上で「公安委員会は被告に対して不利益な処分を行う理由を示しておらず、行政手続法に反する」として男性の訴えを認め、免許証期間を3年とする処分の取り消しを命じた。しかし、被告の公安委員会側はこれを不服として控訴していた。
26日に開かれた控訴審判決で、東京高裁の赤塚信雄裁判長は「現行の運転免許制度は“一定要件を備えた者に運転を許す制度”であり、その一定要件上に運転者の区分がある」とした上で、「免許の更新時に申請者が制度によって何らかの制限を受けたとしても、運転する権利を制限する不利益な処分に当たるとはいえず、従って制限理由の提示義務もなく、行政手続法には反しない」と判断した。さらに「一事不再理の原則は刑事上の責任に関するもので、行政処分たる運転免許証の更新には適用されない」とも判断して、一審の千葉地裁判決を破棄。男性の訴えを退けた。