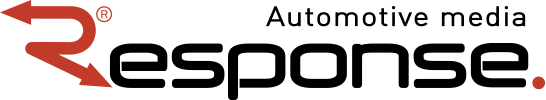脂肪滴の動態解析により疾患理解、診断・治療法開発に貢献
2025年10月10日
名古屋大学
岐阜大学
細胞内の脂質代謝を可視化する蛍光プローブを開発 ~脂肪滴の動態解析により疾患理解、診断・治療法開発に貢献~
本研究のポイント
・脂肪滴(注1)で脂質の加水分解が進行すると蛍光寿命が変化する蛍光プローブ(特定の物質や化学反応を蛍光として検知できる分子)を開発し、この特性を利用して脂質代謝を解析する新たな技術を確立した。
・肝臓がん細胞では、脂肪滴ごとに加水分解活性が不均一であることを見いだし、その違いは中性脂肪を分解する酵素(ATGL(注2))に起因することを明らかにした。
・脂肪滴選択的なオートファジー(リポファジー(注3))は、加水分解が進行した脂肪滴に対して起こることを明らかにした。
研究概要
名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM※)・学際統合物質科学研究機構(IRCCS※)の山口 茂弘 教授、岐阜大学糖鎖生命コア研究所(iGCORE※)の多喜 正泰 教授らの研究グループは、脂肪滴に特異的に局在する環境応答型蛍光プローブを開発し、脂質の加水分解の進行度を蛍光寿命の違いとして可視化する新たな解析技術を確立しました。
脂質代謝異常は、がん、糖尿病、肥満、動脈硬化など多様な疾患と密接に関連しています。脂質を蓄積する脂肪滴は、脂質代謝の中核を担う細胞内小器官(オルガネラ)であり、その動態を明らかにすることは疾患の理解に不可欠です。蛍光イメージングは脂肪滴動態の解析において強力な手法であり、脂肪滴を染色する蛍光プローブはこれまでも多く開発されてきました。しかし、これらは主として脂肪滴の大きさや挙動を可視化するにとどまり、脂肪滴内部における脂質の代謝状態をリアルタイムに捉えることは困難でした。
今回開発したプローブは、脂肪滴の主要構成脂質であるトリグリセリド(TAG)(注4)と、TAGが加水分解されて生成するジグリセリド(DAG)(注5)の割合に応じて蛍光寿命が変化する特性を示します。肝臓がん細胞内の脂肪滴を標識し、蛍光寿命イメージング顕微鏡(FLIM)(注6)で観察したところ、蛍光寿命に不均一性が認められ、脂肪滴ごとに加水分解の進行度が異なることを明らかにしました。さらに本技術を活用することで、脂肪滴選択的オートファジー(リポファジー)に先行して脂肪滴分解リパーゼによる脂肪分解(リポリシス(注7))が起こることを解明しました。
本研究成果は、2025年10月9日21時(日本時間)に米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」オンライン版に掲載されました。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510086756-O11-QkqO2oQ6】
研究背景と内容
脂質は生物の生命活動に欠かせないエネルギー源であるだけでなく、細胞膜の構成要素やシグナル伝達分子としても重要な役割を果たしています。細胞内での脂質代謝が乱れると、がん、糖尿病、肥満、動脈硬化といった生活習慣病や重篤な疾患に直結することが知られています。脂質代謝は複数の細胞小器官(オルガネラ)が互いに連携し、これらが協調的に機能することで維持されていますが、その中心的な役割を担うのが「脂肪滴」(図1a)です。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510086756-O14-N9tJOG3R】
脂肪滴の主成分の一つであるトリグリセリド(TAG)は、細胞のエネルギー需要に応じて分解され、脂肪酸を放出しながらジグリセリド(DAG)、モノグリセリド(MAG)、最終的にはグリセロールへと変換されます(図1b)。細胞内における脂肪滴の動態観察を可能にするためのツールとしてさまざまな蛍光プローブが開発されてきましたが、これらは脂肪滴の数や大きさを観察することはできても、「どの脂肪滴がいつ・どのように分解されるのか」といった代謝に関する時空間情報を得ることができませんでした。
研究チームではこれまでに、リン原子を導入して構造を強化した蛍光色素骨格を開発し、その極めて高い耐光性(超耐光性)と、周囲の極性環境に応じて蛍光特性が変化する環境応答性を利用し、ミトコンドリアの内膜を標識する蛍光プローブを報告してきました。今回研究チームは、この知見を基盤に、新しい脂肪滴蛍光プローブ「LipiPB Red」を開発しました(図2a)。この特性について評価するため、まずTAGであるトリオレイン(TO)とDAGであるジオレイン(DO)の構成割合を変えた人工脂肪滴を作製し、それぞれについて蛍光寿命イメージング顕微鏡(FLIM)を用いて解析しました。その結果、DAGの比率が高くなるほどプローブの蛍光寿命が短くなることが分かりました(図2b)。これは、DAGが極性の高いヒドロキシ基(−OH基、下図の赤丸部分)を含むためであり、LipiPB Redがその極性の違いを鋭敏に検知できることを示しています。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510086756-O13-4zSOGWkL】
図2.(a) LipiPB Redの構造と環境応答性。(b) LipiPB Redを用いた人工脂肪滴の蛍光寿命イメージング。
蛍光寿命を擬似カラーで表している。
次に、LipiPB Redによってさまざまな細胞種に含まれる脂肪滴を染色し、その様子をFLIMによって観察しました。その結果、肝臓がん細胞株であるHepG2細胞とHuh-7細胞中に存在する脂肪滴では蛍光寿命が一様ではなく、同じ細胞内であっても脂質組成に不均一性があることを発見しました(図3a)。興味深いことに、この不均一性は肝臓がん細胞特有の現象であり、HeLa細胞(ヒト子宮がん)やCOS-7細胞(サル腎)、脂肪細胞などでは認められませんでした。さらに、TAGからDAGへの加水分解を担うリパーゼであるATGLの活性を阻害したり、siRNAによってATGLの発現を抑制したりすると、この不均一性は消失(色が均一化)しました(図3b)。その際、DAG/TAG比の減少に伴う長い蛍光寿命が細胞全体で観察されたことから、ATGLが脂肪滴ごとの代謝状態の違いを生み出す鍵酵素であることが示唆されました。また、LipiPB Redで染色した脂肪細胞に対して脂肪分解を促進するフォルスコリン(注8)を投与し、その過程をFLIMで追跡したところ、脂肪滴サイズの縮小とともに、一様だった蛍光寿命が経時的に不均一になっていく(色の分布が広くなる)様子が観察されました(図3c)。これは、脂肪滴ごとに分解の進行度が異なることを示しています。このように長時間にわたり脂肪滴の動態を1細胞レベルで追跡できたのは、超耐光性を示すLipiPB Redの大きな利点の一つです。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510086756-O15-s31TU1si】
一方、脂肪滴の分解には、上記のようにTAGを段階的に加水分解する「リポリシス」に加え、脂肪滴を選択的に分解する「リポファジー」とよばれるオートファジー経路も存在します。オートファジー経路を可視化する分子マーカーであるRFP-GFP-LC3を用いて同時に観察したところ、脂肪滴がオートファゴソームに取り込まれる前の段階ですでにTAGの分解が進行していることが判明しました。これは、リポリシスとリポファジーが連携して働き、TAGの加水分解がある程度進んだ脂肪滴に対してオートファジーが起こることを示しており(図4)、脂質代謝の制御機構を理解するうえで重要な知見です。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510086756-O12-dFA4t9L5】
成果の意義
本成果の意義は、これまで数や大きさしか見ることができなかった脂肪滴について、超耐光性かつ環境応答性を備えた蛍光プローブを開発することにより、その「代謝状態」まで直接観察できるようになった点にあります。LipiPB RedとFLIMを組み合わせ、どの脂肪滴がどの程度分解されているのかを生きた細胞内でリアルタイムに解析することが可能になりました。
本成果は脂肪滴研究における新たな手法を提供するものであり、脂質代謝異常に起因する疾患の理解や診断・治療法の開発に向けても大きく貢献するものと期待されます。
付記
本成果は、以下の事業・共同利用研究施設による支援を受けて行われました。
科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 CREST(JPMJCR21O5)
研究プロジェクト「励起ダイナミクス制御に基づく光機能性ヘテロπ電子系の創製」
研究代表者 山口 茂弘
研究期間 2021年10月~2027年3月
日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤B(23H02105)
研究プロジェクト「生細胞1脂肪滴解析によるコレステロール輸送機構の解明」
研究代表者 多喜 正泰
研究期間 2023年4月~2026年3月
日本学術振興会 科学研究費補助金 学術変革領域研究(A)(25H01261)
研究プロジェクト「高度π分子体への環境応答性付与に基づく蛍光イメージングへの展開」
研究代表者 山口 茂弘
研究期間 2025年4月~2030年3月
日本学術振興会 科学研究費補助金 国際共同研究加速基金(22K21346)
研究プロジェクト「動的元素効果デザインによる未踏分子機能の探究」
研究代表者 山口 茂弘
研究期間 2022年12月~2029年3月
日本学術振興会 科学研究費補助金 学術変革領域研究(A)(24H02260)
研究プロジェクト「データ融合シミュレーションによるタンパク質の動的構造解析」
研究代表者 Florence Tama
研究期間 2024年4月~2029年3月
日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤B(24K02208)
研究プロジェクト「脂肪滴の細胞質および核内での生理機能解明」
研究代表者 大崎 雄樹
研究期間 2024年4月~2027年3月
日本学術振興会 科学研究費補助金 学術変革領域研究(22H04926)
研究プロジェクト「先端バイオイメージング支援プラットフォーム」
研究代表者 鍋倉 淳一
研究期間 2020年4月~2028年3月
上原記念生命科学財団 特定研究助成
研究プロジェクト「脂質代謝イメージングを用いた進行期卵巣癌の予後予測」
研究代表者 多喜 正泰
研究期間 2024年4月~2027年3月
武田科学振興財団
研究プロジェクト「脂肪滴による核内蛋白質機能制御機構の解明」
研究代表者 大崎 雄樹
研究期間 2022年8月~2027年5月
代謝異常治療研究基金
研究プロジェクト「核膜変形機構と核内脂質代謝の細胞老化への影響の解明」
研究代表者 大崎 雄樹
研究期間 2023年4月~2024年3月
風戸研究奨励会
研究プロジェクト「脂肪滴の核内での形成機構と生理機能の形態学的解析」
研究代表者 大崎 雄樹
研究期間 2023年4月~2025年3月
北海道B型肝炎訴訟オレンジ基金
研究プロジェクト「核内脂肪滴の肝疾患における意義」
研究代表者 大崎 雄樹
研究期間 2023年4月~2025年3月
用語説明
(注1) 脂肪滴:
トリグリセリドやコレステロールエステルなどの中性脂肪がリン脂質の単分子膜で囲まれた構造体。膜表面にはさまざまなタンパク質が存在しており、脂肪滴のサイズ調節や脂質代謝制御に重要な役割を担っている。
(注2) ATGL:
脂肪トリグリセリドリパーゼ。トリグリセリドをジグリセリドに加水分解する酵素。
(注3) リポファジー:
オートファジーによる脂肪滴分解。脂肪滴を含んだオートファゴソームがリソソームと融合することによって、分解が進行する。
(注4) トリグリセリド(TAG):
中性脂肪の一つで、1分子のグリセロールに3分子の脂肪酸がエステル結合した分子の総称。トリオレイン酸(TO)は3分子のオレイン酸が結合したもの。
(注5) ジグリセリド(DAG):
1分子のグリセロールに2分子の脂肪酸がエステル結合した分子の総称で一つの水酸基をもつ(例えばジオレイン酸(DO))。
(注6) 蛍光寿命イメージング顕微鏡(FLIM):
蛍光分子が光により励起されてから、蛍光を発してもとの状態に戻るまでの時間(蛍光寿命)を計測し、その値を擬似カラーとしてマッピングする方法。蛍光波長の強度による解析の欠点を補うイメージング手法として注目されている。
(注7) リポリシス:
ATGLやホルモン感受性リパーゼ(HSL)などの加水分解酵素の働きによる段階的なTAGの分解経路。
(注8) フォルスコリン:
コレウス・フォルスコリという植物の根に含まれる天然成分。サイクリックAMPの濃度を高める作用をもつ。
論文情報
雑誌名:Journal of the American Chemical Society
論文タイトル:Single-Cell Fluorescence Analysis of Lipid Droplet Compositional Dynamics during Triacylglycerol Catabolism
著者:Junwei Wang, Keiji Kajiwara, Manish Kesherwani, Florence Tama, Yuki Ohsaki, Shigehiro Yamaguchi*, Masayasu Taki*(*は責任著者)
DOI: 10.1021/jacs.5c11742
※【WPI-ITbMについて】(http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp)
名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)は、2012年に文部科学省の世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の1つとして採択されました。
WPI-ITbMでは、精緻にデザインされた機能をもつ分子(化合物)を用いて、これまで明らかにされていなかった生命機能の解明を目指すと共に、化学者と生物学者が隣り合わせになって融合研究をおこなうミックス・ラボ、ミックス・オフィスで化学と生物学の融合領域研究を展開しています。「ミックス」をキーワードに、人々の思考、生活、行動を劇的に変えるトランスフォーマティブ分子の発見と開発をおこない、社会が直面する環境問題、食料問題、医療技術の発展といったさまざまな課題に取り組んでいます。これまで10年間の取り組みが高く評価され、世界トップレベルの極めて高い研究水準と優れた研究環境にある研究拠点「WPIアカデミー」のメンバーに認定されました。
※【IRCCSについて】(http://irccs.nagoya-u.ac.jp)
学際統合物質科学研究機構(IRCCS)は、名古屋大学、北海道大学触媒科学研究所、京都大学化学研究所附属元素科学国際研究センター、九州大学先導物質化学研究所の4大学がコアとなり、単なる研究所連携を越えた組織として、2022年に名古屋大学に設置されました。物質創製化学分野の融合フロンティアの開拓に挑むとともに、国際・異分野・地域・産学官の連携を強力に進める場を構築することにより、当該分野の世界的トップ拠点の形成を目指しています。触媒、バイオ機能、マテリアルを中心とした新分野創出の潮流を生むとともに、持続可能社会の進歩に貢献する科学研究を展開することを目的としています。
※【iGCOREについて】(https://igcore.thers.ac.jp)
岐阜大学糖鎖生命コア研究所は、名古屋大学糖鎖生命コア研究所と連携し、東海国立大学機構が実施する連携拠点支援事業(糖鎖生命コア研究拠点)としての支援を得ながら、世界と伍する研究拠点を目指しています。