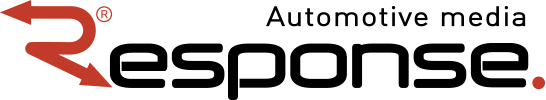毎年1車種づつニューモデルを加えていくスケジュールに、2020年はコロナ禍のため遅れが出た。とはいえシトロエンから独立ブランドになって早6年半、独自開発モデルとして『DS 7 クロスバック』を世に問うてから3年半(日本上陸は2年少々前)。DSの現在位置を確かめるべく、オールラインアップ試乗会を覗いてみた。
オールラインナップとはいえまだ3車種!
 DS 3 クロスバック
DS 3 クロスバック
『DS 3 クロスバック』とDS 7 クロスバックという大小2車種のSUVクロスオーバーに加え、2020年最終四半期から投入された純EVモデルの『DS 3 クロスバック E-テンス』という、まだ3車種だ。ぱっと見はエントリーとフラッグシップという上下のキリに、新味のEVが加わったようだが、ことほど左様に単純でないのが、フランス車として久々に高級車として位置づけられるDSブランドの理解されづらくも面白いところではある。
最初に乗ったのはDS 3 クロスバックの「ピュアテック130」版。PSAグループの、直噴ガソリンのダウンサイジング直3・1.2リットルターボで、本国では155ps版も用意されているが、日本での「ピュアテック」搭載車の中では今のところ最強となる。
物理的にはプジョーやシトロエン、あるいはオペルに共通するパワーユニットやプラットフォームであることは間違いないが、DS 3 クロスバックが抜きん出いてるのは静粛性だ。これは前席サイドウィンドウに二重構造のアコースティックガラスを用いたことが大きい。全長4.1m強で、車幅は1.8mに満たない小さな車格にも関わらず、だ。
 DS 3 クロスバック
DS 3 クロスバック
しかも年次改良されたモデルイヤー2021仕様は、いつアイドリングストップに入って再スタートしたのか分からないほど、エンジンの振動の抑え込みが格段に進歩している。街中で信号待ちしていた時、ステアリングに手を添えていたのに、意識しないと気づかないぐらいだった。
加えて侮れないのが、乗り心地とドライバビリティ。Bセグとしては大きめで外観重視になりがちな18インチ・ホイールを採用しつつも、55扁平で外径690mmという大きめタイヤを履きこなし、乗り心地に角がない。フロントサスはストラット式だがアルミ平断面のアームによるしっとり落ち着いたハンドリングもいい。
さらに、幾度もエンジン・オブ・ザ・イヤーを獲ったピュアテックが低回転域から力強いだけでなく、唄うように軽快な音質で、それこそ「街に繰り出す」気にさせる。ショーファードリブンや古典的なセダンボディのドライバーズカーではなく、こういう街乗りメインのスモールカーが高級車であるという、その考え方自体の小気味よさだ。
小さな高級車の伝統はどこから?
 DS 3 クロスバック
DS 3 クロスバック
こういう「ポップな高級車」は、オリジナルのミニに対するライレーやウーズレーといったADO16シリーズの華やかなりし60年代からあったが、ローバー114を最後に英国の小型車が下火になって以降、あるいは80年代のルノー『5バカラ』や90年代のプジョー『205グリフ』らの時代から、フランス車の得意技になった。しかもフランス車はウォールナットなどウッドにクロームメッキといった誂えを、否定はしないが、前時代的と捉えている節が多々ある。
それを前提にDS 3 クロスバックの内外装を眺めていくと、キラキラとは程遠いことが分かる。そもそもDS内装の艶消し質感は、プライベート・ラウンジのような「コクーン(繭)」効果狙いで、開放的で明るいのはシトロエン任せ。パールステッチの「パール」部分は、縫い目が線ではなく点なので相対的に「光って」見えるだけだし、センターコンソールスイッチの「ギョシェ彫り」模様も、18世紀にブレゲが時計の文字盤用に発明した時は、反射を防ぐ加工だった。
外装のクローム使いも、フロントグリルの格子の中で下を向いているし、マトリクスLEDライトやリトラクタブル式ドアオープナーなど、インテリジェント制御の部位に限られる。だからDSワールドがキラキラして見えるというのは、そもそも論的な蘊蓄を知らない/知識のない人の目にそう見えたか、たまたま光を拾っただけなのだ。光モノの使い方がまるで異なるし、純粋にヴィジュアル上のキラキラ具合でいえば、メッキの面積が存在理由のような国産ハイトワゴン辺りには遠く及ばないのだ。
Bセグの輸入EVという独自の位置づけと走りの「E-テンス」
 DS 3 クロスバック E-テンス
DS 3 クロスバック E-テンス
次に乗り換えたのはDS 3 クロスバック E-テンス。50kWhのリチウムイオンバッテリーをリアシート下あたりから荷室床下に収め、航続距離はJC08モードで398km、欧州ではWLTPモードで約320kmと発表されている。車両重量も1580kgと先ほどまでのガソリン版に比べ300kg増。ガソリン版が好印象だっただけに、乗る前から気にしていたことがある。
というのも、じつは2年前の国際試乗会でE-テンスの生産型プロトタイプにちょい乗りした時は、リアサスは固くて縦にも横にも跳ねるような印象だった。しかもいつものトレーリングアーム式ではなく、左右リジッドの車軸を斜めのロッドで吊るというパナールロッド式という。
1955年に登場したオリジナルのシトロエンDSはハイドロプニューマチック・サスペンションで他の車すべてを時代遅れにした。そんな祖先の前衛ぶりに比して、今日の最新のDSがパナールロッド…って大丈夫か?という、ツッコミどころを2年抱えたまま、本邦での市販仕様に初めて試乗したのだ。
みなとみらいを発って横浜市内を横切って第三京浜にのり、K7の新しめ舗装から首都高1号線のツギハギ路面まで巡る一周コースにしてみた。予想を大きく裏切ることに、DS 3 クロスバック E-テンスの足まわりは穏やかでしっとりと、ガソリン版のそれと直後の比較だというのに、何ひとつ譲るところがなかった。
 DS 3 クロスバック E-テンス
DS 3 クロスバック E-テンス
三ッ沢の登りのS字などはEVの方が力強く、アクセルを少しオフにした時のノーズの入りも鮮やかで、その上、高速では輪をかけて静かだったのだから、文句のつけようがない。K7走行中は、タイヤのロードノイズどころかトンネルの換気ファンが煩かったぐらいだ。
撮影中は通電しっ放し、試乗中は加減速を繰り返して意地悪く走ってみたのだが、バッテリーの減りは20%ほど。ひとつ明確に感じた難点は、下り坂などで強めの減速中、ブレーキディスクの摩擦とモーター回生の摺り合わせ領域で、軽いジャダー音が出ることだ。減速しなくなる訳ではないが、協調制御として完璧を期した部分ではある。
とはいえ、ダイヤモンドステッチのレザー張りダッシュボードに、シートはファブリックとナッパレザーのコンビ、そんな白一色による素材感グラデは、フランス流「小さな高級車」のお手本といえるインテリアだ。質感的にもBセグ随一だし、これ一択の指名買いマダムも少なくないだろう。EV補助金を考慮すれば乗り出し500万円という予算感は、国産EVと、Dセグ以上が多い他の輸入車EVの中間という独自ポジションでもある。
Cセグ+αと思えない貫禄のある動的質感「DS 7 クロスバック」
 DS 7 クロスバック
DS 7 クロスバック
最後に、同じコースをDS 7 クロスバックに乗って1周した。試乗車は「グランシック」のオペラ内装だった。ダッシュボードやシートのサイドサポートの「パティ―ヌ仕上げ」は、革色と異なるトーンの染料を塗り込んで奥行きが醸し出す加工。カタチ的に腕時計のブレスレットのような、しかし70年代のシトロエンSMやCXを彷彿させるシートは1枚革で仕立てられており、身体を預けた時の馴染み方からして格別だ。
DS 7 クロスバックはフランス車としては珍しい可変ダンパーシステムを備えており、その白眉は「コンフォートモード」にある。カメラで前方数十mの路面の凹凸をスキャンしたデータを元に、ダンパー減衰力が数千分の1秒単位でアクティブ制御される。フラットなだけではなく吸収動作の柔らかさ、収束の最後にあとを引く感覚は、往年のDSほどストローク量はなくとも、通じるものがある。ハンドリングの味つけは2リットルディーゼルのBlueHDi180の強大なトルクをもてあまさない程度に、ノーマルでも十分にスポーティだ。
 DS 7 クロスバック
DS 7 クロスバック
ディーゼルらしからぬ高い静粛性もさることながら、DSはフランスのオーディオメーカー「フォーカル」社の最高級システム「エレクトラ」を、車載では独占的に用いている。じつはDS 7クロスバックのそれは、設定がデフォルトのままだと平べったい音なのだが、音場設定を少しドライバー側に寄せると突然、クリアだがデジタル的でない、あくまでアナログな艶っぽさのある聞こえ方になる。ボーカルの音像が急に目の前に現れるかのようだ。
万人に認知され「高級でいいモノだから皆から求められる」より、「分かる人だけ満足してもらえればいい」というのがフランスのラグジュアリー・メゾン的な態度であり、DSもかなりその気が強い。好悪は分かれて当然だし、プラットフォーム共有で中身はプジョーやシトロエンと同じように考えられがちだが、実際は違う。
全長4.6mもしくは4.2mに満たない「小さな高級車」として、然るべき造り込みと動的質感が与えらえているだけに、喰わず嫌いで済ませるのはもったいないブランド、それがDSなのだ。