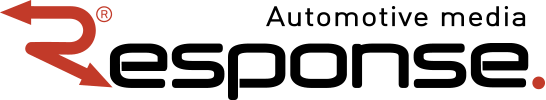鉄道関連のデザイン関係者が一堂に会する『レイルウェイ・デザイナーズ・イブニング』が12月上旬、京都鉄道博物館で開催された。フォーラム会場には聴講者が続々と押し寄せ、座席をどんどん追加するほどの盛況となった。
「レイルウェイ・デザイナーズ・イブニング」は、鉄道車両や機器のデザインに携わるデザイナーや、鉄道事業に携わる企業のデザイン関係者が集結するイベント。2015年に正式にスタートして、12月6日に開催された今回は4回目となるが、近畿圏で開催されるのは初となる。主催は同イベントの実行委員会とフジサンケイビジネスアイ。
イベントの第一部は「地域文化と鉄道デザイン」というテーマによるフォーラム。まず近畿車輛設計室長の南井健治氏と、京都鉄道博物館副館長の藤谷哲男氏による基調講演がおこなわれた。
南井氏は「鉄道デザインの過去・現在・未来」という題で、かつてのデザインの目的や、時代の変化とともにデザインに対する意識も変化してきたことを紹介。技術と文化というデザインの評価軸に、歴史を加えることを提唱した。「技術には優劣がある。文化は地域によって異なるが、優劣はない。ここにもうひとつ、歴史を加えたい」と南井氏。
また「かつては技術者が車両をデザインしていた。現在はデザインという言葉の指す幅が広がり、“あるべき姿”としてのデザインを創らなくてはいけない。これからはデザイナーだけがデザインをするのではない」と語った。
続いて藤谷氏は、同博物館のさまざまな取り組みや、仕事での苦労話を紹介。動態保存するSLをメンテナンスする際、図面が残っていないために部品を新造することができず、新規の図面を起こすために製図のノウハウを積み上げることから作業を始めたことなどが語られた。
また周辺地域の小学生たちにレストア作業を公開したり、出張授業で鉄道車両の原理や仕組みを紹介し、簡単な空力実験も実演するといった活動を紹介。過去と未来の両方を見つめるという博物館の意義が理解できた。
基調講演の後はテーマ講演。いずれも西日本を本拠とする3社が、それぞれの立場でのさまざまなデザインについて語った。まず京阪ホールディングス経営統括室の大浅田寛経営戦略部長は「商都大阪と古都京都を結ぶ - 京阪電鉄の企業文化とそのデザイン」として、さまざまな局面でデザインを活用して魅力向上に務めていることを紹介。
京阪電鉄では10年前から、沿線全体の雰囲気を考えて車両デザインをすることにしたと大浅田氏。例として書院造の丸窓を新型車両の先頭形状やグラフィックのモチーフに採用したことや、カラーリングをリニューアルする際のエピソードを語った。特急は赤、通勤車は緑というカラースキームが沿線に広く浸透しているので、色域は踏襲することにしたという。
また駅のトータルデザインについては15年前から取り組んでいるという。以前は駅ごとにサインがバラバラで「あまりにバラバラで面白いから、本が出せるんじゃないかと思ったほど」だったとか。まずサインマニュアルを作成し、時刻表や各種サインを刷新。さらには発車メロディをデザインしたが、京都方面に向かう番線では和楽器の優雅な音、反対の大阪方面ではリズミカルな都会的な音を採用。沿線全体の雰囲気を伝えると同時に、音で方面という情報を伝える機能を持たせたという。「京阪らしさを五感で訴求することが大切」と大浅田氏。
次の講演は、近畿車輛デザイン室のダニエル・ロドリゲス シニアエキスパートによる「ドーハ向け車両デザイン~異なる文化と鉄道」。カタールの首都、ドーハの事例を紹介した。デザインにあたっては「ドーハという街のアイデンティティを表現しなければいけない。そのためには現地に行って、五感で経験しないといけない」と考えたという。「なぜなら街を走る車両は、街の一部分。パズルのピースのように、きれいに嵌まるものでなければいけない」からだと説明した。
実際の車両デザインは、アラビア語で馬を意味する「アル・ファラス」というキーワードで進めたとか。カラーリングは伝統的なドーム建築に着想を得たもの。「グラフィックは、意味を忘れたら意味がない」とダニエル氏。インテリアもカタールの文化やカタール人のライフスタイルを取り込んだところ、日本の鉄道車両ではまったく異なるものになった。「どこでも受け入れられるデザインではない。ドーハのためにデザインしたもので、カタールの文化を発信し、アピールするものです」と結んだ。
最後は、アルナ車両の田島辰哉社長による「国内の路面電車と地域特性」。冒頭、スライドショーで同社の代表シリーズ『リトルダンサー』を紹介したが、そのバリエーションの多様さに驚かされる。これは事業者ごとに異なる事情や要望を丁寧に汲み取り、デザインに反映させた結果のようだ。
全国各地の路面電車の例を紹介した後、車両を製造する側としては「本当は標準化したいけれど、無理」と田島氏。地形も気候もバラエティに富んだ日本の風土、そしてそれによるライフスタイルと事業者の多様性が、画一化した車両の運行を不可能にしている。路面電車特有の事情として、自動車との接触事故が多いことを挙げた。修理のしやすさやコストを考慮すると、車体にアルミやステンレスを使うことはできず鉄のみで、ガラスも平面ガラスしか使えないとか。
いずれの講演も、地域文化が車両や設備などあらゆる部分のデザインに大きな影響を及ぼし、またデザインが沿線文化を育むことに貢献できることが窺える内容だった。総評を述べたGKデザイン機構の山田晃三取締役相談役は「自動車は個人のステータスシンボルで、どこへでも持っていける。でも鉄道は地域のステータスで、地域に根ざしている。また地域で商売をしているため、車両だけでなくいろいろなものをデザインしなければいけない」と語った。
フォーラムの後は、実行委員長の南井氏が、冗談半分で「これが本来の目的」と言う懇親会。博物館の閉館時間まで、企業の垣根を越えた活発な交流が続いた。