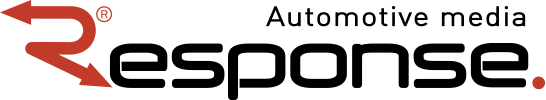大規模量子コンピューターシステムに向けたサプライチェーンに関する技術報告書を公開
ポイント
・ 量子コンピューターの大規模化に必要な要素技術の現状と課題を俯瞰
・ 技術報告書の活用により国内企業の量子コンピューター産業への新規参入を後押し
・ 量子コンピューター産業の安定的かつ強靭なサプライチェーンの実現に貢献
概 要
国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)、国立研究開発法人理化学研究所、日本電気株式会社は、富士通株式会社と共同で大規模量子コンピューターシステムに向けた俯瞰図・ロードマップの策定を進めています。このたび、その第一報として、超伝導方式のサプライチェーンに関わる技術報告書を公開しました。
産総研 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(以下「G-QuAT」という)は、内閣府の政策である「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の第3期課題「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進(プログラムディレクター:寒川 哲臣(NTT株式会社))」のうち、サブ課題「量子コンピューティング(サブプログラムディレクター:G-QuAT 堀部 雅弘)」において、「現実の社会・産業課題の具体的な解決事例(ユースケース)」開発に向けた研究開発に取り組んでいます。今回、研究開発テーマA-4「大規模量子コンピューターシステムに向けたロードマップ等作成(研究開発責任者:産総研 昆 盛太郎)」において、量子コンピューターの複数ある技術方式のうち、超伝導方式による大規模量子コンピューターシステムに向けた技術報告書を作成しました。本技術報告書では、超伝導方式のシステム全体の要素技術、大規模化に向けた開発要素を提示しています。本技術報告書を公開することにより、日本が強みとしている素材・製造産業分野から量子産業界への積極的な参入を促し、安定的かつ強靭なサプライチェーンの構築に貢献することを目指しています。
下線部は【用語解説】参照
社会的背景
量子コンピューターの実用化および大規模化のためには、周辺デバイス・部品・材料などの高度化とともに、これらのサプライチェーンの構築が不可欠です。国内産業は、エレクトロニクスを含むデバイス・部品・材料などに関して強みを有しています。しかしながら、現時点では量子コンピューターシステムの技術仕様が明確ではなく、多くの企業、特に中小企業にとっては参入のハードルが高い状況です。こうした課題を踏まえ、量子コンピューターシステムの技術仕様を明確化し、システム全体や必要なデバイス・部品・材料などに関する技術報告書を作成します。これにより、中小企業を含む裾野の広い産業界の積極的な参入を促進し、安定的かつ強靭なサプライチェーンの構築を目指します。
技術報告書のポイント
◆ 超伝導方式の量子コンピューターシステム全体における要素技術と必要スペック
◆ 大規模化に向けた開発要素
◆ 世界の主要機関における量子コンピューターの研究開発動向
超伝導方式の量子コンピューターを構成する重要な要素技術として、信号増幅器、ケーブル、コネクター、高周波コンポーネント、希釈冷凍機、制御システムなどがあります。約2年前に実施した調査では、超伝導量子コンピューターを構成する多くの部品・機器は日本企業で開発されたものであり(1位:日本31種、2位:米国29種、3位:ドイツ4種、他)、ほぼ日本と米国製部品で超伝導方式の量子コンピューターを完成できる状況でした。また、それらの部品・製品のいくつかは技術的な参入障壁が高く、後発の企業が後追いで開発することが困難なチョークポイントとなっています。これらは、例えば通信産業など、非量子産業で発展した部品・装置を応用・転用したものも多く、国および研究機関の支援によりこれらの部品・装置の小型化・高密度化・省エネルギー化を図ることは、大規模量子コンピューター実現を阻む課題の1つを解決するだけでなく、転用元となった非量子産業分野における技術力を高めて競争力を強化することにも繋がります。
例えば、量子ビットの状態の読み出しや制御にはマイクロ波が通る配線を使用する必要があり、現状はほぼ同軸ケーブルを使用しています。量子ビットを大規模集積化するためには、そのマイクロ波が通る配線の数を増やす必要がありますが、実装面積や熱負荷などの増加を伴うため、現状の部品や素材では量子コンピューターの大規模化に限界があります。この課題を解決するためには、例えば、より大型で冷却能力の高い希釈冷凍機や、ケーブルのフラット化、コネクターの多連化などの技術開発が必要です。
そこで、超伝導方式の量子コンピューターの要素技術部品について、大規模集積化に向けた課題を抽出し、その課題を解決するために、関連部品を製造または開発できる可能性のある国内外の企業や量子コンピューターの研究を行う研究機関、各種学会の主催する国内・国際会議などから量子コンピューターに関わる情報収集を行いました。これらの調査をふまえ、1000量子ビット級あるいはそれを超える量子コンピューターを実現するために必要な研究要素の抽出と、研究を遂行するために必要な環境など、量子コンピューターの大規模化に向けた開発要素の技術報告書を作成し、公開しました。
なお、技術報告書についてはこちらをご覧ください。
今後の予定
超伝導方式以外の量子コンピューターの技術方式(例:光量子、中性原子、イオントラップなど)についても、技術報告書を作成していきます。各方式に共通するデバイス・部品・材料や、非量子産業製品の活用の可能性も検討し、これらを技術報告書に反映して一定程度の市場性・経済性があることを示し、より多くの企業の参入を促進するための取り組みも行う予定です。
研究開発体制
研究テーマ:大規模量子コンピューターシステムに向けた俯瞰図・ロードマップとサプライチェーン強靭化
研究開発責任者:昆 盛太郎(国立研究開発法人 産業技術総合研究所)
共同研究機関:国立研究開発法人理化学研究所、日本電気株式会社、富士通株式会社
用語解説
高周波コンポーネント
量子コンピューターで利用されるコンポーネントには、サーキュレーター、フィルター、アッテネータなどがある。これらのコンポーネントを接続するコネクターの形状は、高周波信号の散乱を防ぐために国際規格によって厳密に決められている。
量子ビット
古典コンピューターにおける情報の最小単位(ビット)は0と1だが、量子コンピューターでは0と1に加えて、それらの重ね合わせ状態が利用でき、量子ビットと呼ばれている。量子コンピューターを実現するためには、利用できる量子ビットの数を増やす必要がある。
マイクロ波
周波数が3 GHzから30 GHzまでの電磁波で、超伝導量子ビットの制御には、5 GHz付近のマイクロ波が使用される。
プレスリリースURL
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250909/pr20250909.html