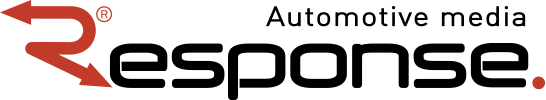クルマの使い方の変化
自動車の調達・生産プロセスは車体構造の変化だけに影響を受けるわけではない。シェアリングによる使い方の変化にも注視すべきである。
シェアリングの普及と自動運転の実現はクルマの使い方を様変わりさせる。現在よりも遥かに安価な金額で自動運転タクシーを利用できるようになるからだ。タクシービジネスの原価に占める人件費の割合は70%を超えること、自動運転になれば24時間稼働が可能になることなどを考えると、自動運転タクシーの料金は現状の30%未満になる。もちろん、運転をしたり、駐車場を探したり、クルマを取りに行ったりする必要もない。クルマに特別なこだわりがある人を除けば、自家用車を購入・所有すべき経済合理的理由はなくなる。
大量生産の再来
では、大多数の人が自動運転タクシーを都度利用する時代になったとしよう。今ある豊富なモデルラインナップは必要だろうか。
タクシーに乗るとき、大型や小型といったクルマの大きさを気にかける人はいる。クレジットカードやタクシーチケットが使えることを条件にする人もいる。しかし、ボディの形状やカラーを気にする人はほとんどいないはずだ。
自家用車であればこそ、クルマはステータスシンボルに成り得たのである。他の人が持っていないクルマが欲しいとか、近所の人とかぶらないようにしたいとか、個性への要求があったわけだ。都度利用するだけの「移動のための手段」になれば、ユニークネスは求められなくなる。むしろ、大量生産に回帰することで、製造コストの更なる低減や品質不良の最小化が図られるのだとすれば、その方が社会の要請に合っている。
つまり、調達・生産プロセスのデジタル化と設備の汎用化によるマスカスタマイゼーションの実現は、業界の垣根を越えたムーブメントになろうとしているが、自動車業界ではこの流れに逆行するような変化が起きようとしているのである。地域や用途による多少のバラエティは必要だが、今までのように類似のモデルが複数の自動車メーカーからいくつも投入されるようなことはなくなる。自動車でのシェアリングの拡大は、モデルラインナップの減少と、モデルあたりの生産量の増加に帰するのである。
部品の共通化
シェアリングが増えることは、自動車の稼働率を高めることにもつながる。自家用車とは違って、不特定多数のユーザーが利用することになるからだ。ゆえに、高稼働でも壊れない、耐久性に優れた自動車への需要が高まるだろう。だが、どれほど耐久性が高くとも、メンテナンスの頻度を向上させたとしても、不具合や故障の発生を完全に防ぐことはできない。一定の確率で不具合や故障が発生することを前提に、早期修理を可能とする仕組みを構築することが求められる。
そのためのリカバリーネットワークを形成することは、修理の早期化に資するはずだ。しかし、自動車に使われる部品の種類は段違いに多い。補修用部品の置き場を増やそうとすると、その分だけ在庫量が増えてしまう。この相反する状況を打開するためには、部品の共通化を図る以外にない。つまるところ、シェアリングの拡大は自動車本体のみならず、部品のラインナップも減ずる結果をもたらすのである。