マツダが2013年11月21日に発売した新型『アクセラ』。発売から4ヶ月での受注台数は2万5000台を超える好調振りを見せている。
同社の"SKYACTIV TECHNOLOGY"や“i-ACTIVSENSE”を搭載し、ガソリン、ディーゼル、ハイブリッドと3種類のパワートレインをラインナップ。さらに、新世代カーコネクティビティシステム“マツダコネクト”を採用した新型アクセラの誕生秘話と魅力を探るべく、開発陣に「10の質問」を行った。
Q9.どうやってアクセラに人馬一体を宿らせたのか?
A9.各モデルの重量に合わせ、調整を行った。北米、欧州、首都高などあらゆる条件下で走り込み、新構造のダンパーを採用するなど、徹底的に乗り味を追求している。
マツダ『アクセラ』の開発で、乗り味を仕立てたエンジニア2人に話を聞くことができた。あの気持ちいい走りはどうやって作り上げられたのか、開発の現場の情景が脳裏に浮かんでくるような話をお届けしよう。
「やはりお客さんに感じてほしいのは、人馬一体感。それは運転して気持ちいいことであって、大事なのは人の感性に沿った動きですから、人間の感覚より遅れているようではダメですし、追い越したような動きでもダメだと思うんです。例えば持ち上げようするモノが想像より軽かったら、力を入れすぎて腕が浮いてしまうでしょうし、逆に想像より重ければ持ち上がらずに次の動作に違和感が出ますよね。そんな違和感を起こさないことが、クルマの作り方を決める時に重要なポイントになっています」。
まず口を開いたのは操安関係の評価を行う操安性能開発部の青木智朗氏。穏やかな口調で、分かりやすく目指した乗り味への仕上げ方を語ってくれた。しかし優しい物言いの中に、強い信念を感じるようになるには、時間はかからなかった。
「コモンアーキテクチャなので、メカニズムの理解度が深まっているというメリットは大きいですね。メカニズムがごそっと変わっていると、出来上がるモノのイメージと実際のズレはどうしても大きくなってしまいます。でもコモンアーキテクチャなら基本的なプラットフォームが同じというだけでなく、相似関係にあるのでイメージと実際のズレは少ないんです」。
しかしアクセラだけを考えても、パワーユニットは4種類も存在する。それぞれのパワーユニットに相応しい装備を与えていけば、自然と重量も異なる。したがって乗り味の方向性を揃える作業自体、相当難しいことだ。仮に同じモノコックボディを使ったとしても、それ以外の要素が違うのだから。そういう意味では開発が一番難しかったのは、やはりXDだったのだろうか。
「ボクらの立場からすると、一番難しかったのは1.5リットルのモデルでした。なぜかというと一番バネ上荷重が軽いモデルなので、走る状況によって動き方が変わってしまうんです。足回りのフリクションなどの抗力に対してサスペンションが動きにくいんですね。むしろある程度重さがあった方が、足を動かしやすいんです。なので応力の方向をコンロールしたり、小さなことの積み上げで実現できたのが、今の15Sの乗り味なんです」。
スポーティな動きを好むユーザーにしてみれば、足が動きにくい=踏ん張るということで、好ましいと思えるかもしれない。ところが一定以上の入力があった途端に動くような足回りになっていては、やはり走りの安定感が低下する。それではマツダの考える人馬一体を実現したとは言えないだろう。1.5リットルは、シンプルで軽いからタイト感のある動きを自然に作れた、と想像したのは筆者の浅はかな考えだった。
「ライド感、乗り味は同じものにしたいと思っていますが、重量が違うことでバネ上荷重の固有振動数も異なるので、それを同じ乗り味にするのは無理があるんです。そこで方向性は同じでも、2.0リットルやディーゼル、ハイブリッドはそのグレードの素性にあった仕上がりを目指しました」。
「いいものは一つ、と常に思っていますからターゲット、目指す到達地点は一緒なんです。でも実際にはエンジンの重さ、タイヤのグリップなども違いますから、それぞれにアジャストしてやる必要があるんです」。
と、車両開発推進部の森内健夫氏が補足する。青木氏と一緒にアクセラの試作車を走らせ、トータルなパッケージで人馬一体感を作り上げてきた人物である。
「色々な環境でアクセラを走らせました。北米、欧州…、夜の首都高速も走り込みました。あそこは日本独特の過酷な道路ですから」(森内氏)。
そもそも突貫工事で作り上げたためサーキットのようなコーナーが連続する上に、後からの増築でレイアウトは複雑、しかも老朽化で路面状況も様々に荒れている首都高速。条件が悪い道路ほど、絶好のテストコースにもなった。
「広島で走っている時にはいいと思っていた乗り味も、首都高速に持って行ったら違う問題点が見えてくることが多くて、何度もそれを繰り返しました。徹底的に走り込んでチェックしたんです」(森内氏)。
会社の敷地以外の場所を走った距離は、今回のアクセラが最長だと言う。
「路面から入力の厳しいところでは、思うような乗り味を出せていませんでした。そうした場合、その部分の性能を満足させるためには、何をすればいいのか方法を考えるんです。そこで今回は新構造のダンパーを採用しよう、ということになりました」。(青木氏)
「実は、開発の期間はすでに終わっていました。けれども我々は納得できなかったんで、上司に直談判してやらせてもらったんです。ここで妥協したくありませんでしたから」。(森内氏)
重役に頭を下げても人馬一体を追求するエンジニア。こうした熱意が、今のマツダを走らせる、そして未来の原動力になる。だからこそ開発部門のトップもリセッティングにGOサインを出したのだろう。
「我々が目指したのは15Sの走りなんです」。かつて前開発主査の猿渡氏から聞いた言葉を思い出した。それと同時にマツダの開発陣が、いかにクルマを走らせることが好きか、伝わってきた。
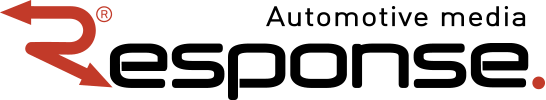




































![自動車8社の10月世界生産、トヨタ過去最高、ホンダ・スバルは大幅減[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2163431.jpg)
