8日、都内で「VICSプローブ懇談会」が開催された。これは道路交通情報通信センター(VICSセンター)が事務局となり、産官学の有識者が次世代VICSについて議論するものだ。
明日、11日に衆議院選挙を控えた今夜だからこそ、次世代VICSの存在意義をもういちど考えてみたい。
衆院選挙の大きな争点の一つは郵政民営化の是非である。小泉自民党が唱えるのは「民にできることは民に任せる、小さな政府を目指して国家の財政再建を進める」という考え方。新聞各社による事前アンケートによれば、その自民党が有利に支持を集めているようだ。もし、明日の選挙結果が本当に自民の大勝で終わるならば、郵政にとどまらず、官から民への流れがいっそう強くなることが予想される。
■「VICS」は道路交通情報サービスにおける「郵政」!?
なぜ突然選挙を持ち出すかというと、「郵政」を交通情報やITSにも当てはめてみると「VICS」が郵政にあたるのではないかと、8日の「VICSプローブ懇談会」を傍聴しながらふと考えたからだ。
VICSは今年7月で10周年を迎えたが、日本のカーナビITS普及に大きな貢献をしてきたことは誰もが認める部分だ。例えば、2004年の新車販売台数3,962千台(普通自動車)に対してカーナビの出荷台数は3,630千台だった。2005年は確実に逆転するであろうこの市場を作り出した要素のひとつにVICSの交通情報がある。
VICSセンターは昨年度は約82億の収入に対し約14億の利益を出す優秀な財団法人である。税金の注入は受けていない。しかし、国土交通省、警察庁が税金で設置したインフラ(光ビーコン、車両感知器など)を通じて集めた交通情報を無償で提供してもらう一方で、ユーザーからも対応カーナビの売り上げの一部を回収するという方法で二重のユーザー負担の上でのサービス運営を行っている。
民の交通情報サービスはどうか? 2002年に交通情報の加工提供が可能になってから3年。渋滞予測とダイナミックルートガイダンスを中心に、テレマティクス、ケータイ向け有料コンテンツ、事業者向けソリューションなどいっきに民間交通情報ビジネスが開花した。VICSが陳腐なことに気がついたユーザーは、特にカーナビの渋滞予測機能は読者アンケートを行ってもユーザの関心は高く、各社の予測技術の競合が新たな利便と市場を切り開く可能性を示している。3年間の進歩は目を見張るばかりだ。
それに比べてVICS進歩は無に等しい。10年前の仕様を地域拡大をしながら忠実に繰り返してきた。10年間同じサービス。それでもVICSは交通情報ビジネスにおける民間ビジネスに立ちはだかる最大の敵でありつづけた。
現在議論している次世代VICSについてもロードマップはインフラ普及についてしか述べられていない。進化し続けるサービスやテクノロジーの進化により質が高まる情報収集については、過去10年と同じく興味が無いのかもしれない。官らしい考え方である。
■民間パワーを引き出す触媒のような官の役割とは
そのような次世代VICS(VICSプローブ情報収集および提供)はユーザーにとって本当に吉だろうか。官であるVICSは、これからもより強大なサービスプロバイダとして民間に立ちはだかるのであろうか。それとも、渋滞解消は経済波及効果が著しいため、民のビジネスを圧迫してでも官がサービスするメリットがあると考えるべきか。VICSは情報収集の統合機関としての役割に徹するべきなのか。その場合どの部分で官と民はサービスをリレーするべきなのか。
新サービスの原資は税金であっても、製品価格であっても、サービス利用料であっても結局はユーザー負担である。ならばユーザーが喜んで財布を開き新たな市場をつくるサービスは何かなど、節目にあたって議論すべき内容は山ほどある。
8日の議論では、上記コストについての意見を含め、各委員から様々な注文が出て、事務局が提案した次世代のVICSプローブの着手に「ちょっと待った」をかけた状態でタイムアップとなった。しかし、事務局であるVICSセンターは次回12月の懇談会では「仕様決め」を予告している。おそらく、この間3ヶ月あまりを根回しと取り引きを水面下で行うことで12月の懇談会を平穏に乗り越えたいと望んでいるのだろうが、ぜひとも議論の続きを公開の場で続けてほしい。
ハードがITSを引っ張る時代は終わった。ビジョンやサービス設計、進化向上するマーケット作りのソフトで次の10年、その先のぶつからないクルマ、交通死亡事故ゼロの社会を描かなければならない時期である。もちろん交通問題は民だけでは解決できない。そこが郵政とは違う部分かもしれない。しかし、官がどの役割を担うべきかは過去の例はとりあえずリセットして、もう一度考え直すべきであろう。








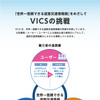
![国交省がトヨタ本社に立ち入り、『ヤリスクロス』など不正3車種月末まで生産停止へ[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_l1/2013784.jpg)


![道幅狭い生活道路、法定速度を30km/hに変更へ、警察庁検討[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_l1/2012571.jpg)
![大型・中型車もAT限定免許、「物流の2024年問題」で警察庁が導入検討[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2002012.jpg)
