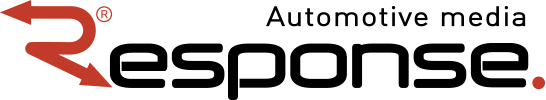11月下旬の『第5回鉄道技術展』にあわせ、30日には幕張メッセ(千葉県)で『第3回レイルウェイ・デザイナーズイブニング』が開催された。講演とパネルディスカッションは立ち見が出るほどの盛況で、その後の懇親会でも活発な交流がおこなわれた。
「レイルウェイ・デザイナーズイブニング」は車両や機器、設備やインフラなど、鉄道に関わるさまざまな領域で活動するデザイナーが所属企業や役職の壁を越えて交流するイベント。同イベントの実行委員会とフジサンケイビジネスアイの主催で2013年にプレ開催され、15年から正式にスタートしている。鉄道技術展の併催イベントとしては一昨年に続いての開催となる。
今回のテーマは「鉄道とコミュニケーションデザイン サインからひも解く情報環境の未来」というもの。ピクトグラムをはじめとする案内誘導サインや路線カラーといった情報伝達を目的とした「コミュニケーションデザイン」に着目し、鉄道事業におけるこれからの「情報環境」のあり方を議論するというものだ。
イベントはまず、GKデザイン機構の山田晃三 取締役相談役による基調講演でスタート。「鉄道とコミュニケーションデザイン」という題だが、「デザイン」というものを多面的に捉え、考えることの重要性を説く内容だった。
まず「鉄道技術展の各社の展示では安全、安心、省エネ、未来といった単語は出てくるが、デザインという言葉はひとつも出てこない。技術重視の展示会に、デザイナーはどのようにして切り込んでゆくのか。それは科学をベースとした技術にたいして身体、地域、国といったようなものを基本とした、文化の視点ではないか?」と問いかけた。
「文化というのは数字に置き換えることができず、優劣を数値で測ることができない。差異、違いに価値を置くものなのではないだろうか。歴史とか風土とか思想とか、そういうものの違いから生まれる個性。これが大事な価値観だと認識している」と山田氏。
また一般的な「デザイン」の認識は誤解に基づいている、とも述べる。「一般的には、リゾート列車やイベント列車などが”デザインされている”と思われている。たしかにこれらはいろいろ付加していった”プラスのデザイン”で、ここから”デザインとは付加価値である”という認識が生まれている」と指摘。
「しかし通勤車両のように、余計なものを省いてゆく”マイナスのデザイン”も重要で、かつ難しい。だから”デザイン=付加価値”という考え方には反対だ。デザインは本質的価値ではないか。デザインは総合的アプローチで、全体を俯瞰する立場にあるものではないかと思っている」と続けた。
そしてその総合性を、モノのデザイン(プロダクトデザイン)、空間デザイン(エンバイロメントデザイン)、情報のデザイン(コミュニケーションデザイン)という3要素で表現。しかしこれらはそれぞれ独立したものではない、と山田氏。「これらは相互に重なるものだ。たとえば車両デザインはプロダクトデザイン領域だと思われがちだが、実際には形、空間、情報伝達のすべての要素が車両のデザインには含まれている」とのこと。
現在の情報伝達と、そのデザインについては「ICT技術によって、顧客のさまざまな行動パターンがデータになって蓄積されつつある。コミュニケーションデザインはそういうところまできている」と、旧来のものは現代流にアップデートしつつ、他の要素と有機的に絡み合った新しい手段をデザインしなければいけないことを示唆した。
基調講演の後は、アイ・デザイン代表取締役の児山啓一氏、ソーシャルデザインネットワークス代表取締役社長の定村俊満氏、ジェイアール西日本テクノス車両事業部の大森正樹 設計部長という3名のデザイナーによる講演が続いた。
児山氏は「国際的視点から見た鉄道とサインの公共性」というタイトルで、カラーコーディング(機能や目的ごとにそれぞれ色を決め、色彩で情報を伝えること)の歴史を紹介。現在、多くの駅の表示に採用されている「入口は緑、出口は黄」というカラーコーディングは、大阪万博を控えた1968年の伊丹空港、そして70年の羽田空港ではじまり、それが鉄道にも浸透したものだとか。
また現在、駅に掲出されている新幹線のピクトグラムは車両前面を図案化したもので、その絵柄は運行事業者ごとに異なっていることに触れた。公共性を第一に考えるならば、新幹線のピクトグラムは統一されていたほうがいいと児山氏。しかし「地域ごとのブランドイメージを考えると、それぞれに違いがあったほうがいいともいえる。どちらも正解ではないか?」と続けた。
「公共サインというのはコミュニケーションのための共通言語である、ということは守らなければいけない」としつつも、同時に「周囲の環境の質は、生活の質に大きく関わってくる。鉄道のデザインは文化であり、ないがしろにしてはいけない」と、鉄道に関わるデザインは利用客や沿線住民に影響を及ぼすものだと指摘。「サインデザインは平面上のものかもしれないが、それが文化を創っているんだという視点だけは大切に持っておきたい」と結んだ。
続く定村氏は「小さなマーケットニーズからの発想」というタイトルで、ユニバーサルデザインの本質や、特殊な事例をノーマライズすることの価値を紹介。まず触れたのは博多駅の環境デザインについてだった。駅内部をリニューアルする際に出口、新幹線の乗り継ぎ、在来線への乗り換えという3方向の動線を色分けし、駅構内の空間デザインで情報提供をするようにしたが、これは「小さなニーズ」を取り込むデザインを考えた結果、すべての旅客にメリットをもたらすものになった例だという。
「飛行機の福岡~大阪(伊丹)便に対抗するというビジネスコンセプトだった。この距離だと飛行機利用者はさほど多くないのだが、そのニーズをも取り込むことで新幹線の優位性を強化し、弱点の補強をしようとした」と定村氏。デザインコンセプトは「最短時間でスムーズに乗降できる空間作り」だったとか。「旅客機での移動に負けている点はワクワク感やゴージャス感。そこで駅全体で期待が膨らむものにしようとデザインを提案した。航空路線を使う少数に向けてデザインを考えたら、他の旅客もシンプルに動ける効果をもたらした」という。
続いてユニバーサルデザインを全面的に、全駅統一仕様で採用した福岡市営地下鉄七隈線の例を紹介。「建設前の、既存路線の利用者アンケートでは大方が地下鉄に肯定的。しかし”地下鉄はキツい”という少数意見があった」と定村氏。それは、さまざまな身体障害者や車椅子利用者、妊婦、子供連れといった人たちの声だったという。
これを受けてユニバーサルデザインを全面的に採用しつつ、さらに「空間を記号化する」というアイデアを提案。博多駅と同様に案内記号で示すだけではなく、空間そのもので情報を伝えるというものだ。券売機とトイレは壁面を曲面にし、同時に濃い色を塗って目印としたほか、動線の分岐点ではケルビンの低いスポット照明を採用し、色味の異なる空間を作って注意喚起するといったアイデアを採用している。
また、当初は「これは本当に必要なのか?」と半信半疑だった駅ごとのシンボルマークも「路線図にも掲出すると、発達障害者や海外の人にとって情報伝達の助けになっているという思わぬ評価があった」という。「移動制約者や情報制約者の小さなニーズをひとつひとつすくいあげていった結果、メインのユーザーグループにも使いやすい、大きな価値が生まれた」と定村氏。「鉄道は大量輸送機関だからマスで考えがちだが、その陰に隠れたニーズをしっかり把握してほしい」と結んだ。
最後に「モデルチェンジで消費される”フローのデザイン”ではなく、価値が蓄積してゆく”ストックのデザイン”を心がけてほしい。仕組みや空間といった、蓄積される部分にデザインを投入してほしい」と金融用語を用いつつ訴えたが、これは鉄道に限らずすべてのデザイナーに向けたメッセージだろう。
最後に登壇した大森氏は「コミュニケーションデザインが、鉄道のなかでいかに重要な解決策であるか」を例示。3路線が乗り入れる大阪環状線の色彩を紹介した。大阪環状線はオレンジ色が路線カラーだが、ここには他地域へ伸びる3つの路線が乗り入れているため、すべての車両の色彩を統一することができない。またホームで待つ利用者に「目の前の列車は、どこへ行くのか」を明確に示す必要がある。
そこで車両側面の方向幕に、文字に加えてそれぞれの路線カラーを表示するようにした。「車両を設計する際にも、どうやって利用者に情報提供するのか、どこをどのように使うのかを考えることを意識している。コミュニケーションの視点で車両を考えることも大切だ」と大森氏。
また、その大阪環状線の新型車両『323系』のエピソードも興味深い。323系は2016年度のグッドデザイン賞を受賞しているが、前年には同じくJR西日本の『227系』が受賞している。323系、227系のどちらも『225系』をベースに開発されたもので、実質的な姉妹モデルの関係。本来であれば2年連続のGマーク獲得はありえないところだ。しかし受賞対象名を見れば、2年連続受賞の理由が理解できる。
2015年度の受賞対象は「”JRシティネットワーク広島”のブランディング(227系電車と路線記号カラーデザイン)」、翌年度は「323系と大阪環状線改造プロジェクト」となっているのだ。「323系は、エリア全体をデザインしようというなかで、地域に親しまれるための記号を盛り込んだ。車両のハードウェアとしては227系とほとんど同じ車両だが、広島と大阪では課題が異なった。コミュニケーションの観点でデザインに取り組んだ結果、異なるアウトプットになったから評価してもらえたと思っている」と大森氏は述べる。
そして最後に「鉄道会社と利用者を結ぶのがデザインだとするならば、一番重要なのがコミュニケーション。これをもっと徹底してゆくと、鉄道会社だけでなく利用者、沿線に住む人たちの価値になる。沿線地域の人が、自分のもののように鉄道を自慢するようになる。コミュニケーションデザインの究極の姿は、みんなが共有できる価値だ」と結んだ。
講演の後は、モデレーターに近畿車輛取締役設計室長の南井健治氏を迎えたパネルディスカッション。ここでは「情報の伝え方」についてさまざまな議論が交わされた。トイレのピクトグラムを例にした議論ではジェンダーフリーの話題になり「旧来の意識や習慣にもとづく象徴的な図形を、すべての人に当てはめることは失礼。駐車場の”P”のように、新たな取り決めで記号を考えるほうがいい」、「色で性差を表現するのは減ってゆくだろう」、「新しい概念が浸透してきたなら、それに合わせて表示を変えてゆくことも必要」といった意見が出された。
いっぽう各国の地域性にもとづく色や表現の違いについては「標準語と方言があるように、ピクトグラムも統一するものと地域性のあるものが両方あっていい」、「ただし、命に関わる危険を知らせるものは共通化すべき」といった意見。最後に「コミュニケーションデザインといえばサインが大きな比重だが、車両の形や色、駅やパブリシティも情報発信手段」、「便利なほうがいいけれども、違いがあってもいい。違いを知ることも、旅行の大きな印象になる」といった南井氏のコメントでディスカッッションは終了した。
その後の懇親会では新たな試みとして、主催者が指名したゲストによる2分間のフリー・プレゼンテーションがおこなわれた。ここではドーハメトロの車両デザイン、駅に表示される文字のフォントなど幅広いテーマが展開。南井氏は「レイルウェイ・デザイナーズイブニングを、講演を聴くだけのイベントにはしたくない。デザイン関係者がもっと自由闊達に交流し、議論のできる場にしたい。だから懇親会もメインイベントだ」と語っている。