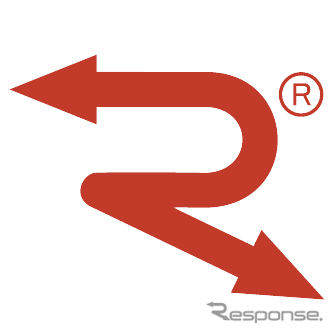事業仕分け、議論が巻き起こったことが前進
様々な議論を巻き起こした与党民主党・行政刷新会議による事業仕分け作業。とりわけ科学分野や芸術分野において、認識不足に由来すると思われる杓子定規な判断があまりにも多く、また予算の再配分ではなく一方的に削減するばかりであったことから、各方面から様々な批判が巻き起こった。
が、企業経営の視点から見ると、仕分け作業は非常にポジティブに感じたという声が多いのも確かだ。自動車業界もそれは同様。
「より良い方向を目指すためには、常に変わり続けなければいけない。仕分け作業の中には間違っているとしか思えない判断も多く見られましたが、硬直化したまま何も変わらないよりは議論が巻き起こっただけ前進したと思う。とくに今は資源・エネルギー政策を含め、国の基盤が大きく変わる可能性がある時期。そういう時に前例を守ることに固執するのは、メリットよりデメリットのほうがはるかに大きい」(トヨタ自動車幹部)
この仕分け作業、予算に関する議論がごく一部とはいえ可視化されたという点でも大いに関心を引いた。仕分け人と称する議員の物言いがあまりに尊大で嫌悪感を与えた一方で、少々の突っ込みに官僚がしどろもどろになるなど、省庁がいかに前例主義に染まっていたか白日の下にさらけ出されたからだ。
◆CO2規制の本質は、自国に有利な枠組みづくり
その仕分け作業などモノともしないエンターテインメント性を呈しているのが、国連気候変動枠組み条約第15回締約国会議、いわゆるCOP15。京都議定書が採択されたCOP3からおよそ12年が経過した今日、世界各国がそれぞれの国益をバックボーンに、ほとんど子供の喧嘩のごときバトルを繰り広げている様が、テレビを通じてお茶の間に届けられているのを楽しんでいる人も多いことだろう。
COP15で議論を巻き起こしているのは中国だ。日本の90年比25%をまやかしと断じ、アメリカの目標は低すぎて話にならないとなじり、EUも不十分と斬って捨てた。挙げ句の果ては、中国を含め発展途上国に資金と技術をよこせ、である。まさに“言いたい放題”であり、当然アメリカをはじめ先進諸国の反発を買っている。
このやり取り、中国にしてもアメリカにしても、その他の国々にしても、それぞれもっともな言い分であるのが問題を難しくしており、それだけに面白い。中国はアメリカを抜いて世界最大の炭酸ガス排出国であり、その中国が今後10年で約2倍ものCO2を出せば、CO2排出規制など到底不可能である。そこにキャップをかぶせようとするアメリカの主張は実に妥当性がある。中国は中国で、世界のおよそ5分の1もの人口を抱えているのにグロスの排出量がアメリカと同じというのは少ないというのも理はある。せっかく経済成長中なのに、頭を抑えられてたまるかというのが本音だ。
CO2規制の本質は、先進国、発展途上国ともに、自分にいかに有利な枠組みを作るかということにある。京都議定書が採択されたCOP3でも今回のCOP15でも、世界の有力国で唯一、お人好しにもフェアすぎるほどフェアな目標を立てたのは日本くらいのものである。
◆武器を使わない戦争、平行線のCO2削減
今回のCOP15は今月18日まで続くが、スペクタクルの本番はむしろこれからである。どういう結末を迎えるか、結果はまだ出ていないが、これほど各国が露骨に国益を前面に出した論争はなかなか類例がない。あるとすれば安全保障理事会くらいのものだ。すなわち、CO2削減はもはや、武器を使わない戦争のようなものなのである。
そのCOP15では、発展途上国や米国なども加えた新たなCO2排出抑制の枠組み、コペンハーゲン議定書の採択を目指すことになっていたが、開幕前からもはや絶望的な状況。ならばせめて政治合意をということでコペンハーゲン合意を目指すことになるが、それも何ら有効性のないものに落ち着く可能性が高い。
折しも欧州では、CO2濃度上昇による温暖化のシミュレーションを行うための元データに改ざんがあったのではないかというスキャンダル騒動まで勃発する有様で、CO2排出量削減の枠組み自体、風前の灯火である。そもそも地球温暖化のシミュレーションが、誤った気象データを入力することで導き出されたものであったとしたら、正しいデータに基づいて再検証しなければならない。
◆CO2より脱石油、自動車メーカーの冷ややかな目
CO2削減を巡るこの混乱に対し、日本の自動車メーカー関係者の多くは冷ややかな目を向けている。社会的責任が要求される社長はじめ首脳はCO2削減をうたってきたが、研究開発部門のスタッフの多くはメーカー問わず「CO2が温暖化の主因かどうかなんてわかったものではない」と語っていた。
ハイブリッドカーやEV、燃料電池車のエンジニアの多くはCO2削減より、脱石油を狙うことをモチベーションとしていた。とりわけ08年に原油が1バレル=150ドル近くまで上昇してからは、“一度あることは二度ある”という意識が一気に高まった。需給バランスの悪化にともなう原油価格の上昇への対策として、技術開発を加速させているのだ。炭素系エネルギーへの依存度を減らす技術を作り上げれば、副次的にCO2など自ずと減るというわけだ。
◆エコロジーとエコノミー、COP15で占うエコカーの未来
環境問題は、イコール経済問題でもある。CO2が本当に温暖化の原因であるとしても、目の前の豊かさの前には何も我慢することができないのが人間の欲望というものだ。先進国では我慢をするというライフスタイルへの転換も一部では可能かもしれないが、甘い果実をまだまだ食べ足りない発展途上国や新興国にとっては、豊かさの追求を我慢することは到底耐えられないことであろう。
COP15は今後の地球規模の環境・経済のフレームワークがどのようになっていくかということを占うという意味で、きわめて興味深い。その行方によって、エコカーの商品力の2大ファクターであるエコロジーとエコノミーの配分にも、微妙な影響が出てくる可能性があるからだ。