カーボンニュートラルに対する世界的な動向を受け、各社の決算発表などではその取り組みが強調される事が多い。自動車業界も例外ではなく、各社の電動化ロードマップの発表やアナウンスを耳にすることが多くなっている。BMWも30日、「BMWのサスティナビリティおよび先端テクノロジーへの取り組み関する説明会」と題するプレスカンファレンスを開催した。
前半、過去・現在・未来とBMWのSDGsへの取り組みや電動化のロードマップなどが発表され、後半はモータージャーナリストの清水和夫氏とヨコハマSDGsデザインセンター長の信時正人氏らを招いたトークセッションが開催された。
BEV・電動化はサスティナビリティの延長
BMWは1972年のミュンヘンオリンピックで、マラソン競技の並走車としてEVを走らせている。欧州勢の中では電動化に積極的でないイメージだが、環境保全やサスティナビリティという点では、1973年に社内に環境保全担当部署を設置し、いまではグローバル企業では当たり前となった投資家向けの「サスティナビリティレポート」は2001年から発行している。初代日産『リーフ』が販売された2年後の2013年には『i3』の市販が始まっている。
フォルクスワーゲンやメルセデスベンツより“走り”のイメージが先行するBMWだが、環境問題に対する意識は古くから高く、電動化やEVはその延長として取り組んでいる。すでに、BMWグループ全体では、2030年までにバリューチェーン全体でCO2の排出量を1/3に、量にして2億トン減らすと宣言している。現在グループではi3とMINIにしか設定のないBEVについては2025年までは対前年比で+50%の販売台数増を目指す。累計の目標数は200万台という。25年以降30年までは、前年比成長率を+20%と設定し、2030年のグローバルでの販売の50%をBEVとする。
すでに発表済みのBMW『iX』のBEVモデルとなる「iX3」も年内には国内での販売が正式に発表される予定だ。『i4』も22年には日本でデリバリが開始される。加えて2023年までに、『7シリーズ』、『5シリーズ』、『MINIクロスオーバー』、『X1』のBEVモデルの発売計画があるという(BMWジャパン広報部の佐藤毅部長)。計画どおりなら2023年の時点で、BMWの全モデルの約9割にBEVモデルが用意される見込みだ。
計画に必要なバッテリーについては外部調達でまかなうとする。BMWは、バッテリー技術についてはまだ進化途中であり、さまざまなソリューションや技術があるとして、特定の方式や製品に限定しない。
グループにはMINIなどBEV専業ブランドになることを表明している会社もあり、英国やEUなどBEV以外の販売が規制されるとはいえ、2025年類型100万台、2030年で全体の半分をBEVにするのは実現可能なのだろうか。
BEV普及のポイントは社会変革
パネルディスカッションでは、BEV普及の課題についての意見もだされた。清水氏は「BMWグループのCEOでもある欧州自動車工業会(ACEA)オリバー・ゼプシ議長は、カーボンニュートラルへの全面コミットを表明しているが、バッテリーの重さや特性から、代替燃料を含めたショートレンジのインフラ整備が重要」と、インフラと一体化した議論と施策の重要性を解く。
信時氏は、横浜市が行った超小型モビリティの実証実験で市民から「EV優遇はCO2削減にならない」というクレームを受けたという。その一方で、高齢化が進む団地でのオンデマンド交通の実験では、地域の商店街や病院の活性化、交通事故の減少、子育て世代からの高評価といった成果も得ている。コペンハーゲン市長の発言を引用し「温暖化対策でまちづくりをするのではなく、市民に選ばれるまちづくりをすべき」との意見だ。
「モデルルームの実証では、EVを家電として家の中に入れるようにして、会議室、オーディオルームにするアイデア、あるいは介護ベッドと一体化できる車両といったコンセプトがだされた。EVやコネクテッド機能が車だけでなく、住宅やライフスタイルが変わるものとしての考え方も普及の鍵になるのでは」(信時氏)という意見もあった。日産などが取り組む自治体との災害協定やEVによるV2Hなども、車と住宅の役割や機能を広げる一例だ。
これに対して清水氏は「EVは回生システムによって位置エネルギーを利用できる。中央高速の八ヶ岳で電池がなくなっても充電しながら降りてくることができる。また、EVの超低重心と重量物がオーバハングしない構造、電子制御は、ガソリンエンジンにできないハンドリング性能や機能を付加する。」とEVの可能性を指摘した。
改革の必然性の違いが各国BEV戦略の差
インフラ問題やカーボンニュートラルなど環境問題と、BEVを取り巻く課題は決して楽観できるものではないが、社会のしくみや生活スタイルの変革をどう受け入れるかで電動化やBEVに対する評価や普及が変わってくるということだろう。
この点で、輸入エネルギーの依存度が高くハイブリッド技術で先行する日本は、CO2削減や社会様式の変化は必然がなく、BEVシフトのハードルは高い。グリーンエネルギーが調達しやすく国策としても電動化・BEVにメリットがある欧米は、モビリティ革命や第4次産業革命へのモチベーションが高い。
BMWのBEV販売計画は、日本の基準では無謀に見えるかもしれない。しかしインフラ整備やエネルギー政策など公的な支援が期待できるなら、読みにくい市場原理を想定したプランより数字は積み上げやすい。また、多くのグローバル企業は中長期のプランを立てつつも、その見直しや軌道修正は日本の平均的な企業より意思決定が早い。状況しだいで目標値は上下させていく備えがあるからこそのプランと見るべきだろう。
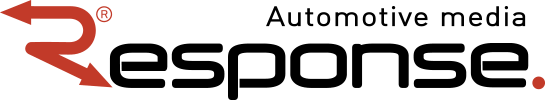


















![スピーカーのアウター化で得られる“本物の音”とは? 効果と施工法を解説![魅惑のハイエンド・カーオーディオ]](/imgs/sq_m_l1/2105044.jpg)