日本航空(JAL)には定時性委員会というものがあり、各部署の代表が月に1回のペースで集まって、定時運航を行うための対策を協議しているという。「決め打ちのような対策はない」というが、これまでにどのような対策を行ってきたのだろうか。
JAL顧客マーケティング本部・商品サービス開発部の南良樹さんは「手の空いたキャビンアテンダントが機内清掃作業を手伝うというのも、定時性委員会の提言から実現したもので、今ではこれが当たり前になっています」と説明する。
発着便の多い羽田では出発時刻が近い便というのも数多く存在するが、こうした便が利用するスポットを離したり、隣接している場合はプッシュバックする方向を変え、誘導路に向かうルートが重ならないようにするなどの工夫も行っている。しかし、それでも恒常的に遅れが生じてしまう便があるそうだ。
こうした場合、遅れの原因が運航側にあるのか、それとも乗客側にあるのかといった分析も行われていて、運航側にあると判断された場合には出発時刻の変更も視野に入れて調整する。JALではなく、管制側にその責があると考えられる場合でも「まずは自己解決を目指す」といい、これまでに航空当局への提言などは一度も行っていないという。
ただ、運航側がどんなに頑張っても、乗客に定時運航の趣旨に賛同して協力してもらわないと目標の達成はできない。
「お客様には可能なかぎり早い時間に空港へいらしていただいて、搭乗手続きが終了した時点で可能なかぎり早く保安検査場を通過していただくことです」という。「これに勝る協力はない」と、居合わせたJALのスタッフ皆が言う。
携帯電話やICカードでチェックインできるようになり、以前よりもギリギリに空港へ到着するという乗客も増えてきた。搭乗手続きは簡略化されたものの、保安検査は逆に年々厳しくなっているために想定外の時間を奪われてしまう。1人や2人ならまだしも、繁忙期などは出発時間に影響を与えるレベルとなってしまう。
「私たちはお客様の時間を大切にするという意味でも定時性の確保に努めております。ほんの少しでもいいのでご協力いただければ幸いです」。これは定時運航を成し得ようとするJALスタッフ全員の願いでもある。
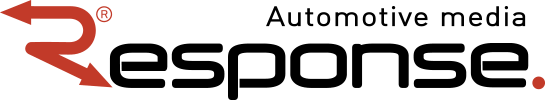























![マツダ『CX-5』新型、欧州からデビュー…ラインナップ最量販のクロスオーバーSUV[詳細画像]](/imgs/sq_l1/2125313.jpg)

