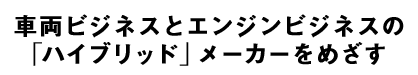| インタビュー/コラム:企業人 | |
|
――“膿(うみ)”を2001年3月期決算で全て出したわけだ。となると、間もなく始まる2001年度(決算期でいうと2002年3月期)は“攻め”に転じることになりますか。
湯浅 アグレッシブに事業展開をしていかなくてはならないと思っています。私は2001年度の経営課題は3つあると考えています。ひとつは、これまでのように国内市場のみを考えるのではなく、世界の市場でコスト競争力、品質、商品力で世界ナンバーワンを目指さなければならないということです。今年後半頃には中型トラックのモデルチェンジがありますが、まず、このモデルチェンジから、コスト競争力、品質、商品力で世界ナンバーワンになるという考えかたを徹底し、2001年度以降の中・長期的なテーマとして取り組んでいくべきだと考えています。 ――国内のいすゞ自動車、三菱自動車、日産ディーゼルとの競争だけでなく、ダイムラー・クライスラーやボルボなど世界の強豪トラックメーカーとの競争に勝ち残ろうというわけですね。 湯浅 世界市場でナンバーワンになるために、決め手となるのはコスト競争力。品質や商品力は欧米の強豪トラックメーカーと比べてもほとんど差はありません。欧米のトラックメーカーと比較しますと、開発のあり方、工場の生産投資のあり方、生産方法、部品の調達方法が、日野をはじめとする日本のトラックメーカーとは全て違う。この違いがコスト競争力の差になっています。 ――コスト競争力の差を縮めるためには何が必要ですか。 湯浅 3つあります。ひとつ目は部品を世界最適調達すること。ふたつ目は世界最適生産拠点を築くこと。最後は数量、つまり生産量を上げることです。とくに数量はポイントですね。日本のトラックメーカーは国内と東南アジア市場を中心に、年間4万台の生産量です。ところが、ダイムラー・クライスラーは年間20万台の生産量。日本のトラックメーカーの約5倍生産しているわけですから、数量効果でいうと、コストへの寄与率で五分の一有利なんです。言い換えれば、コスト競争力で日本のトラックメーカーより圧倒的に上回っているわけなんです。ダイムラー・クライスラーは三菱自動車と資本提携して、さらに数量効果を上げようとしています。日野がコスト競争力で欧米トラックメーカーに対抗するためには部品の世界最適調達や生産拠点の世界最適化だけでは難しい。数量効果をいかに上げるかを、グローバルな戦略として考えていかざるを得ないと思っております。 ――数量効果を上げるために、国内あるいは海外トラックメーカーとの提携(アライアンス)を考えているということですか。 湯浅 可能性があれば国内外を問わず考えています。ただし、アライアンスといっても資本提携もあれば、ビジネスベースでユニットのOEM供給を行うというアライアンスもあるわけで、資本提携までいくとは限りません。 ――日野はいすゞとバスの共同事業会社をつくり、一部報道によれば、トラックでも部品の共通化を両社で進めるということですが、進捗状況はどうですか。 湯浅 部品の共通化というよりも、部品の組み合わせとしてのユニットを共通化していきます。例えば、エンジンは種類があまりにも多いから、ウチはこの種類のエンジンをやめますから、それはいすゞさんのエンジンを使う、逆にいすゞさんがやめたエンジンはウチのを使うというように、ユニット単位での共通化を考えています。部品の共通化ではあまり数量効果が出ません。ユニット単位での共通化のほうが数量効果は大きいでしょうね。 |
||||||||
|
湯浅 ウチも含めて日本のトラックメーカーはエンジンの開発に相当の投資をしています。ところが、欧米のトラックメーカーはカミンズ、キャタピラーといったエンジンメーカーからエンジンを買って載せています。エンジンメーカーが開発したエンジンを、フレートライナー(アメリカのトラックメーカー)やダイムラー・クライスラーは載せている。ですから、例えばカミンズのエンジンは一機種だけで年間20万台ぐらい出るわけです。日本のトラックメーカーはさっきも言いましたが、大型トラックの年間生産台数が約4万台。エンジンは自前ですから、これまた年間4万台しか生産していないことになる。つまり、欧米のエンジンメーカーは日本のトラックメーカーの約5倍の数量です。欧米のトラックメーカーはコスト差が5倍もあるエンジンメーカーからエンジンを買っているわけで、その分コストを大きく削減できることになる。 ――つまり、日野はエンジンの数量効果を上げるために、エンジンビジネスをやるということですか。 湯浅 そう。善くも悪くも石原都知事のおかげで日本の環境規制は世界でもっとも厳しくなります。車両はともかく世界一クリーンなエンジンなら売れるのではないかと思っています。国内トラックメーカーは自前でエンジンを作っていますから、国内トラックメーカーへの売り込みは無理。狙いはカミンズ、キャタピラー、パーキンスなど欧米のエンジンメーカーが降ろしている車両メーカー。そこに「日野のエンジンはいいですよ」と売り込むわけです。エンジンビジネスについてはここ2年間ずっと考えていましたし、すでにエンジンメーカーに売り込んでいます。 ――しかし、エンジンビジネスをやろうにも、日野には海外の生産拠点がありませんね。湯浅 ですから、欧米トラックメーカーあるいはエンジンメーカーとアライアンスがあるかもしれません。アライアンスして、欧米トラックメーカーあるいはエンジンメーカーに日野のエンジンの生産委託をする方法もあるし、あるいは、それらメーカーの工場の一部、または遊休工場を借りて現地生産する方法もあります。 ――資本提携関係にあるトヨタ自動車の欧米生産拠点を使う方法もありますね。 湯浅 選択肢の中では大きいでしょうね。同じトヨタグループとして、協力をあおぎたいですね。 安田有三トップインタビュー Vol. 7(後編)へ >>
|
||||||||
|
||||||||
|
<関連記事> 【シリーズ:安田有三トップインタビュー】 ・日本経団連 奥田碩会長(2002年8月) ・富士重工業 竹中恭二社長(2001年8月) ・三菱 園部社長+エクロート副社長(2001年4月) ・ダイハツ工業 山田隆哉社長(2001年3月) ・日野自動車 湯浅浩社長(2001年3月) ・三菱ふそうトラック・バスカンパニー 村田有造社長(2001年2月) ・いすゞ自動車 井田義則社長(2001年2月) ・スズキ株式会社 戸田昌男社長(2001年1月) ・日産自動車 塙 義一会長(2000年12月) ・トヨタ自動車 張 富士夫社長(2000年11月) ・いすゞ自動車 稲生 武社長(2000年7月) |
||||||||
| 『デイリーニュースランキング』の登録はこちら |
| auto-ASCIIトップページへ |