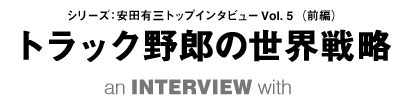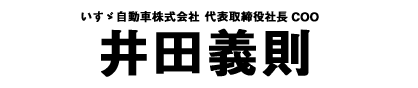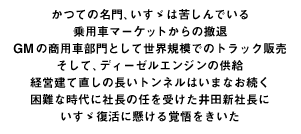[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
|
 |
 |
インタビュー/コラム:企業人 |
 |
[an error occurred while processing this directive]
【安田有三トップインタビュー Vol. 5(前編)】トラック野郎の世界戦略---いすゞ井田義則社長
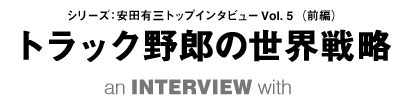 |
 |
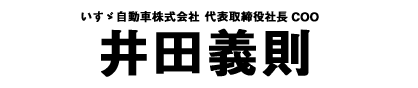 |
 |
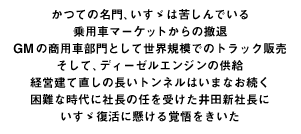 |
 |
●合併は意味がない
――トラック業界は未曾有の不況の只中にありますね。大型トラックの全体需要は2000年暦年で約8万台弱と、ピーク時の半分程度まで落ちこんでいる。厳しい市場環境の中で、いすゞ自動車をはじめ、三菱自動車、日野自動車、日産ディーゼルの大型トラック4社が激しくしのぎを削っているわけですが、今後全体需要の大幅な伸びが期待できない日本国内のトラック市場で、4社がすべて生き残るのは無理だ、との観測があります。つまり、大型4社の再編は必至だというわけです。そんな中でいすゞは、すでにバス事業で共同した日野と、トラック事業でも両社の間で部品の共通化を図ることになった、と新聞に報じられました。いすゞと日野は今後さらに関係を緊密化し、最終的には合併まで進むということはないですか。
井田 バス事業だとか、トラック事業での部品の共通化とか、部分的なところでは日野さんとの協力関係はありえますが、合併していっしょになるなんて、あまり意味があることだとは思わないですね。
――なぜですか。
井田 大型トラックメーカー4社が国内市場だけで戦っているなら、どこかと合併して規模を大きくしたほうが勝つかもしれない。でも、これからは世界のトラックメーカーを相手に戦わなければならなくなるわけで、国内トラックメーカー同士が合併してもしょうがない。アメリカやヨーロッパでディーゼルエンジンやトラックが売れるわけではないわけだから、国内トラックメーカー同士が合併しても、世界のトラックメーカーとの競争には関係ない。世界のトラックメーカーは、ダイムラー・クライスラーとフレートライナー(アメリカのトラックメーカー)グループ、ボルボ・ルノーと三菱自動車グループ、ゼネラルモーターズ(GM)といすゞグループの3大グループが「ビッグスリー」といわれています。いすゞは、ダイムラーグループやボルボグループと世界で戦っていくために、グローバルな事業展開を行っているわけです。
――なるほど。いすゞ以外の日本国内3社は、東南アジア以外にはほとんど拠点がない。相変わらず日本市場のみを考えた事業展開をしている。いすゞのように世界のトラックメーカーを相手に戦うためにグローバルな事業展開をしているところとは、進むべき道が違っているわけですね。
井田 いすゞは、商用車で世界の巨人となっていくためには、アメリカやヨーロッパで頑張らなくてはいけないと考えているわけです。こんなことをいうと、いすゞは国内でもたいして売れもしないくせに、といわれてしまうかもしれませんがね(笑)。
――確かにここのところ、いすゞは国内で苦戦していますね。もっとも、これだけ全体需要が落ち込んでいるので、いすゞ以外の3社も同じように苦戦しています。いすゞは業績を立て直すために、構造改革計画を打ち出しましたが、その効果はいまひとつあらわれていないように思います。原因は何ですか。
井田 大型トラックの全体需要の落ち込みや為替変動など世の中の変化があまりにも激しく、しかも速かった。構造改革が世の中の変化の速さに追いついていけず、構造改革をやる、しかし利益が出ない、するとまた構造改革をやる。が、またも利益が出ない、どんどん業績が悪化したわけです。
――すると、構造改革計画を改めて見直さざるを得ない。
井田 景気の動向やお客さまのマインドなどから考えると、はっきり全体需要が良くなるとはいえませんが、もっと悪くなるとも思えない。2000年暦年の全体需要が約8万台という線を下回ることはないと思っています。全体需要などの環境要因があるていど見定めることができるようになりましたので、それをベースに最終的な構造改革計画を作成し直そうと、いまは作業に取りかかっています。
――以前打ち出された構造改革計画の中で注目されたのが、販売会社の広域化です。普通販社は都道府県を単位にしているのを、いすゞは、九州・四国・中国・近畿・東海の5地区で、府県単位の販社をまとめてひとつにして、広域化を図りました。この販社の広域化も見直すことになりますか。
井田 販社の広域化は、広域化することが目的でなく、いすゞのお客様により満足してもらうサービスを提供することが本来の目的なんです。例えば、北海道でいすゞ車を買ったお客様が東京でどうしても修理しなければならなくなった。そこで、いすゞの東京販売店に北海道のお客様が修理を頼んでも、東京は自分のところで買ったお客様じゃないし、工場も混んでいるからと、真っ先には修理はしない。そういう優先順位をつけてしまう。だけど、北海道だろうが東京だろうが、いすゞのお客様であることは違いがないわけです。北海道でいすゞ車を買ったお客様が東京で修理するというのはよっぽど困ったからです。それを東京の販売店の優先順位で修理が遅れるというのはいかがなものか。こういうところを是正する目的で販社の広域化を行うことにしたわけです。販社の広域化は、いすゞのお客様により高い満足度を与えることが本来の目的であり、その本来の目的を十分意識しながら微修正を加えていくつもりです。
《写真=菊地 慶》
|
|
安田有三トップインタビュー Vol. 5(後編)へ >>
|
<関連記事>
【シリーズ:安田有三トップインタビュー】
・日本経団連 奥田碩会長(2002年8月)
・富士重工業 竹中恭二社長(2001年8月)
・三菱 園部社長+エクロート副社長(2001年4月)
・ダイハツ工業 山田隆哉社長(2001年3月)
・日野自動車 湯浅浩社長(2001年3月)
・三菱ふそうトラック・バスカンパニー 村田有造社長(2001年2月)
・いすゞ自動車 井田義則社長(2001年2月)
・スズキ株式会社 戸田昌男社長(2001年1月)
・日産自動車 塙 義一会長(2000年12月)
・トヨタ自動車 張 富士夫社長(2000年11月)
・いすゞ自動車 稲生 武社長(2000年7月)
|
|
 |