脱石油の有力なソリューションとして期待のかかる電気自動車(EV)の性能を決定づける最重要部品といえば、電力を蓄えるリチウムイオン電池である。今日、バッテリーメーカー各社は次世代電力網スマートグリッドに使う蓄電装置などの需要増も見越して、大型電池の研究開発を加速させている。
「バッテリー耐久性はまさにEV普及のひとつのカギ」
電動車両用電池のメジャーサプライヤーといえば三洋電機、パナソニック、GSユアサ、日産・NEC系のオートモーティブエナジーサプライなどの名が挙がるが、その分野で最近、東芝が存在感を上げている。2010年末にホンダが二輪EV『EV-neo』を皮切りに、三菱自動車『i-MiEV M』、『MINICAB-MiEV 10.5kWh』、ホンダ『フィットEV』と、東芝のリチウムイオン電池「SCiB」を採用するEVが続出したのだ。
EV分野で急に東芝が頭角を現したのは、SCiBが他のリチウムイオン電池にない特性を持っているからだ。まずは耐久性。東芝はSCiBの寿命について、空から満充電までの深充放電を4000回繰り返しても初期性能の9割を維持できるとしている。これはリチウムイオン電池のなかでもケタ外れの数字で、仮に 航続距離200kmのEVを2日に1回充電する場合、寿命は実に20年以上ということになる。
「あえて言えば、EVのバッテリーは高価な部品です。そのEVを普及商品にするためには、クルマが廃車になるまでバッテリー交換不要というのは前提条件です。電池の性能が維持されていれば、中古車となっても価値が維持され、中古EVでも市場が形成される。その先もスマートグリッド用の定置型バッテリーとして再使用できるくらいの耐久性があれば、下取りでさらにコストを分散させることができる。EVの泣きどころである高い初期コストをこのように分散できれば、最初から残価設定によってリース価格を下げることも可能になる。耐久性はまさにEV普及のひとつのカギだと思います」
東芝のSCiBビジネスの技監 本多啓三氏は長寿命のメリットをこう語る。
リチウムイオン電池で最も安いのは、世界で大量に生産されている18650(パソコンのバッテリーモジュールなどに組み込まれている乾電池に似た形状のセル)タイプと呼ばれるもので、容量1Whあたり25円程度だ。
「現在、EV用電池の量産価格は1Whあたり100円を切るくらいのところまできています。量産が進むにつれてコストはさらに安くなるでしょうが、大量生産で徹底的に安くなった18650のレベルに近づくことはできても、これを下回るレベルにはならないと思う。製品単体のコスト低下に限界がある以上、ライフサイクルの長い電池がコスト分散の点で優位に立てる。SCiBはその領域ではトップランナーと自負しています」(本多氏)
◆低温環境下でも性能を維持
SCiBの特徴は単に優れた充放電の特性ばかりではない。クルマにとって必要とされる低温環境下での耐久性も傑出している。自動車メーカー各社のEV開発が加速しはじめたのは2000年代半ば頃だが、ほどなく各社の開発現場では低温時にリチウムイオン電池が激しく劣化することが問題視されるようになった。EVを冬の北海道などの寒冷地で走らせると、モーターが発電する抗力で減速する回生ブレーキが強めに作動するだけで、バッテリーが急速にダメになってしまうというケースが続出したのだ。
「もともとリチウムイオン電池は熱すぎても冷たすぎてもダメというデリケートな電池。ハイブリッドならエンジンの熱でバッテリーを保温するなどの方法も考えられますが、EVはそうはいかない。低温環境でも劣化しないことは、エネルギー密度など数値的な性能よりずっと大事なんです。将来的にはいろいろな技術が出てくるでしょうが、現時点では東芝のSCiBは最良のソリューションのひとつだと思います」(自動車部品世界大手の上級エンジニア)
リチウムイオン電池の性能競争でよく話題となるのは、プラス側の電極材料だ。コストが安く安定性も高いマンガン酸リチウム、高密度化が期待できるニッケル酸リチウム、また最近登場した最新鋭の三元系(ニッケル・マンガン・コバルト)リチウム等々。しかし、SCiBの最大の技術的特徴はその正極側ではなく、負極側にある。通常、負極には炭素系の物質が使われているのに対して、SCiBの負極材料はチタン酸リチウムという物質でできている。
◆技術の「伸びしろ」にも期待
「SCiBの開発はもともと、充電時間を数分間に短縮したいという動機でスタートしました。負極にチタン酸リチウムを採用したのもそのためだったのですが、EVやスマートグリッド用の大型リチウムイオン電池に求められる性能を検証すると、急速充電はもちろん、たとえケースが壊れても発火しないという安全性、耐久性、幅広い温度特性といったSCiBの特性が活きることがわかった。それもあって事業化に踏み切ったんです」(本多氏)
SCiBは最初から自動車エンジニアにポジティブに受け取られていたわけではない。「バッテリーは電気化学のなかでも最も奥深いもののひとつ」(トヨタ自動車幹部)で、機械工学が主体の自動車エンジニアにとっては専門外のようなものだ。そのこともあって、バッテリーの特性を検証するときも出力密度、エネルギー密度、電圧などのスペックシートの数値が重視されがちだった。
SCiBはそれらの数値が傑出しているというわけではなく、電圧に至っては一般的なリチウムイオン電池の3分の2程度しか出ないなど劣勢な部分もある。電動品のエネルギー効率を向上させるには、電圧を上げることで熱損失の原因となる電流を少なくしてやるというのがセオリーだ。SCiBで他の電池と同じ電圧にするには他のリチウムイオン電池の1.5倍のセルを直列につながなければならない。それをネガティブにとらえるEVエンジニアは結構多く、筆者もEVブームの走りの頃にそういう評判を少なからず耳にした。
しかし、低温特性や耐久性の確保に四苦八苦するなかで、自動車メーカー各社のEV開発陣の間では今や「少々無茶な使い方をしても大丈夫な電池のほうが、結局は性能を目一杯使い切れる。見た目のスペックより堅牢さ、耐久性のほうが重要だとわかってきた」(ホンダ関係者)といった声が大勢を占めつつある。
「PR当初、スペック優先の比較では相手にしてもらえないこともしばしばでした。ですが、最近は自動車メーカーの認識も変化してきました。もちろん我々も現状の性能に満足しているわけではありません。絶対的な性能の向上にも力を入れています。09年頃に比べてエネルギー密度は、既に50%アップしていますが、今後さらに強化していきます。また、高電圧化を含めた、高性能化の研究も、鋭意進めています」(本多氏)
このチタン酸リチウムという材料、何も東芝だけが研究していたわけではない。チタン酸化物を電極材料に使うという研究は、古くから各国の電池研究者が行ってきていることだ。
「実は電池の研究開発の世界でも、電圧が低くなるというチタン酸リチウムの特性をネガティブに捉える向きが少なくなかった。加えてこのタイプの電池を安定的に量産することが容易ではないと考えられていたこともあって、大型の実用電池の開発に取り組んだのは東芝だけでした。大量生産を実現できるシステムを構築できたのは、ある意味コロンブスの卵的なところもあった。この分野では当面、優位性を維持できると思っています」(本多氏)
東芝は今日、SCiBを武器にEVの駆動用バッテリーやスマートグリッドの定置型蓄電池など大型電池分野でのシェア拡大を目論んでいる。もっとも、他の電池メーカー、材料メーカーもチタン酸リチウム材料に対抗し得る新材料、新製法などの研究を加速させている。大幅な需要増が見込まれている大型バッテリーを巡る業界戦争。その動向は今後も注目に値しよう。
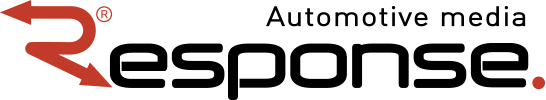









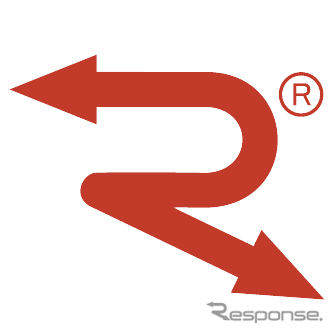














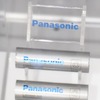




![中国製部品の急成長で2025年以降日本製の車載半導体は使われなくなる…名古屋大学 山本真義 教授[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2003386.jpg)




