スバルのDセグメントミッド中型セダン『レガシィB4』で北関東を450kmほどドライブする機会があった。ミドルレンジではあるがインプレッションをお送りする。
レガシィB4の長所と短所
1989年に登場した初代レガシィは、倒産も噂されるほどの経営危機に直面していた富士重工業(現在のスバル)が乾坤一擲で放ったモデル。前年に設立されたばかりのモータースポーツ子会社STI(スバルテクニカインターナショナル)の手で10万km速度記録へのチャレンジが行われ、223.345km/hの世界記録を樹立するなど性能を誇示。これによる技術イメージの向上、およびステーションワゴンが大人気を博したことで、スバル復活の狼煙を上げるモデルとなったことは、昭和世代のスバリストにとっては懐かしいドキュメントであろう。
以後、レガシィはスバルの屋台骨を支える基幹車種として発展したが、セールスのメインフィールドが日本からアメリカに移行するにつれて性格が変化し、現行の第6世代レガシィB4はトヨタ『カムリ』、ホンダ『アコード』と同様、もっぱらアメリカの庶民層をターゲットとするミッドサイズセダンとなった。
試乗車はレザーインテリアや18インチ径ホイールなどの装備を持つ上位グレードの「リミテッド」。2.5リットル水平対向4気筒エンジン+チェーンドライブCVT、AWD(4輪駆動)、先進安全システム「アイサイト3」や後方警戒安全装備は基本モデルと変わらない。オプションとしてムーンルーフ、カーナビなどが装着されていた。
試乗ルートは東京都心を起点とした北関東ルートで、筑波山、桜川、古河、宇都宮などを周遊し、総走行距離は449.7km。大まかな道路種別は市街路2、郊外路5、高速1、山岳路1。路面コンディションはドライ。全区間1名乗車、エアコンAUTO。
では最初に、ドライブで体感されたレガシィB4の長所と短所を5つずつ挙げてみよう。
■長所
1. 地味な外観、凡庸なスペックからはとても想像できないシャシーのダイナミック性能の高さと懐の深いハンドリングチューン。
2. 初期型からセッティングが変わり、気持ちよくなったCVT。
3. 郊外路では非ハイブリッドとしては十分良い燃費。
4. いい意味での“ユルさ”を感じさせる乗り心地と居住感。
5. 売りの「アイサイト」だけでなく、安全に関する独創的なアイデアがいろいろ盛り込まれていること。
1. せっかくの素晴らしいシャシーチューンがまったく似合わない地味な外観…と言うか、モデルのキャラクターそのもの。
2. 都心部ではやはり落ちる燃費。「e-BOXER」ではなくISGタイプの軽量なマイルドハイブリッドを積極採用するくらいの勢いがほしい。
3. シートは頑張っているが、それ以外のインテリアの質感が大衆車然としていること。
4. アメリカモデルの常だが、車体サイズのわりに室内の収納スペースが不足気味。
5. ロードノイズは平均的だが、エンジンのノイズ・バイブレーションがいささか過大(音質的にはスバリストが喜びそうな)。

国産セダンに敵なし?
現行レガシィB4はアメリカのノンプレミアム中型セダン丸出しの地味きわまりない内外装デザインとは裏腹に、いったん郊外に出るや、とてもファントゥドライブなクルマであった。
とくに傑出していたのはシャシーチューニング。走り屋が集まる表筑波スカイラインをちょっと流してみたが、タイトコーナーでの回頭性、そこから脱出する時の揺り戻しの穏やかさ、タイヤの摩擦を一気に使い切らないコントローラブルなサスペンションセッティング、アンジュレーション(路面のうねり)に煽られても失われないスタビリティ等々。
クルマとしてのキャラクターはまったく違うが、チューニングの方向性や質の高さは何度かサーキットやクローズドコースでテストドライブした同社のスポーツセダン『WRX STI』と軌を一にするものと感じられた。試乗車には第6世代モデルで採用されたオプションの「スタブレックスライド」が装備されていなかったが、ナチュラルでむしろ好感が持てた。
これだけの性能を持ちながらフラットライドな乗り心地を維持しているのもすごい。現行レガシィB4に乗るのはデビュー直後にショートテストドライブをやって以来だが、初期型が妙に揺すられ感の強い乗り心地であったのに対し、幾度かの改良を経た今は打って変わって滑らかだ。その滑らかさのなかにしっかりと路面のインフォメーションが含まれているのも好ましかった。
今回はミドルレンジドライブであったが、感触的にはロングドライブ耐性も高そうだった。ドライバーに直進感を与えるフィールの作りは『インプレッサ』ほどではないが、日本勢のミッドサイズセダンのなかではダントツで、クルマの意外な動きに神経をすり減らさずにすむことうけあいだった。
日本勢でライバルとして挙げられるのは、トヨタ自動車『カムリ』、ホンダ『アコードハイブリッド』、マツダ『アテンザ』、日産自動車『ティアナ』あたりだが、ことツーリングカーに求められる走りの質感という点では、それらはレガシィの敵ではない。試さないかぎり信じられないかもしれないが、不整な路面にもしっとり練りつくようなロードホールディングや、それをうまくいなす乗り心地は、アウディ『A4』相手でも一歩も引けを取るものではないのだ。
アメリカが主戦場のスバルゆえ
残念なポイントは何と言っても、こんな素晴らしいテイストが与えられたモデルのキャラクターが、なんとも平凡で華のないアメリカのノンプレミアムミッドサイズセダンそのものであるということに尽きる。おそらくレガシィB4の乗り味がこんなふうになっているということは、世間のクルマの顧客のなかでも0.1%も知るまい。当然である。スバリストと呼ばれる伝統的スバルファンでさえ、レガシィB4に興味を持つ人はごく僅か。積極的に遠乗りを楽しむ層はさらにその一部でしかないであろうことは想像に難くない。
このところ、スバルの経営陣はほとんどアメリカしか見ていない状況だった。スバルのアメリカ好きは何も今に始まったことではない。何しろちょうど50年前、『スバル360』でアメリカビジネスを始めたくらいの“古参”なのだ。が、今は技術開発からクルマの仕様まで、アメリカに引きずられている感があまりに強い。
レガシィセダンがワゴンと分化して「B4」のサブネームを持つようになったのは20年前の3代目から。この代までは経営的にはアメリカ重視であったが、アメリカの顧客に媚を売るようなクルマづくりというわけではなかった。ほぼ同時期にデビューしたスポーツセダン『アルテッツァ』を販売でうっちゃり、トヨタ自動車を切歯扼腕させるくらいの存在感を示していたのだ。それから20年ほどが経った今、すっかり“アメ車”と化したレガシィB4は日本ではスバル社員やOB、“クルマはスバル”と決めているような中高年層のファン相手に細々と売れるだけのクルマになった。
スバルは全社員に対する実験部隊のスタッフの割合が日本の自動車メーカーの中でも突出して高く、技量もピカイチだ。彼らが日本での販売が難しいことが容易に想像のつく現行レガシィをちょっとでも魅力的なものにしようと、日本仕様のチューニングに心血を注いだであろうことは、テストドライブを通じて痛いほどに伝わってきた。だが、その努力が日本で報われることはおそらくあるまい。高品位で時にアスレチックという雰囲気が、今のレガシィB4にはないからである。
こういう味付け能力が生かされるミッドサイズセダンを生み出し、スバルブランドが上の世界に行くのは、スバルがアメリカ一本足打法から脱却し、名実ともに“世界のスバル”を目指すことを決意するときであろう。それがいつになるのか、そもそもそういう時が来るのかはわからないが。
予想をはるかに超えたシャシー
雑談が長くなってしまったが、個別のファクターについてみていこう。まずはレガシィB4の最大のハイライトと感じられたシャシーチューンについて。デビュー当初はハーシュネス、揺すられ感が強めだった乗り心地は大幅に改善され、とても滑らかになった。直進性の良さは出色もので、高速道路やバイパスのクルーズは気持ちよく、かつ安心感があった。
予想をはるかに超えて良かったのは、前述のようにワインディングロードでのパフォーマンスだった。レガシィB4の水平対向エンジン&変速機縦置きのパワーユニットは左右対称配置というメリットがある半面、エンジンが前輪の前にどっかりと被る配置にならざるをえない。排気量2.5リットルエンジンというウェイトを前オーバーハングにぶら下げていたら、さすがに回頭性は悪いのではないかと思ったが、実際にドライブしてみると、コーナー進入でのブレーキ→旋回という一連の運転操作における鼻先の入りのスムーズさは、ライバルと比較しても飛び抜けて良かった。
旋回中のドライビングアクションに対する寛容性も抜群であった。タイヤは225/50R18サイズのダンロップ「SP SPORT MAXX 050」だったが、タイトなコーナーでもそのタイヤが微妙に滑り出すところからしっかりとインフォメーションが伝わってきた。ステアリングを切り足すと、切り足しの量に応じてタイヤのグリップが連続的に失われていくのが手に取るようにわかる。結果、まったく怖くない。おそらくウェット路面の高原道路などを走ったりしても、安心感はきわめて高いレベルで保たれるだろう。
しかも、そういう特性が、綺麗でない路面でも維持される。アウト側のサスペンションがかなり縮んでいる状態でギャップ、盛り上がりを踏んでも、そこからさらにサスペンションがたわみ、グリップが維持される感覚で、ほとんどアウディA4やボルボのRデザインモデルばりであった。
コーナリング姿勢は、後発のインプレッサよりいいくらいである。ロールは前外側と後内側のホイールを軸とした綺麗なダイアゴナル(対角線)で、S字コーナーの切り返しでもスキーのパラレル滑降くらいナチュラル。ドライブしていて、何でこんなファミリーカーにこんな足を与えるのかと、理解に苦しむほどであった。タイヤサイズに余裕があるためコーナリングスピードも速く、昭和生まれで若い頃には峠を攻めたというような腕に覚えのある向きなら、スポーツカーをびっくりさせるような走りを見せることも可能だろう。ローター温度が上がるほど走ったわけではないが、2ポッド式のブレーキの初期タッチは良好だった。
もっとパワーを
次にパワートレイン。2.5リットル水平対向DOHC+チェーンドライブCVT「リニアトロニック」という構成だが、普段使いには十分なものの、シャシー性能に対してはいくら何でもアンダーパワーもいいところであった。といって、高出力エンジンがラインナップされているわけでもない。アメリカでは3.6リットル6気筒も売られているが、日本には合わないだろう。こういう日本市場への適合性の薄さも、開発陣の心意気に反してレガシィB4を何だかよくわからないモデルに見せてしまう要因であろう。
初期型に対して改良されたなーと感じられたのはCVTのシフトスケジュールで、ふわふわと揺れ動くのではなく、車速の上昇とエンジンの回転上がりがある程度リンケージするようなタイトなセッティングになっていた。スロットル開度が大きいときには擬似有段ATのような動きを見せるが、その変速もなかなかシャープ。ただし、手動変速のときにはそこまでの切れ味はなかった。
燃費は交通状況や運転の仕方で大差が出るという印象だった。東京・葛飾で満タン給油後、高速道路と地方道で筑波山にアプローチ、表筑波スカイラインまで一気に駆け上り、その後茨城の古河市街、さらに国道4号線旧道を経て栃木の宇都宮郊外に至るというパターンで307.6km走行後に給油したところ、満タン法による実燃費は12.4km/リットル。宇都宮から国道新4号線経由で葛飾まではトロトロ走りというわけではないものの、スロットルワークにそれなりに神経を配り、惰力を応用しながら走ったところ、実燃費は17.7km/リットルまで伸ばせた。燃費を測ったのはこの2区間だけだが、平均燃費計は実数に対し、ほぼ正確な値を表示した。
このように、それほど混雑していない市街地や郊外路では、非ハイブリッドのミッドサイズセダンとしては十分にアクセプタブルな燃費であったのだが、弱点は混雑した東京都心のような都市走行。その区間では平均燃費計値ベースで10km/リットルを超えることができず、8~9km/リットル台で推移した。スロットルをわずかに開けた低負荷域の熱効率がトップランナーに対して劣っていること、またアイドリングストップシステムがいまひとつ粘りに欠け、信号待ちがちょっと長くなったり連続したりすると再始動したりアイドリングストップしなかったりという状態であったことが燃費低下の主因と推測された。
スバルは「e-BOXER」と称するパラレルハイブリッドシステムを持っているが、重量のわりにパフォーマンスはあまりいいとは言えない。変速機、できれば有段式のそれにISG(エンジンスターター、駆動モーター、発電機の3役をこなす1モーター式パラレルハイブリッド)を組み込むなどすれば、ドライバビリティに悪影響を与えず燃費向上を図れるであろうし、珍品好きのスバリストたちをちょっとでも萌えさせるかもしれないのになどと思った。
車内の快適性、仕立ては
車内の快適性は十分に高い。ロードノイズのカットはトップランナーというわけではなく普通。ただ、舗装のざらつきが強めのところを通過するときのザーッというホワイトノイズのような音はほどよく遮断されていた。ロードノイズに比べ、ちょっと大きいかなと思ったのはエンジンノイズの室内への透過で、結構聞こえる。
面白かったのは、一時はごく控えめになっていたドロロロロという水平対向っぽい音が強調されていたこと。水平対向エンジンもとうにエキゾーストマニホールドが等長化されており、そういう音が必然的に高まるということはないので、これはちょっとした演出なのだろう。その音が発するごくわずかな微振動とあいまって、スバルファンならちょっとノスタルジーに浸れそうな感じであった。乗り心地は後席については確認できなかったが、ドライバーズシートに座っているかぎり、すこぶる気持ちよかった。
そんな動的質感とは裏腹に、インテリアの仕立てはチープであった。シートはダブルステッチの、そこそこ見栄えのする工作がなされていたが、それ以外の部分は大衆車の域を出ない。とくに安っぽかったのはオーディオコントロール部で、小さい銀メッキプラスチックのスイッチの感触は、ディスカウントストアなどで売られている安物ラジカセのごときもので、決して褒められたものではない。ダッシュボードその他のトリム類も大衆車レベルで、質感の面ではWRXシリーズのほうがよっぽど高級であるように感じられた。アメリカではノンプレミアムミッドサイズの白物モデルなのだろうが、日本では平均よりずっと高い所得層の顧客が乗るのだから、何とかひと工夫ほしいところだ。
安全思想について。レガシィB4には先進安全システム「アイサイト・バージョン3」のみならず、駐車場での近接車両警報など充実装備となっている。実際に高速道路などで使ってみても、相変わらず装置の作動状況は良好。とくにアダプティブクルーズコントロールのスムーズさは印象的だった。レーダーが付くとなおいいのではないかと思うものの、実性能が出ているので今のところはこれで十分であろう。悪天候に弱いという欠点があるが、筆者の経験ではカメラ部にシリコン撥水剤を塗りこんでおくと相当な雨にも耐えるようになるので、手軽な対策としてはおすすめだ。
スペックや機能に表れない工夫
ところで、今回のドライブ中にあちこちを観察したところ、スペックや機能に表れない工夫がいろいろあるものだなあと興味深く思われた。ひとつはラゲッジルームのカーペット下の工具。ごく弱い照明しかない場所でも何がどこにあるか、ひと目でわかるところにきっちりと整理されて置かれているのだ。筆者は暗所で工具をまさぐったことがあるが、工具が奥まったところにひとまとめにされていたり、バラバラに置かれていたりすると非常に使いにくい。万が一のときというのは万がゼロとは違い、起こりうるものなのだという哲学が肌身に感じられた。
もう一点、トランクリッドに引っ張ると中から開けることができる紐がついていること。電装系が全部死に、車内に完全に閉じ込められてしまっても、最後の手段として窓ガラスを割らずともリアシートのトランクスルーから脱出することができるのだ。スバルがこういうものを作ったのは突拍子もない思い付きによるものではあるまい。実際にフィールド上で困った経験を持つ顧客がおり、それを聞いて設計に反映させたのであろう。こういう真摯さはスバルのいいところだ。
まとめ
まとめに入る。レガシィB4は乗ってみると随所に素晴らしい部分がある、大変面白いミッドサイズセダンであった。とくにシャシーの味付けは今回乗ってみた限りでは苦手とする路面状況がなく、国産同クラスのライバルを寄せ付けないもの。快適性も十分に高い。雨天走行の機会はなかったが、過去のスバル車のドライブ経験に照らし合わせれば荒天時のAWDのパフォーマンスも申し分ないことだろう。
が、かりに知人から国産ミッドサイズセダンが欲しいんだけどと相談を持ちかけられて、レガシィをリコメンドするかといえば、なかなか難しいところである。日本でこのクラスに乗るカスタマーの大半が求めるのは先進安全システム、路面からの当たりの柔らかさや静粛性の高さなどは当たり前で、決め手となるのは大抵、内外装の質感、ハイブリッドやターボディーゼルなどの現代的な燃費デバイスであったりするからだ。
その決め手を欠くレガシィB4をおススメできるとすれば、最初からスバル車ご指名、雪国に住んでいる、燃費はそこそこでいいからとにかく足のいいクルマがいい、アウディやボルボに興味があるけどちょっと手が届かない…といった人であろうか。とことんドライブを楽しみ、積算走行距離を気にせず乗り倒す人にも好都合であろう。
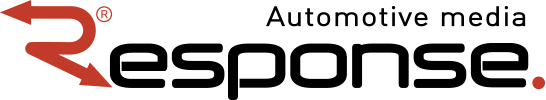









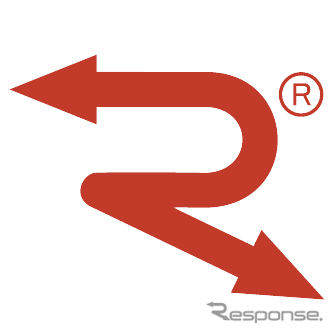





























![【VW ゴルフ TDI R-Line 3700km試乗】走行性能、ユーティリティ、経済性で対抗できる国産車はあるか[後編]](/imgs/sq_m_l1/1957408.jpg)
![【VW ゴルフ TDI R-Line 3700km試乗】もはや高嶺の花となったゴルフ、ツーリング性能は[前編]](/imgs/sq_m_l1/1951402.jpg)



![スバル フォレスター Advance、アクティブにより使いやすく…利便性と安全性が向上[詳細画像]](/imgs/sq_l1/1990151.jpg)









